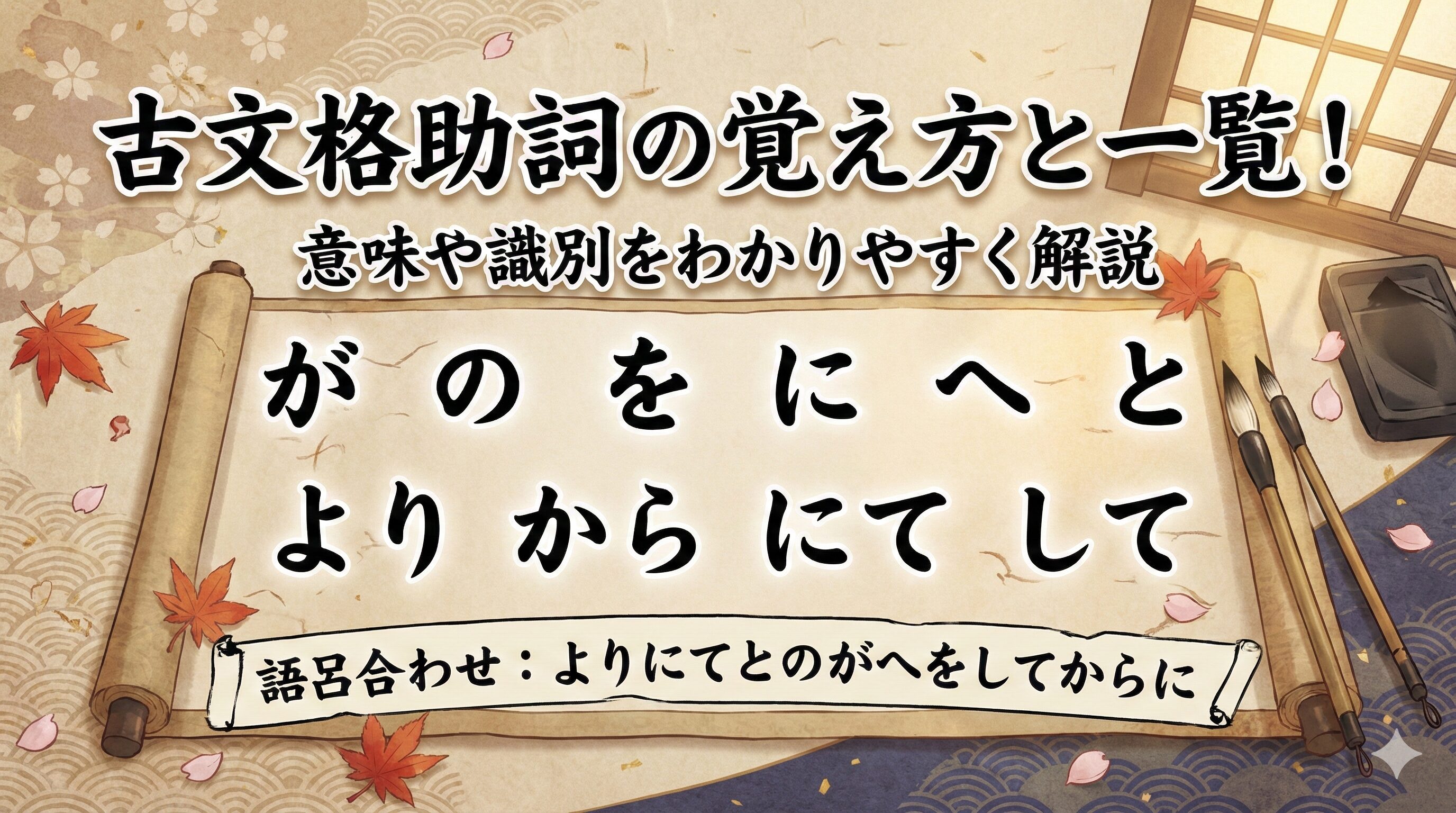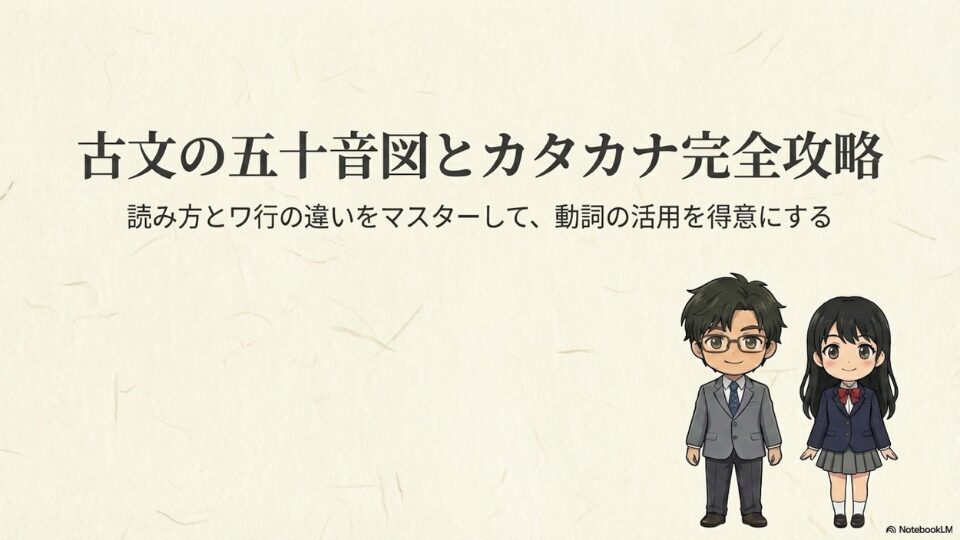助動詞「き」「けり」の違いを基本から解説!意味・接続・活用【練習問題付】
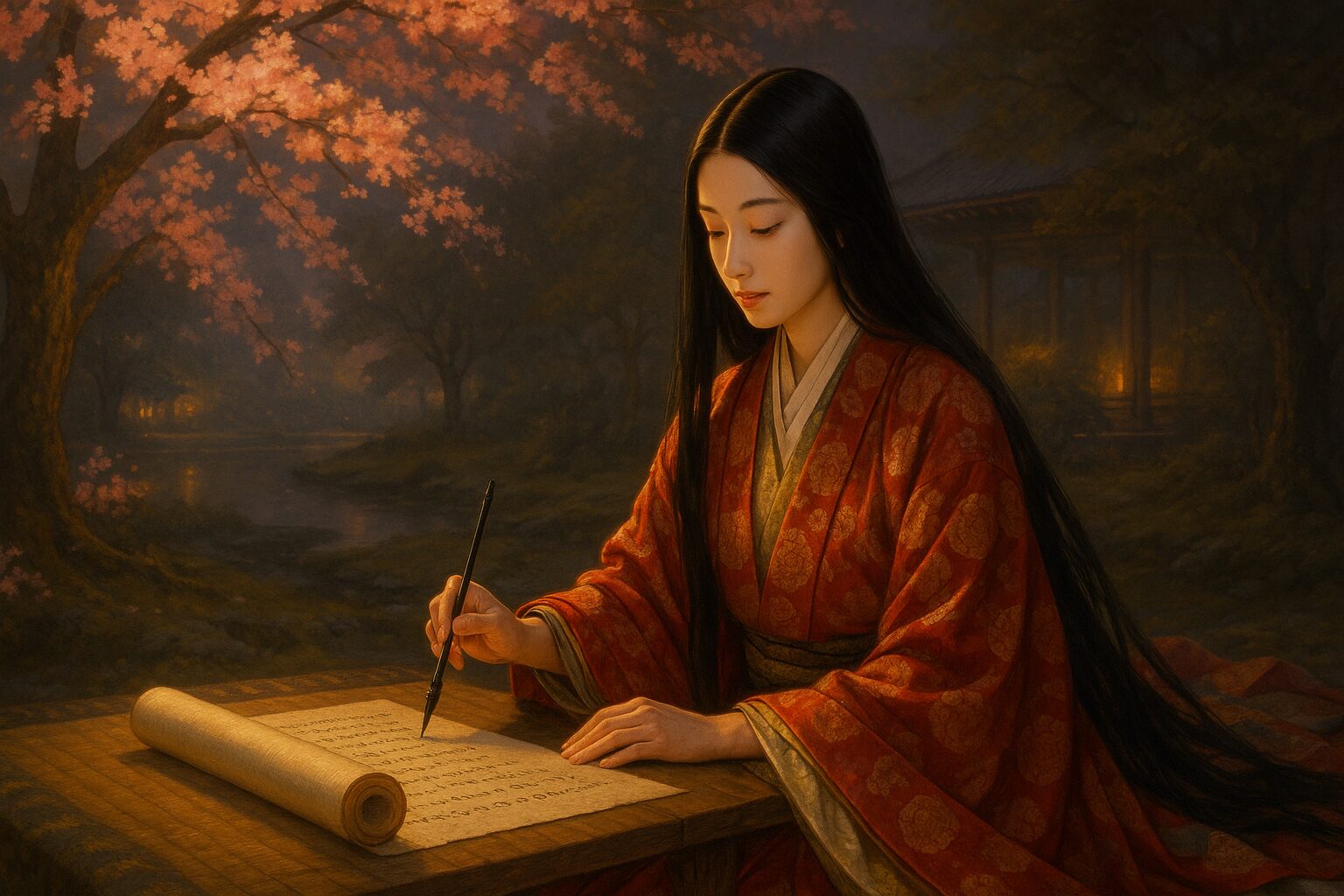
古文の学習で「助動詞 き けり」の違いがよくわからず、困っていませんか。
「どちらも過去を表すみたいだけど、具体的な意味はどう違うの?」「活用表を見ても、どう使い分けるのかピンとこない…」そんな悩みを抱えている方も多いかもしれません。
確かに、助動詞「き」と「けり」は古文において非常に重要でありながら、混同しやすいポイントの一つです。
しかし、ご安心ください。
この記事では、「助動詞 き けり」について、それぞれの基本的な「意味」の違いから、どのような語に付くのかという「接続」のルール、そして複雑に見える活用を一覧で確認できる「活用表」まで、初心者の方にも分かりやすく解説します。
さらに、多くの方がつまずきやすい「き」と「けり」の「識別」方法についても、明確な見分け方のコツを詳しくご紹介します。
記事の最後には、内容の理解度を確認できる「練習問題」も用意していますので、知識の定着に役立てていただけます。
この記事を読み進めることで、「き」と「けり」への苦手意識がなくなり、古文読解がよりスムーズになるはずです。
- 助動詞「き」と「けり」の根本的な意味の違い
- 文脈から「き」と「けり」を識別する具体的な方法
- 「き」と「けり」それぞれの正しい活用パターン
- 各助動詞がどのような言葉に接続するかのルール
助動詞「き」「けり」の基本を徹底解説

- 古文の助動詞「き」「けり」とは?
- 助動詞「き」が持つ意味を理解する
- 助動詞「けり」が持つ意味とは?
- 「き」と「けり」は何に接続するのか
- 助動詞「き」の具体的な接続ルール
- 助動詞「けり」の具体的な接続ルール
古文の助動詞「き」「けり」とは?

古文を読む上で、助動詞「き」と「けり」は非常によく登場する重要な要素です。
どちらも過去を表す助動詞ですが、そのニュアンスには明確な違いがあります。
簡単に言えば、「き」は主に話し手自身が直接体験した過去の出来事を表します。
一方で「けり」は、人から聞いたり書物で読んだりして知った過去(伝聞過去)や、今まさに気づいたこと(詠嘆)を表すことが多いです。
これらの助動詞を正確に理解することは、古文の文章が誰の視点で、どのような状況を描写しているのかを掴むために不可欠です。
古文の世界をより深く味わうために、まずはこの二つの助動詞の基本的な役割を把握しましょう。
助動詞「き」が持つ意味を理解する

助動詞「き」は、基本的に「~た」と訳され、話し手が過去に直接体験した出来事を表します。
これを「直接過去」と呼びます。自分が実際に見たり聞いたり、行動したりしたことについて語る際に用いられる助動詞です。
例えば、「花を見き」という文があった場合、これは「(私が)花を見た」という意味になり、話し手自身が花を直接見た経験を語っていることがわかります。
物語の語り手が自身の経験を回想する場面などで頻繁に使われます。この「直接体験」という点が、「き」を理解する上での最も重要なポイントになります。
ただし、注意点として、会話文の中や、明らかに他の人の体験について述べている文脈では、話し手以外の直接体験を表す場合もあります。
文脈をよく読んで判断することが大切です。
助動詞「けり」が持つ意味とは?

助動詞「けり」も「~た」と訳されることが多いですが、「き」とは異なり、主に二つの意味を持っています。一つは「伝聞過去」、もう一つは「詠嘆」です。
「伝聞過去」は、人から伝え聞いた話や、書物などで知った過去の出来事を表します。
「~たそうだ」「~ということだ」といったニュアンスが含まれます。
例えば、「昔、男ありけり」という文は、「昔、ある男がいたそうだ」という意味合いになり、語り手が直接経験したことではなく、伝聞として知っている情報を述べています。
歴史物語や説話などで多く見られます。
もう一つの「詠嘆」は、今その場で何かにはっと気づいたり、しみじみと感動したりする気持ちを表します。
「~だなあ」「~たことよ」といった訳し方が適しています。
和歌の中で使われる「けり」はこの詠嘆の意味を持つことが多いです。
例えば、「山吹の花、咲きにけり」は、「(見ると)山吹の花が咲いていたのだなあ」という、今気づいた驚きや感動を表します。
このように、「けり」は直接体験ではない過去や、現在の気づき・感動を表す助動詞として理解しておくと良いでしょう。
「き」と「けり」は何に接続するのか

助動詞は、単独で使われることはなく、必ず他の単語の後ろに付きます。
どのような種類の単語の後ろに付くのか、というのが「接続」のルールです。
「き」と「けり」がどのような言葉に接続するのかを知ることは、文法的な識別の助けになります。
結論から言うと、「き」と「けり」は、どちらも主に用言(動詞、形容詞、形容動詞)や助動詞の「連用形」に接続します。
連用形とは、活用する語が他の用言や助動詞などに連なる(つながる)ときの形のことです。例えば、動詞「咲く」の連用形は「咲き」となります。
この接続ルールを覚えておくことで、文中で「き」や「けり」を見つけたときに、その直前の語が連用形になっているかを確認する、といった使い方ができます。
ただし、例外的な接続もあるため、基本的なルールとして押さえておくのが良いでしょう。
助動詞「き」の具体的な接続ルール

前述の通り、助動詞「き」は、原則として活用語の「連用形」に接続します。
これは、動詞、形容詞、形容動詞、そして一部の助動詞の連用形の後ろに付くということです。
- 動詞の例: 「書き」+ き → 書きき (書いた)
- 形容詞の例: 「美し」+ き → 美しかりき (美しかった) ※カリ活用
- 形容動詞の例: 「静かなり」+ き → 静かなりき (静かだった) ※ナリ活用
ここで注意したいのは、形容詞や形容動詞に接続する場合です。
形容詞のク活用・シク活用、形容動詞のナリ活用・タリ活用それぞれの連用形に接続します。
特に形容詞のカリ活用(美しかり)や形容動詞のナリ活用(静かなり)の連用形に付く形は少し特殊に見えるかもしれませんが、ルールは一貫して「連用形接続」です。
非常にまれですが、カ行変格活用動詞「来(く)」の未然形「こ」や、サ行変格活用動詞「す」「おはす」の未然形「せ」に接続する特殊な用法(「こし」「せし」)もありますが、基本は連用形接続と覚えておけば問題ありません。
助動詞「けり」の具体的な接続ルール

助動詞「けり」も、「き」と同様に、原則として活用語の「連用形」に接続します。
- 動詞の例: 「知る」+ けり → 知りけり (知ったそうだ、知ったことだなあ)
- 形容詞の例: 「高し」+ けり → 高かりけり (高かったそうだ、高かったことだなあ) ※カリ活用
- 形容動詞の例: 「賑やかなり」+ けり → 賑やかなりけり (賑やかだったそうだ、賑やかだったことだなあ) ※ナリ活用
基本的な接続ルールは「き」と同じです。こちらも形容詞や形容動詞の連用形(カリ活用、ナリ活用、タリ活用を含む)に接続します。
ただし、「けり」には一つ注意すべき点があります。
それは、ラ行変格活用(ラ変)の動詞や助動詞に接続する場合です。ラ変型の活用語(例:「あり」「をり」「はべり」「いまそかり」など)に付く際は、連用形ではなく終止形(言い切りの形)に接続するように見えることがあります(例:「ありけり」)。
これは歴史的な音変化(撥音便の無表記など)によるもので、文法的な解釈としては連用形に接続しているとされることが多いですが、見た目上は終止形に接続しているように見える、と覚えておくと読解の際に役立ちます。
助動詞「き」「けり」の識別と活用をマスター

ここまでは、「き」と「けり」の基本的な意味と接続について見てきました。ここからは、さらに理解を深めるために、両者の決定的な違いである「識別」のポイントと、それぞれの「活用」について詳しく解説します。最後に練習問題で知識を定着させましょう。
- 「き」と「けり」を見分ける識別のコツ
- 助動詞「き」の活用表を覚えよう
- 助動詞「けり」の活用表もチェック
- 練習問題で理解度を確認【最後に正解数を表示】
- まとめ:これで簡単!「き」と「けり」の識別
「き」と「けり」を見分ける識別のコツ

助動詞「き」と「けり」を最も簡単に識別するコツは、その文脈が誰の経験や視点に基づいているかを見極めることです。これが最も重要なポイントとなります。
「き」が使われている場合、それは基本的に語り手(または文中の主語)が直接体験した過去の出来事です。
「私が見た」「私が聞いた」「私が行った」というような、自身の経験に基づいた内容であることが多いです。
回想シーンや、自身の行動を描写する文脈で「き」を見たら、「これは直接体験だな」と判断できます。
一方、「けり」が使われている場合は、二つの可能性を考えます。
一つは、人から聞いたり、書物で読んだりした過去の話(伝聞過去)です。「~たそうだ」「~ということだ」のように、語り手が直接関与していない過去を表します。
物語の導入部(「昔、~ありけり」など)や、歴史的な事実を述べる場面でよく見られます。もう一つは、今まさに気づいたことや、しみじみとした感動(詠嘆)です。
「~だなあ」「~たことよ」と訳せる場合、特に和歌などで見られる場合は、詠嘆の可能性が高いでしょう。
このように、「直接体験か、そうでないか(伝聞または詠嘆か)」という視点で文脈を読むことが、識別の最大の鍵となります。
もちろん、接続や活用形もヒントにはなりますが、意味の違いから判断するのが最も確実です。
助動詞「き」の活用表を覚えよう
助動詞「き」は、少し特殊な活用をします。特に未然形と連体形、已然形に注意が必要です。以下に活用表を示します。
| 活用形 | 活用語 | 接続 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未然形 | せ | 連用形 | 「せば〜まし」で使われる |
| 連用形 | (なし) | – | 活用形が存在しない |
| 終止形 | き | 連用形 | |
| 連体形 | し | 連用形 | |
| 已然形 | しか | 連用形 | |
| 命令形 | (なし) | – | 活用形が存在しない |
この表のポイントは以下の通りです。
- 未然形が「せ」であること:「せば~まし」(もし~だったら~だろうに)という反実仮想の構文でよく使われます。「せ」単独で使われることはほとんどありません。
- 連用形が存在しないこと:これは非常に珍しい特徴です。助動詞「き」が他の用言に連なることは基本的にありません。
- 連体形が「し」、已然形が「しか」であること:この形は重要です。例えば、「見し人」(見た人)のように体言に続く場合は連体形「し」が、「~しかば」(~たので)のように接続助詞「ば」に続く場合は已然形「しか」が使われます。
この特殊な活用を覚えることが、「き」をマスターする上で重要になります。「せ・まる・き・し・しか・まる」(まるは活用形なしの意味)のように、音で覚えるのも一つの方法です。
助動詞「けり」の活用表もチェック
助動詞「けり」の活用は、ラ行変格活用動詞(あり、をり、はべり、いまそかり)と同じ活用パターンを持ちます。比較的覚えやすい活用形と言えるでしょう。
| 活用形 | 活用語 | 接続 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未然形 | けら | 連用形 | |
| 連用形 | (なし) | – | 活用形が存在しない |
| 終止形 | けり | 連用形 | ラ変型への接続は注意 |
| 連体形 | ける | 連用形 | |
| 已然形 | けれ | 連用形 | |
| 命令形 | (なし) | – | 活用形が存在しない |
ポイントは以下の通りです。
- ラ行変格活用と同じ:「ら・り・り・る・れ・れ」のリズムで覚えている人も多いと思いますが、「けら・(まる)・けり・ける・けれ・(まる)」と、ラ変と同じ音の流れで活用します。(連用形・命令形はありません)
- 連用形が存在しない:「き」と同様に、「けり」にも連用形はありません。
- 各活用形の使われ方:
- 未然形「けら」:「けらば」「けらむ」のように使われます。
- 終止形「けり」:文末で言い切る形です。
- 連体形「ける」:「ける人」「ける時」のように体言に続きます。
- 已然形「けれ」:「けれども」「ければ」のように接続助詞に続きます。
「き」と比べると、「けり」の活用はパターン化されており、ラ変活用を覚えていれば容易に類推できます。
練習問題で理解度を確認【最後に正解数を表示】
ここまでの内容を理解できたか、簡単な練習問題で確認してみましょう。以下の問題を考えてみてください。問題の一番最後には正解数も表示されるのでテストと同じように取り組んでみてください。選択肢は一度しか選べませんからきちんと選択するようにしてください。
助動詞「き」「けり」問題演習
第1問
「世の中にたえて桜のなかりせば春の心はのどけからまし」の「せ」の文法的説明として最も適切なものを選べ。
第2問
助動詞「けり」の活用形として存在しないものを選べ。
第3問
「京に下りしとき」の「し」の文法的説明として最も適切なものを選べ。
第4問
「いまは昔、竹取の翁といふもの有りけり」の「けり」の意味として最も適切なものを選べ。
第5問
「選ばれし者」の「し」と同じ助動詞とその活用形を選べ。
第6問
和歌の末尾に用いられる助動詞「けり」に最も多い意味を選べ。
第7問
助動詞「き」の原則的な接続として正しいものを選べ。
第8問
「なりけり」の「けり」に多い意味を選べ。
第9問
助動詞「き」の活用形(未然形・連用形・終止形・連体形・已然形・命令形)として正しいものを全て含むものを選べ。
第10問
カ変動詞「来(く)」に助動詞「き」の連体形「し」が接続する場合、「来(く)」はどのような活用形になるか。
第11問
サ変動詞「す」に助動詞「き」の連体形「し」が接続した形を選べ。
第12問
「ゆかしかりしかど」の「しか」の文法的説明として最も適切なものを選べ。
第13問
主として伝聞や間接的な過去を表す助動詞を選べ。
第14問
話者の直接体験した過去を表す助動詞を選べ。
第15問
物語の冒頭などに「けり」がよく用いられる理由として適切なものを選べ。
第16問
助動詞「けり」が接続する語の活用形を選べ。
第17問
助動詞「き」の活用形「し」が接続する語の品詞として最も適切なものを選べ。
第18問
「かの中の品にとりいでて言ひし、このなみならむかし」の「し」の文法的説明として最も適切なものを選べ。
第19問
「この御酒を醸み祁礼かも」の「醸み祁礼」の「祁礼」と同じ活用形の助動詞を選べ。
第20問
「いづれの御時にか、女御更衣あまたさぶらひ給ひけるなかに」の「ける」の文法的説明として最も適切なものを選べ。
まとめ:これで簡単!「き」と「けり」の識別
最後に、助動詞「き」と「けり」の識別ポイントを改めて整理します。この二つの助動詞は、古文読解において非常に重要であり、その違いを理解することが文脈把握の鍵となります。
最も重要な識別ポイントは、「誰の視点か、どのような種類の過去か」という点です。
- 助動詞「き」:
- 意味:直接過去(~た)
- ポイント:話し手(筆者)自身が直接体験した過去。回想など。
- 活用:特殊(せ・○・き・し・しか・○)
- 接続:主に連用形
- 助動詞「けり」:
- 意味:伝聞過去(~たそうだ)または 詠嘆(~だなあ、~たことよ)
- ポイント:人から聞いたり書物で知ったりした過去。または、今気づいたこと、感動。
- 活用:ラ変型(けら・○・けり・ける・けれ・○)
- 接続:主に連用形(ラ変型には注意)
古文を読む際には、文脈から「これは自分の体験談かな?」「これは昔話かな?」「これは感動を表しているのかな?」と考えながら、「き」と「けり」のどちらが使われているか、またはどちらが適切か判断する練習を繰り返しましょう。
接続や活用の知識も補助的に役立ちますが、まずは意味の違いをしっかり捉えることが、最も効果的な学習方法です。
この記事が、皆さんの古文学習の一助となれば幸いです。
助動詞「き」「けり」の要点まとめ

記事の内容を以下にまとめました。参考になったらうれしいです。
- 助動詞「き」「けり」は共に過去を表す助動詞である
- 「き」は主に話し手の直接体験した過去(直接過去)を示す
- 「けり」は伝聞による過去(伝聞過去)や現在の気づき・感動(詠嘆)を表す
- 両助動詞とも原則として活用語の連用形に接続する
- 「き」の活用は「せ・○・き・し・しか・○」であり特殊な変化をする
- 「けり」の活用は「けら・○・けり・ける・けれ・○」でラ行変格活用型である
- 両助動詞に連用形と命令形は存在しない
- 「き」の未然形「せ」は主に反実仮想「(未然形)+せば〜まし」で使われる
- 「き」の連体形「し」は体言に、已然形「しか」は接続助詞「ば」に付く
- 「けり」はラ変型活用語に接続する場合、音便化により終止形接続に見えることがある
- 「き」と「けり」の識別は、文脈から意味を判断するのが最も重要である
- 直接体験談なら「き」、伝聞や詠嘆なら「けり」と見分ける
- 物語の冒頭などで用いられる「けり」は伝聞過去が多い
- 和歌で用いられる「けり」は詠嘆の意味合いが強い
- 接続や活用の知識は、意味判断を補助する手がかりとなる
古文の勉強、お疲れ様でした!
「よし、やるぞ!」と思っても、「でも、文法をゼロから体系的にやり直すのって、独学だと不安だなぁ…」と感じていませんか?
もし、あなたが「元・古文が苦手」だった先生から、センスに頼らない「論理的な解き方」を学びたいなら…
今、多くの受験生から「神授業」と呼ばれている「スタディサプリ 古文」を、私が徹底的に分析した記事がきっと役立つはずです。
なぜ岡本先生の授業がそこまで支持されるのか、ゼロから始める具体的な受講順番まで詳しく解説しています。
古文を「苦手」から「得意」に変える、その具体的な方法に興味がある方は、ぜひ覗いてみてくださいね。
→ 関連記事:スタディサプリ古文が神授業と言われる理由|ゼロから始める最適ルートも解説
この記事を読んで、古文の理解がまた一つ深まりましたね。
でも、古文は「単語」「文法」「読解」「常識」など、全ての知識が有機的につながって初めて高得点が取れる科目です。
「次はどこを勉強すればいいの?」
「苦手なあの分野、どうやって対策しよう?」
そんな迷子にならないよう、ミチプラス内の古文記事を「勉強する順番」に整理した「完全攻略マップ」を作成しました。
辞書代わりにブックマークして、最短ルートで志望校合格を目指しましょう!