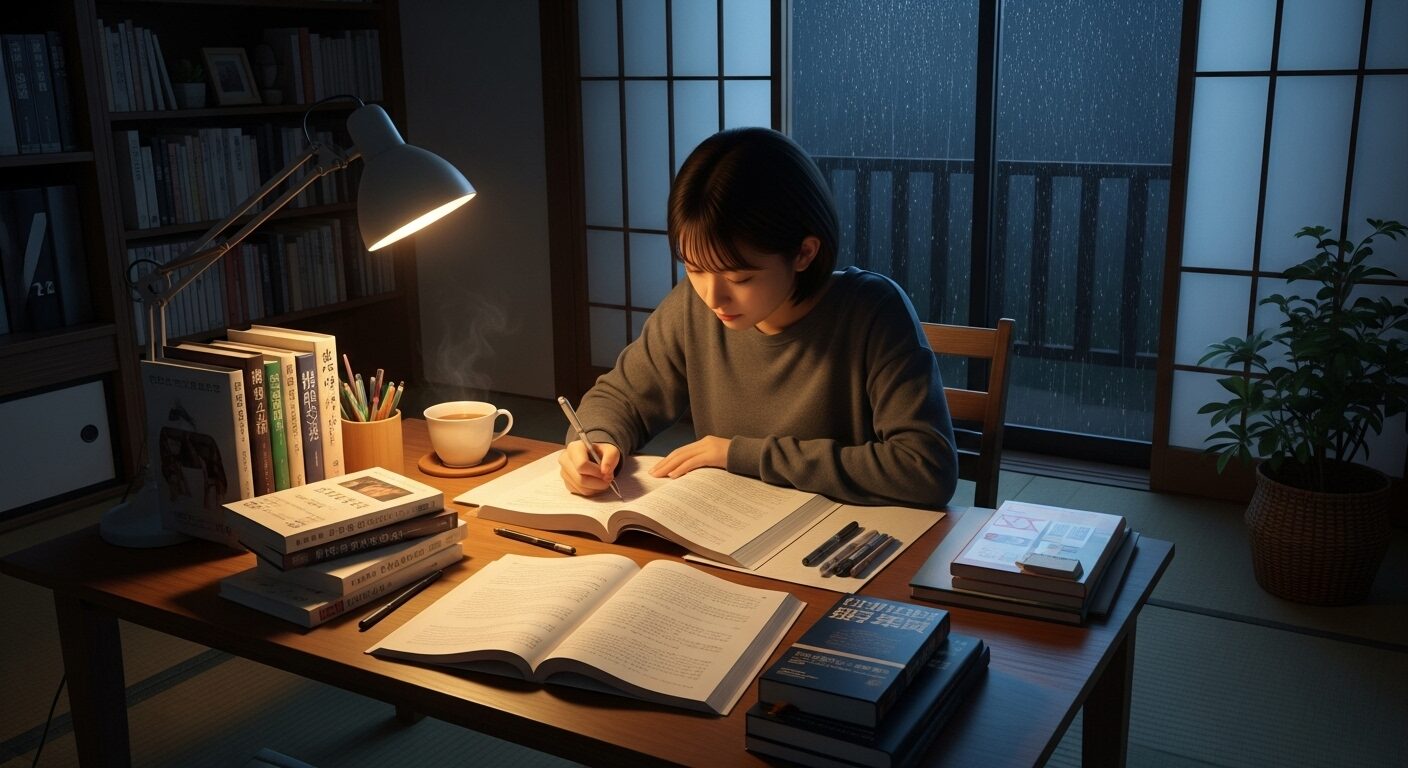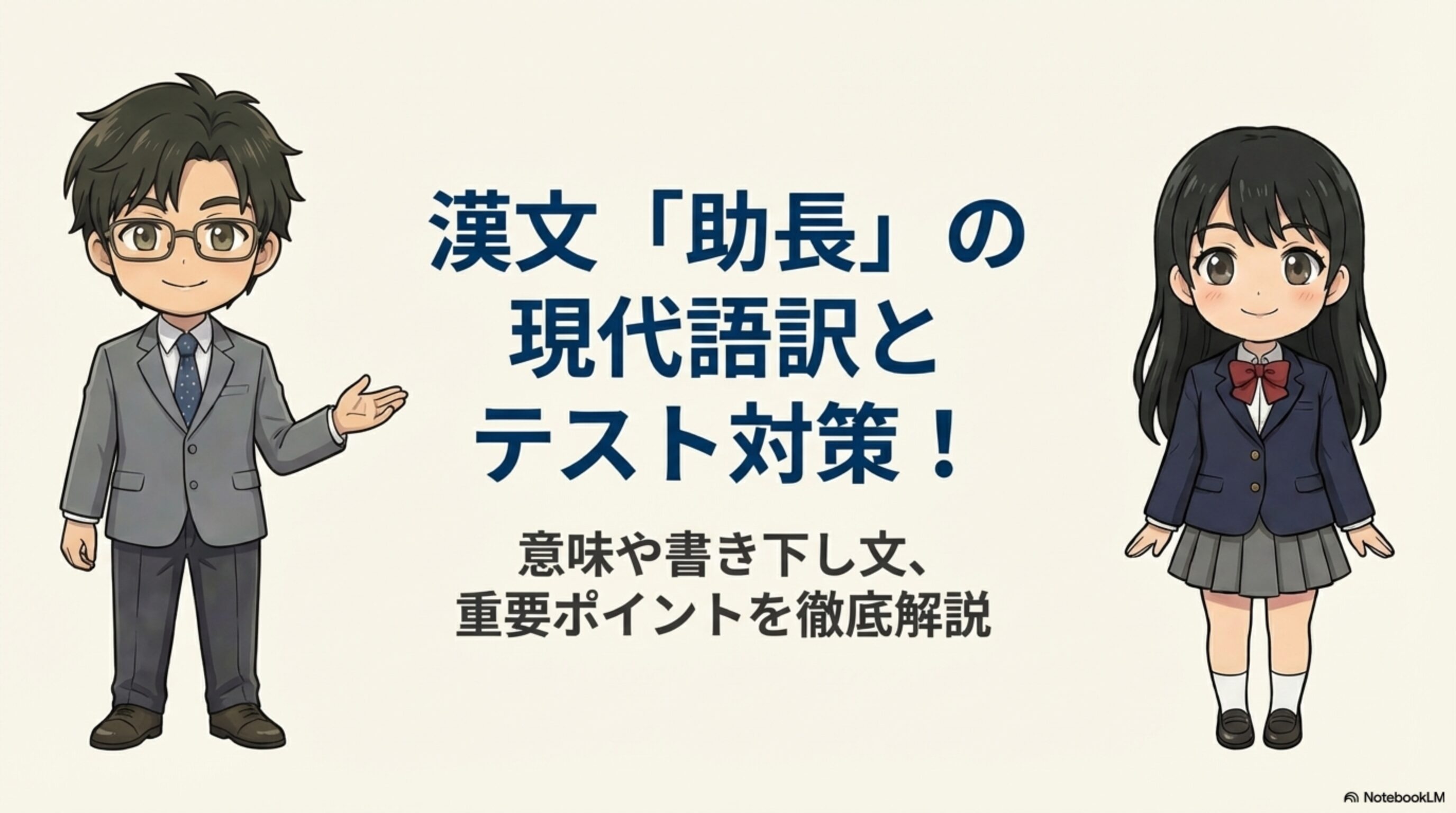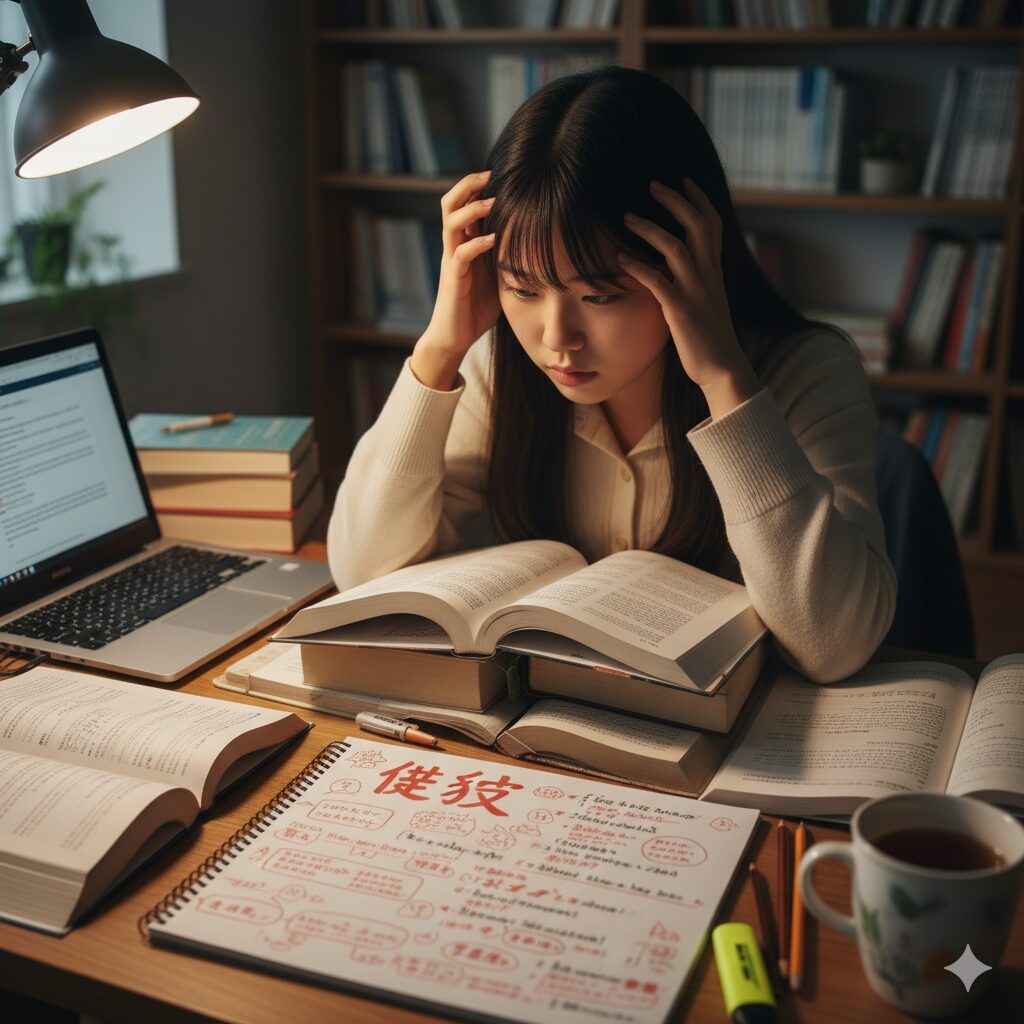漢文「矛盾」を徹底解説!テスト対策から現代語訳まで

漢文の「矛盾」は、多くの方が中学校や高校の国語の授業で初めて触れる、非常に有名な故事成語です。しかし、「昔の話で何となく難しそう…」「テストでどこが問われるのか分からない」といった不安を感じる方も少なくないでしょう。ご安心ください。漢文は、正しい順序でポイントを押さえれば、誰でも必ず理解できるようになります。
この記事では、「矛盾」の物語のあらすじや登場する語句の意味はもちろん、定期テストで高得点を狙うための具体的な対策や問題の解き方まで、段階的に解説を進めていきます。原文である白文の正しい読み方から、書き下し文、そして現代の言葉で書かれた分かりやすい現代語訳まで、学習に必要な情報を網羅しました。この記事全体が、皆さんの学習に役立つ万能なプリントのような存在になることを目指し、情報を丁寧にまとめていきます。
漢文:矛盾の全体像をわかりやすく解説
故事成語「矛盾」の由来とは

「矛盾」は、現代の日本語でも「Aさんの発言は矛盾している」といった形で、「話のつじつまが合わないこと」や「二つの物事が論理的に両立しないこと」を指す言葉として、ごく自然に使われています。このように古くからの物語が元になって定着した言葉を故事成語と呼びます。
この言葉の直接の由来となったのが、今回学習する漢文の物語です。このエピソードが収められているのは、今から2200年以上前の中国、戦国時代末期に生きた思想家・韓非(かんぴ)が著した『韓非子(かんぴし)』という書物です。『韓非子』は、君主が国を効率的に治めるための具体的な術を説いた、実践的な思想書として知られています。(出典:コトバンク「韓非子」)
韓非は、厳格な法によって国を治めるべきだとする「法治主義」を唱えた法家の代表的な人物です。彼の思想は、当時主流だった儒家の「徳治主義(君主の徳によって民を導くべきだという考え)」とは真っ向から対立するものでした。韓非は、儒家の教えがいかに非現実的で、論理的でないかを明らかにするため、たとえ話としてこの「矛盾」のエピソードを用いたと言われています。
【豆知識】韓非はなぜ「矛盾」の話を書いた?
韓非が生きた時代、思想の中心には孔子が説いた「儒家」の教えがありました。儒家は伝説上の名君である「堯(ぎょう)」と「舜(しゅん)」を絶対的な理想とし、彼らが素晴らしい「徳」によって国を完璧に、そして平和に治めたと主張していました。
これに対し韓非は、「もし堯の政治が本当に完璧だったなら、後を継いだ舜がさらに世の中を改める必要などなかったはずだ」と鋭く指摘しました。つまり、「万能で完璧な存在」と「それをさらに改良する存在」は論理的に両立しないという、儒家の主張の根幹にある論理的な破綻を突いたのです。
この小難しくなりがちな批判を、誰にでも分かりやすく伝えるための具体例として、「何でも通す矛」と「何でも防ぐ盾」の話が使われたのです。
このように、単なる商人の面白い失敗談ではなく、背後には思想家たちの厳しい論戦という知的背景が存在します。この背景を知ることで、物語が持つ本当の面白さや深みをより一層感じることができます。
まずは矛盾のあらすじを簡単に理解

物語の筋書き自体は非常にシンプルで、一度聞けば誰もが記憶に残るほど明快です。学習の第一歩として、まずは全体の流れであるあらすじを細部まで情景を思い浮かべながら把握しましょう。
昔、中国の楚の国に、活気あふれる市場で武器を売る商人がいました。彼は自分の商品を一人でも多くの人に買ってもらおうと、自信に満ちた大きな声で宣伝を始めます。市場にいる人々の注目が、彼の手元に集まりました。
まず、彼は左手に持った盾を高く掲げ、太陽の光に反射させながら言いました。
「さあさあ、皆さんご覧ください!この盾は世にも稀な金属でできており、その頑丈さと言ったら天下一品!どんな鋭い剣や矢が来ようとも、決して突き通すことはできません!」
次に、右手に持っていた矛を鋭く突き出し、その切っ先を皆に見せつけながら、さらに声を張り上げます。
「そしてこちらの矛!この矛の鋭さときたら、どんなに硬い鎧や盾であろうとも、まるで紙を裂くかのように突き通してしまいます!この矛で貫けないものは、この世に存在いたしません!」
彼の巧みな口上に、周りの人々は「おおっ」と感心した声をあげました。しかし、その中の一人の客が冷静に前に進み出て、素朴な、しかし核心を突く疑問を投げかけました。
「もしもし、ご主人。では、あなたが言う『何でも突き通せるその矛』で、あなたが言う『絶対に突き通せないその盾』を突いたら、いったいどうなるのですか?」
市場は水を打ったように静まり返りました。この問いに、あれほど自信満々に、そして雄弁に語っていた商人は顔を真っ赤にし、一言も答えることができなくなってしまったのです。
あらすじの要点
結論として、この物語は「両立しない二つの事柄が同時に主張することのおかしさ」を、非常に分かりやすく示しています。「最強の矛(=絶対に貫ける攻撃)」と「最強の盾(=絶対に貫けない防御)」は、どちらか一方が真実ならば、もう一方は必ず嘘になってしまいます。このあまりにも有名な話から、「矛盾」という言葉が生まれたのです。
登場する重要な語句の意味を確認
漢文を正確に読み解くためには、文中に出てくる語句の意味を正しく理解することが学習の土台となります。特に「矛盾」では、現代ではあまり使われない言葉や、文脈によって意味が変わる重要な漢字が登場します。ここで一つひとつ丁寧に確認し、知識を盤石なものにしておきましょう。
| 語句 | 読み方 | 意味と補足解説 |
|---|---|---|
| 楚人 | そひと | 楚の国の人。「楚」は中国の春秋戦国時代に長江流域を支配した大国の一つです。 |
| 鬻ぐ | ひさぐ | 「売る」という意味の動詞。現代語では使われないため、読みと意味の両方を覚える必要があります。 |
| 子 | し | 「あなた」という意味の二人称代名詞。現代語の「先生」のように、相手への敬意を示す言葉です。 |
| 陥す | とおす | 「突き通す」「貫く」という意味。現代語の「陥落」などの言葉にも通じる漢字です。 |
| 利なり | りなり | 「鋭い」「鋭利である」という意味。「利」には「利益」など複数の意味がありますが、ここでは刃物の鋭さを指します。 |
| 莫し | なし | 「~ない」という意味の否定を表す言葉。「無」よりも強い、絶対的な否定のニュアンスを持ちます。 |
| 何如 | いかん | 「どうなるか」「どうであるか」と問いかける疑問の言葉。現代語の「いかがですか」の語源です。 |
| 弗能 | あたはざる | 「~することができない」という不可能を表す言葉。「不」よりもさらに強い否定の意思が込められています。 |
| 与 | と | 「A与B」で「AとB」という意味になる助詞。「与える」という動詞ではない点に注意が必要です。 |
これらの語句は、テストの設問で意味や読みを直接問われることも多い重要単語です。特に「鬻ぐ」「子」「何如」「与」の用法は頻出なので、文脈の中でどのように使われているかを意識しながら、確実に覚えておくことを強くおすすめします。
漢文特有の読み方をマスターしよう

「矛盾」の学習では、漢字の読み方も避けては通れない重要なポイントです。私たちが普段日本語として使っている音読みや訓読みとは異なる、漢文を訓読するためだけの特別な読み方がいくつか登場します。これらは初学者にとっては少し戸惑う部分かもしれませんが、テストで最も狙われやすい部分なので、ここでしっかりマスターして得意分野に変えてしまいましょう。
「鬻(ひさぐ)」
前述の通り、「売る」という意味を持つ動詞です。漢字の構成から意味を推測するのは非常に難しいため、これは一つの知識として暗記する必要があります。「矛盾」の冒頭に出てくる重要な単語です。
「莫也(なきなり)」
「能く陥すもの莫きなり(よく とほすもの なきなり)」という一節で使われます。「~するものは(何一つ)ない」という完全な否定を表す、非常に強い表現です。「莫」という字自体に「無し」という意味が含まれており、漢文の否定形の中でも代表的なものの一つです。
「弗能応也(応ふる能はざるなり)」
「弗能」を「あたはざる」と読むのが最大のポイントです。「能」は「~できる」という可能の意味を持つ漢字ですが、その前に付いている「弗」が強い打ち消しの働きをします。これにより「~することはできない」という不可能の意味が生まれます。物語の結末を決定づける、非常に重要な一節の読み方です。
漢文の特殊な読み方は、最初は呪文のように感じるかもしれませんね。しかし、これらは限られたパターンしかなく、一度覚えてしまえば他の漢文、例えば「五十歩百歩」や「漁夫の利」などを読むときにも必ず応用が利きます。特に否定や不可能を表す言葉は漢文のストーリーの根幹に関わる部分なので、この機会にしっかり声に出して読んで、音で覚えてしまうのが効果的ですよ!
矛盾の原文(白文)を見てみよう

それでは、いよいよ物語のオリジナルの形である原文(白文)を見ていきましょう。白文とは、返り点(レ点、一二三点など)や送り仮名といった、日本語として読むための補助記号が一切付いていない、漢字だけの文章を指します。古代の中国では、このような形で文章が記録されていました。
『矛盾』原文(白文)
楚人有鬻盾与矛者。
誉之曰、「吾盾之堅、莫能陥也。」
又誉其矛曰、「吾矛之利、於物無不陥也。」
或曰、「以子之矛、陥子之楯、何如。」
其人弗能応也。
たとえ漢字が得意な人であっても、この白文をいきなり日本語としてスラスラと正しく読むのは非常に難しいはずです。なぜなら、これは外国語の文章だからです。日本語と古代中国語では、文法、つまり主語・動詞・目的語などの言葉の並び順(語順)が根本的に異なります。この語順の違いを乗り越え、私たち日本人が意味を理解できるようにしたものが、次に紹介する「書き下し文」なのです。
書き下し文で訓読に慣れる
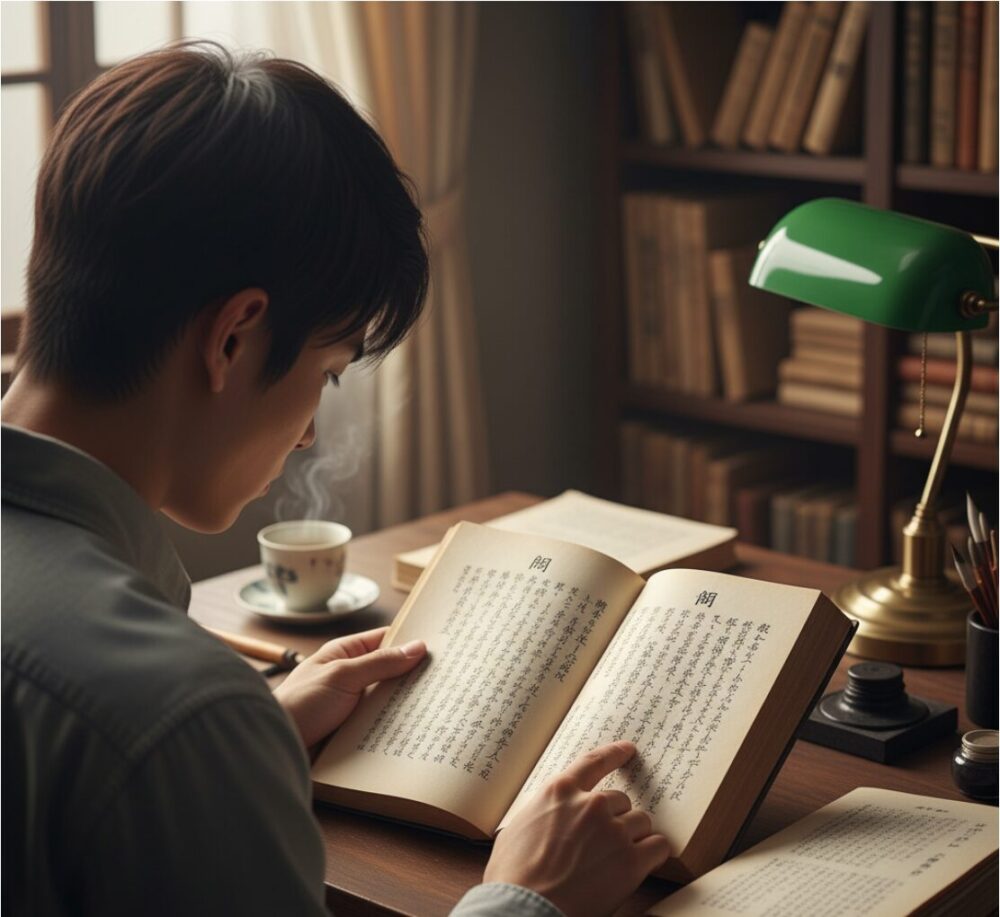
書き下し文は、白文に付けられた返り点や送り仮名といった「訓点(くんてん)」に従って、漢字を読む順番を日本語の文法に合うように並べ替え、さらに「てにをは」などの助詞や助動詞などを補って書いたものです。漢文の授業で学習する文章形式としては、最も基本となるものと言えるでしょう。
下の書き下し文と、先ほどの原文(白文)を丁寧に見比べながら、語順がどのように変化しているかを確認してみてください。
『矛盾』書き下し文
楚人に盾と矛とを鬻ぐ者有り。
之を誉めて曰はく、「吾が盾の堅きこと、能く陥すもの莫きなり。」と。
又其の矛を誉めて曰はく、「吾が矛の利なること、物に於いて陥さざる無きなり。」と。
或るひと曰はく、「子の矛を以つて、子の盾を陥さば何如。」と。
其の人応ふる能はざるなり。
書き下し文は、現代の文章とは異なり、古文のような言葉遣い(文語体)で書かれるのが特徴です。例えば、文末が「~なり」や「~けり」といった助動詞で結ばれる点や、歴史的仮名遣い(例:「言はく」→いはく)が使われている点に注意が必要です。定期テストでは、白文に訓点を施し、それを元に書き下し文に直すという一連の作業が頻繁に出題されます。返り点の基本的なルール(レ点、一二三点)をしっかりと復習しながら、何度も声に出して音読し、訓読のリズムに慣れることが上達への一番の近道です。
わかりやすい現代語訳で内容を把握

最後に、物語の意味を完全に、そして深く理解するために現代語訳を確認します。現代語訳は、書き下し文を、私たちが日常的に使っている言葉(口語体)に直したものです。これまでの学習内容の総まとめとして、登場人物の心情などを想像しながら読んでみてください。
『矛盾』現代語訳
楚の国の人で、盾と矛を市場で売っている者がいた。
(その商人は、自分の持っている)盾を大いに自慢して言うことには、「私のこの盾の頑丈さと言ったら、これを突き通すことができるものは世の中に何一つありません。」と言った。
また、今度は自分の持っている矛を褒め称えて言うことには、「私のこの矛の鋭さと言ったら、どんな物であろうと突き通せないものは絶対にありません。」と言った。
(この一連の口上を聞いていた)ある人が(商人に)尋ねて言うことには、「それでは、あなたの言う『何でも突き通すことができる矛』で、あなたの言う『絶対に突き通すことができない盾』を突いたら、結果は一体どうなるのですか。」と。
その(盾と矛を売っていた)商人は、(この問いに)答えることができなかった。
現代語訳を読むと、自信満々に商品を宣伝している商人の姿と、彼の言葉の論理的な欠陥に気づき、冷静に指摘する客の姿が、生き生きとした情景として目に浮かぶようですね。この鮮やかな対比こそが、この物語が2000年以上もの時を超えて語り継がれてきた面白さの源泉と言えるでしょう。
漢文:矛盾の読解とテスト対策のポイント
つまずきやすい部分を重点的に解説
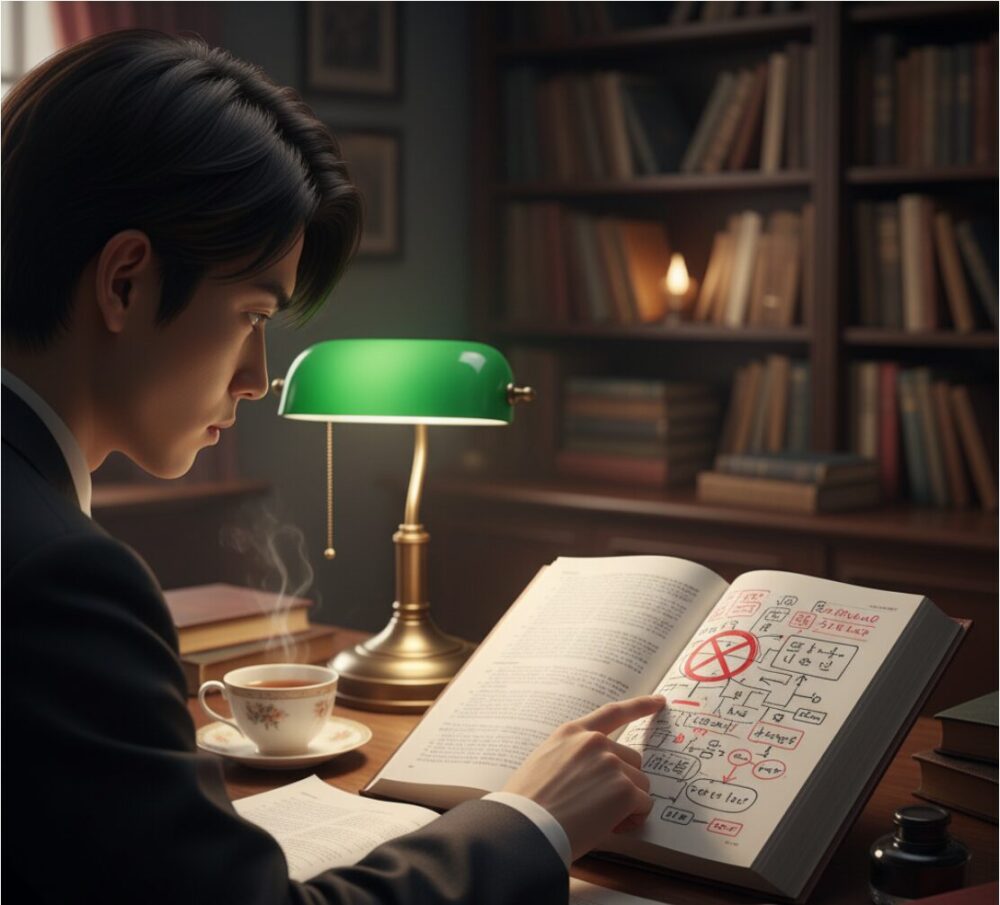
「矛盾」の物語を深く、そして正確に理解する上で、避けては通れない最重要項目が否定、二重否定、不可能といった文法表現です。ここが漢文の学習で多くの人がつまずきやすいポイントであり、同時に定期テストでも配点の高い問題として頻繁に問われる部分です。一つひとつ丁寧に解説しますので、ここで完全にマスターしてしまいましょう。
① 「莫能陥也」(能く陥すもの莫きなり)- 単純な否定
これは「突き通すことができるものは(何一つ)ない」という意味です。「莫」という漢字一字が「~ない」という強い否定の意味を表しており、比較的理解しやすい単純な否定文です。ここでは「どんな攻撃も通用しない絶対的な防御」を表現しています。また「能」(~できる)が「陥」(突き通す)にかかっているところもポイントです。「能」は助動詞的働きをします。
② 「於物無不陥也」(物に於いて陥さざる無きなり)- 最重要の二重否定
ここが「矛盾」における最大の難関であり、最重要ポイントとなる二重否定の構文です。一見すると複雑ですが、パーツに分解して考えれば必ず理解できます。
二重否定の分解ステップ
- 不陥:「陥さず(とおさず)」と読み、「突き通さない」という1回目の否定です。
- 無不陥:「陥さざる無き(とおさざるなき)」と読み、「突き通さないことはない」という意味になります。
「~ないことはない」ということは、数学における「マイナス × マイナス = プラス」の関係と同じで、裏を返せば「必ず~する」という非常に強い肯定の意味に変わります。つまり、商人は「私の矛は、どんなものでも必ず突き通すことができる」という絶対的な攻撃力を主張しているのです。
二重否定の罠に注意!
否定の言葉(不、無、莫など)が二つ重なると、頭が混乱してしまいがちです。しかし、「否定 × 否定 = 強い肯定」というシンプルな公式さえ覚えておけば大丈夫です。この二重否定は、漢文の世界における頻出の重要文法です。正確に訳せるだけでなく、なぜそうなるのかを説明できるようになっておきましょう。
③ 「弗能応也」(応ふる能はざるなり)- 不可能
これは「答えることができなかった」という不可能を表す表現です。「能」は「~できる」という可能の意味を持ちますが、それを「弗」という強い否定の働きを持つ語で打ち消しています。単なる「不」よりも強い打ち消しであり、「まったく~できなかった」というニュアンスになります。これにより、商人が完全に返答に窮したことを示しています。
これらの否定表現、とりわけ二重否定を正確に訳し、説明できるかどうかが、「矛盾」の読解力を測る最も重要なバロメーターとなります。
否定形についてはこちらの記事にまとめています。ぜひ読んでみてください。

定期テスト対策:問題で実力を試す

ここまでの内容がどれだけ身についたか、定期テスト対策を強く意識した実践的な問題で実力を試してみましょう。実際のテストでは、以下のような様々な角度から知識を問う問題が出題されることが多いです。
問題形式1:漢字の読みと意味
問:本文中の「子」の読み方と、誰を指しているかを答えなさい。
答:読み「し」、指している人「矛と盾を売る商(楚)人」
問題形式2:書き下し文への変換
問:「其人弗能応也。」に訓点をつけ、書き下し文に直しなさい。
答:訓点「其人弗レ能レ応也。」、書き下し文「其の人応ふる能はざるなり。」
問題形式3:口語訳(現代語訳)
問:二重否定に注意して、「吾矛之利、於物無不陥也。」を現代語訳しなさい。
答:(例)私の矛の鋭さは、どんな物でも突き通さないものはない。
問題形式4:指示語の内容
問:「之を誉めて曰はく」の「之」が指すものを、本文中から一字で抜き出して答えなさい。
答:盾
問題形式5:内容の読解・説明
問:商人が答えられなくなったのはなぜか。「矛」と「盾」の語を用いて、30字以内で簡潔に説明しなさい。
答:(例)何でも通す矛と、何でも防ぐ盾という両立しない説明をしたから(29字)
どうでしたか?特に問題形式5のような記述問題は、物語の本質を自分の言葉で再構成する力が問われます。ただ丸暗記するだけでなく、「なぜそうなるのか」という理由まで含めて理解しておくことが、応用問題にも対応できる真の実力につながりますよ!
復習に役立つ学習プリントの紹介

「矛盾」の学習内容を一時的な記憶で終わらせず、長期的な知識として定着させるためには、効果的な復習が不可欠です。この記事では、学習プリントのように使える「要点チェックリスト」と「学習ステップ」を用意しました。テスト前に見直したり、自分だけのまとめノートを作成したりする際に、ぜひ活用してください。
この記事自体が最高の参考書となるよう、重要なポイントを多角的に整理して一覧表にまとめます。
「矛盾」要点チェックリスト
| チェック項目 | ポイント解説 |
|---|---|
| 出典と作者 | 『韓非子』(作者:戦国時代の思想家・韓非) |
| 故事成語の意味 | 二つの物事のつじつまが合わないこと。論理的に両立しないこと。 |
| 重要語句(読みと意味) | 鬻ぐ(ひさぐ:売る)、子(し:あなた)、何如(いかん:どうなるか) |
| 最重要文法①:二重否定 | 「無不〜」(〜ざる無きなり)の形で、「必ず〜する」という強い肯定を表す。 |
| 最重要文法②:不可能 | 「弗能〜」(〜能はざるなり)の形で、「〜することができない」という意味になる。 |
| 物語の核心(テーマ) | 絶対的な攻撃力(最強の矛)と絶対的な防御力(最強の盾)は、同じ世界に同時に存在することはできない。 |
おすすめ学習ステップ
「矛盾」を効率的にマスターするための学習手順を紹介します。
- 語句の暗記:まずは表にある重要語句の読みと意味を覚える。
- 音読:書き下し文を、詰まらずにスラスラと音読できるようになるまで何度も読む。
- 内容理解:音読しながら、現代語訳の情景を頭の中に思い浮かべる。
- 文法整理:二重否定などの文法が、文中のどこで使われ、どういう働きをしているかを確認する。
- 問題演習:練習問題に挑戦し、理解できていない部分を特定して復習する。
このステップで学習を進めれば、知識が整理され、記憶に定着しやすくなります。特に、声に出して読む「音読」は、漢文特有のリズムを身体で覚えるのに非常に効果的です。(参照:文部科学省 中学校学習指導要領 国語)
練習問題プリントのダウンロードはこちらから。本文を見ながら取り組んでみましょう。
漢文:矛盾を理解する鍵は否定表現
この記事では、故事成語「矛盾」について、その背景から具体的な読解のポイント、テスト対策までを網羅的に解説してきました。最後に、学習した内容の最も重要なエッセンスをリスト形式で振り返りましょう。
- 「矛盾」は『韓非子』が出典の故事成語
- 意味は話のつじつまが合わないこと
- 楚の国の商人が矛と盾を売る話が元になっている
- 盾を「いかなるものも通さない」と宣伝する
- 矛を「いかなるものも突き通す」と宣伝する
- 客から「その矛でその盾を突いたらどうなるか」と問われる
- 商人は答えに窮してしまう
- 白文は返り点のない漢字のみの原文
- 書き下し文は返り点に従い日本語の語順に直したもの
- 現代語訳は現代の言葉で意味を分かりやすくしたもの
- 「鬻ぐ(ひさぐ)」は「売る」と読む重要単語
- 「子(し)」は相手への敬称で「あなた」という意味
- 「莫(なし)」は強い否定を表す
- 「無不〜(〜ざる無きなり)」は「必ず〜する」を意味する二重否定
- 二重否定は漢文学習における最重要文法の一つ
- 「弗能〜(〜あたはざるなり)」は「〜できない」という不可能を表す
- 漢文「矛盾」を正しく理解する鍵はこれらの否定表現のマスターが不可欠