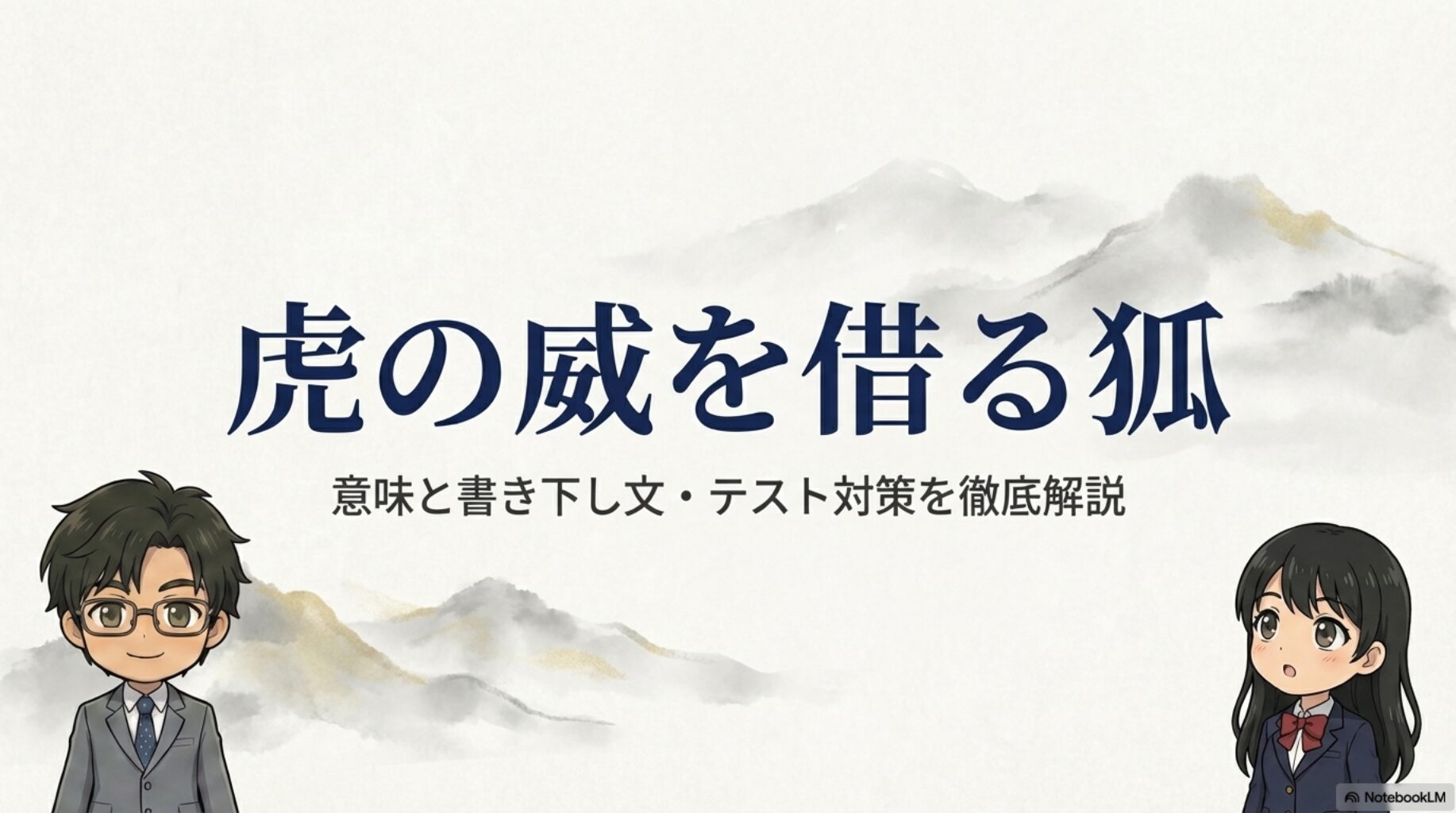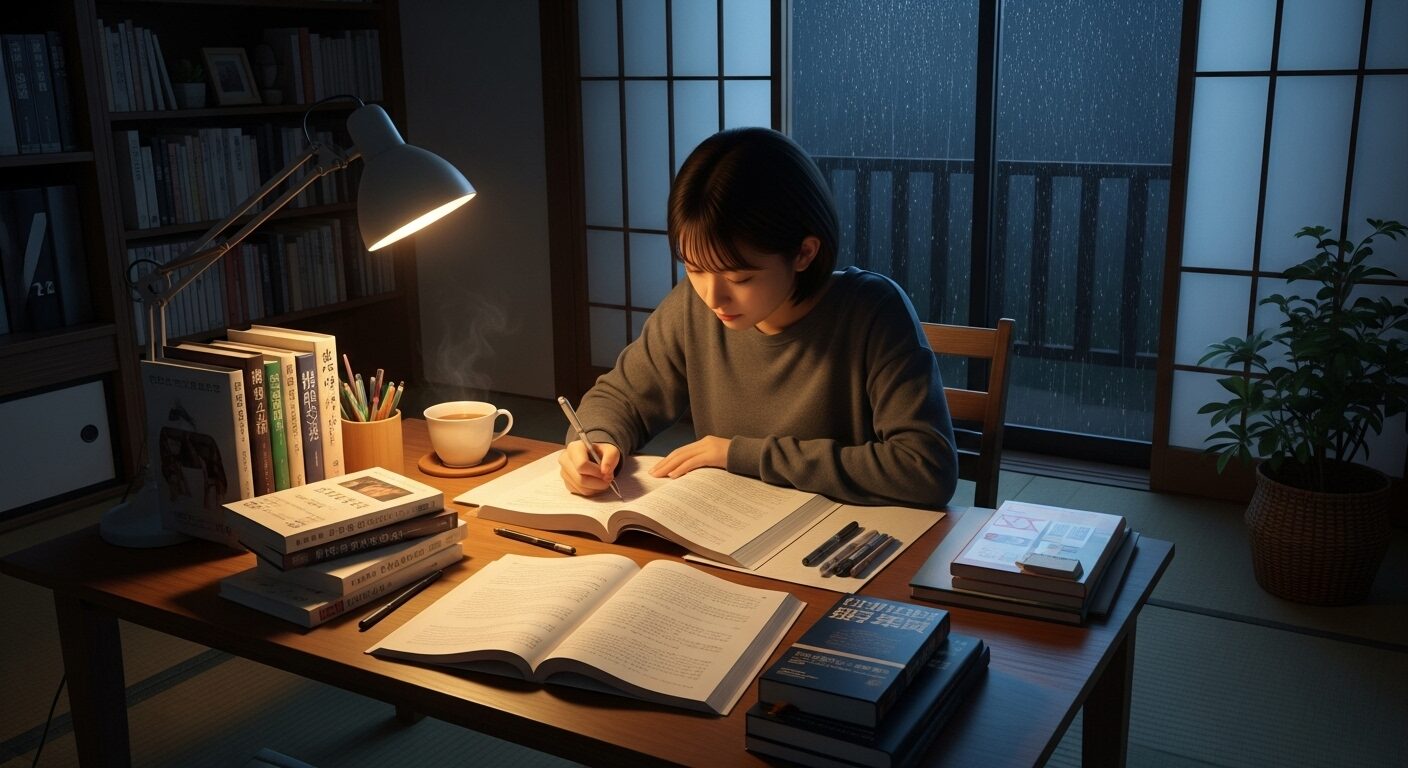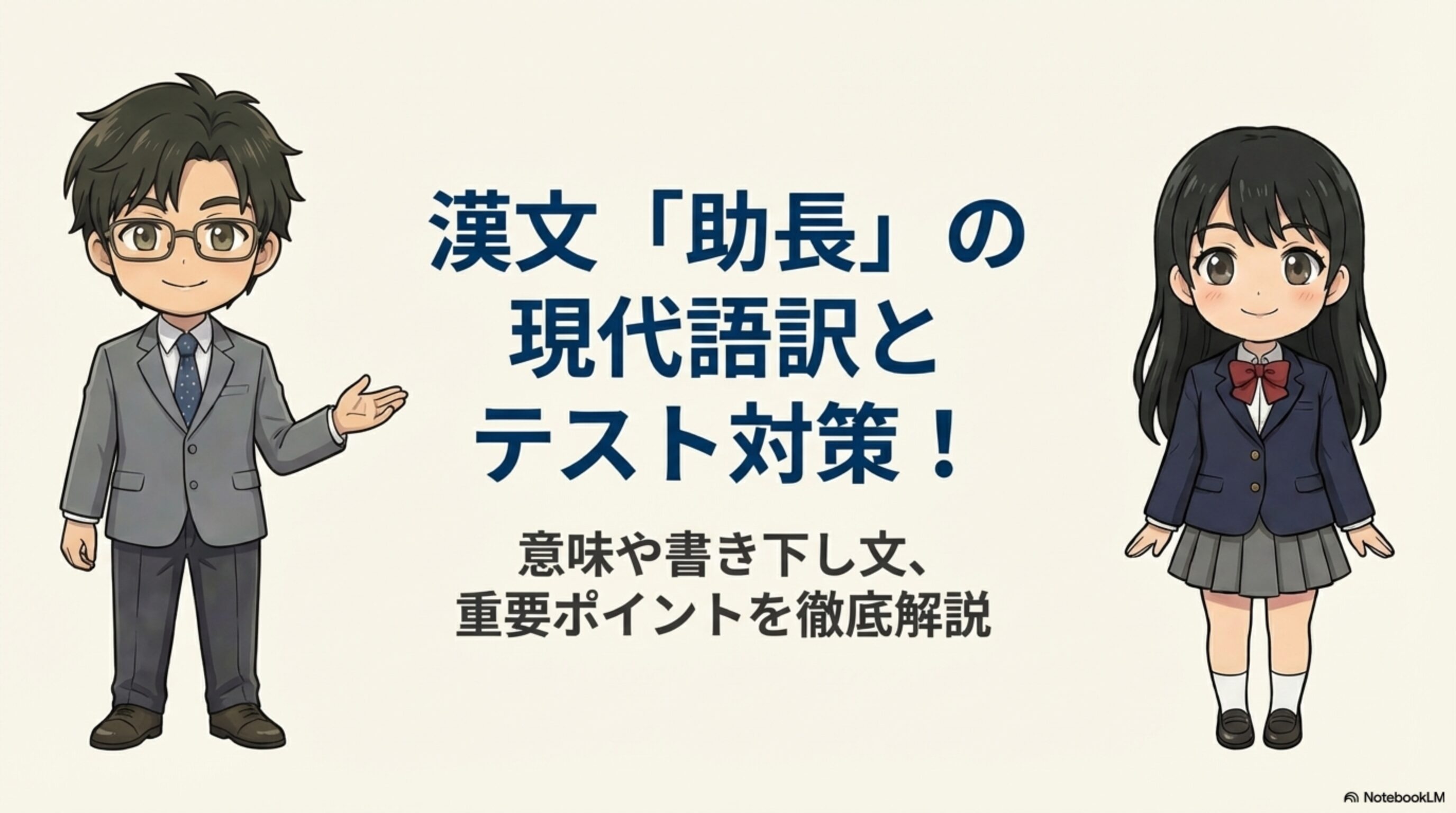【漢文】不などの否定形の読み方や訳し方を徹底解説|二重否定と部分否定の攻略法まで全網羅

漢文の学習を進める上で、多くの人が最初の壁として感じるのが、複雑で多様な「否定形」ではないでしょうか。種類が多く、それぞれの訳や使い方を覚えるのに苦労している方も少なくないはずです。
特に、部分否定と全部否定の違いや、その覚え方、さらには漢文の二重否定や特殊な否定のルールは、一見すると非常に複雑に感じられるかもしれません。しかし、漢文の否定形はまるでパズルのような明確なルールを持っており、一度その仕組みを理解すれば、文章全体の意味を正確に捉える力が飛躍的に向上します。
この記事では、基本的な否定形の一覧から、不可能や禁止を表す句形、そして応用的な二重否定まで、豊富な例文と共に一つひとつ丁寧に分かりやすく解説します。最後には実践的な練習問題も用意していますので、この記事を最後まで読めば、あなたの漢文読解力は一段上のレベルに到達するでしょう。
漢文の否定形|基本パターンを総まとめ
まずは基本の否定形一覧から
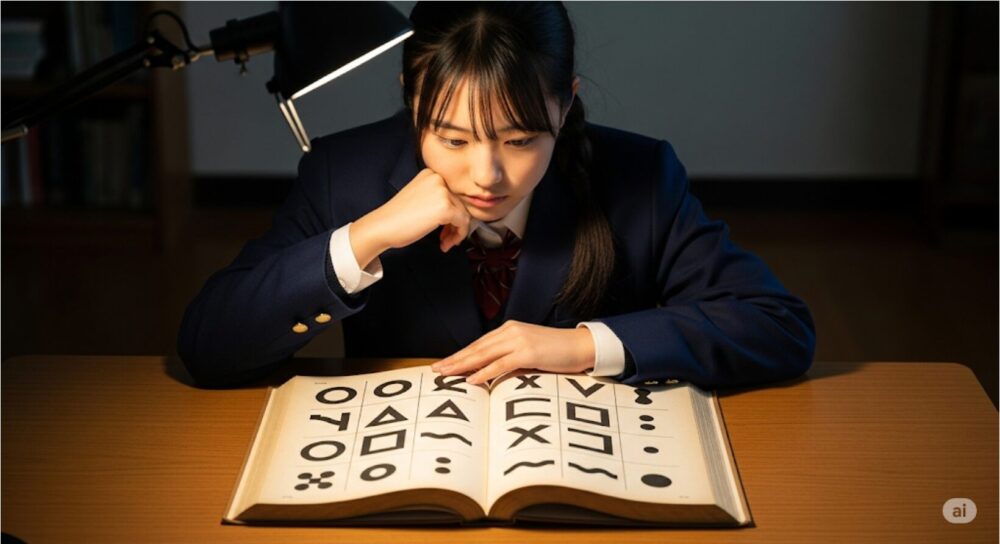
漢文における否定表現をマスターするには、まず核となるいくつかの基本的な漢字を覚えることから始まります。これらはそれぞれ異なるニュアンスや文法的な役割を持っており、その違いを正しく理解することが、正確な読解への第一歩となります。
驚くかもしれませんが、私たちが日常で使っている「不可能」や「非常識」、「未定」といった熟語も、これから学ぶ漢文の否定ルールが深く関わっています。まずは、最も重要となる4つの基本的な否定の漢字について、その特徴を表で詳しく確認しましょう。
否定の基本4類型
漢文の否定は、主に「不」「非」「無」「未」の4つの漢字が基礎となります。これらを理解することが、全ての否定表現を攻略する鍵となります。
| 否定詞 | 読み方 | 基本的な意味 | 主に否定する対象 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 不 (弗) | ~ず | ~しない | 動詞・形容詞など(用言) | 動作や状態といった、客観的な事実を打ち消す際に最も広く使われます。 |
| 非 (匪) | ~にあらず | ~ではない | 名詞など(体言) | 「AはBではない」という断定の否定。価値判断や定義を打ち消すニュアンスです。 |
| 無 (莫) | ~なし | ~がない | 名詞(存在の否定) | 人・物・事柄の存在そのものを否定します。「無礼」のように概念の不在も示します。 |
| 未 | いまだ~ず | まだ~ない | 動作の未完了 | 時間的な要素を含み、現時点での未完了や未経験を表す再読文字です。 |
この表にあるように、どの漢字が使われているかによって、何を否定したいのかが大きく異なります。「不」は動作や状態を、「非」は物事の性質や定義を、「無」は存在そのものを否定するのです。そして、「未」は「まだ」という時間的な要素を含む否定表現であることが分かります。この使い分けは、現在の高等学校学習指導要領における古典の読解でも重要な基礎知識とされています。(参照:文部科学省 高等学校学習指導要領(平成30年告示)解説 国語編)
まずはこの4つの漢字の基本的な役割を覚えるのがおすすめです。特に「不」は用言を、「非」は体言を否定するという使い分けは、テストでも頻繁に問われる非常に重要なポイントになりますよ。
句形ごとの基本的な訳し方

基本的な否定の漢字4種類を理解したら、次はそれぞれの具体的な訳し方を、より深く掘り下げて見ていきましょう。文脈によって微妙な解釈は変わりますが、まずはそれぞれの漢字が持つ中核的なニュアンスをしっかりと身につけることが大切です。
「不(弗)」の訳し方:客観的な打ち消し
「不」は、動詞や形容詞などの用言を打ち消し、「~しない」「~ではない」と訳すのが基本です。これは、書き手の主観を交えず、客観的な事実として動作や状態を否定する際に用いられます。
例えば、「不聞」であれば「聞かず(聞かない)」、「不高」であれば「高からず(高くない)」となります。単純な動作や状態の否定を表す、最も使用頻度の高い否定詞と言えるでしょう。
「非(匪)」の訳し方:断定・価値判断の否定
「非」は、主に名詞などの体言を打ち消し、「~ではない」と訳します。これは単なる事実の否定ではなく、「AはBというカテゴリーには属さない」という強い断定の否定や、価値判断を伴う否定に使われます。
例えば、「非人」であれば「人にあらず(人間ではない)」となり、そのものの本質を否定する強い意味合いを持ちます。また、「是々非々(ぜぜひひ)」という言葉のように、良いことと悪いこと(非)を判断する、という文脈でも使われます。
「無(莫)」の訳し方:存在の否定
「無」は、人や物、事柄が存在しないことを示し、「~がない」と訳します。これは物理的な存在だけでなく、抽象的な概念の不在を示す場合にも使われます。
「無人」であれば「人無し(人がいない)」という物理的な不在を、「無意味」であれば「意味無し(意味がない)」という概念的な不在を表します。存在の有無に関する明確な否定表現です。
「未」の訳し方:時間的な未完了
「未」は再読文字であり、一度返って読んでから再び読む特殊な文字ですが、意味は「まだ~ない」と訳します。現時点では完了していない、あるいは経験していないことを示す、時間軸を意識した否定です。
「未見」であれば「未だ見ず(まだ見ていない)」となり、将来的に見る可能性は否定していませんが、現時点での未完了・未経験を明確に伝える表現です。これが発展し、「未嘗不~(いまだかつて~ずんばあらず)」のような二重否定にも繋がっていきます。
豆知識:「弗」や「莫」について
「弗」は「不」とほぼ同じ意味で使われる異体字で、特に否定の意味を強調したい時に使われることがありました。同様に「莫」も「無」と近い意味で使われますが、文脈によっては「~するものはない」という、範囲内のすべてを否定する強い限定を示す場合があります。まずは「不」と「無」の基本をしっかり押さえることが重要です。
不可能を表す表現

漢文には、単純な否定だけでなく「~することができない」という不可能を表す表現も頻繁に登場します。これらは能力的な制約や、状況による制約を示す重要な句形であり、筆者が置かれた状況や心情を理解する上で欠かせません。
代表的な不可能の表現は以下の3つですが、それぞれのニュアンスの違いを理解することが重要です。
| 句形 | 読み方 | 意味 | ニュアンス |
|---|---|---|---|
| 不能 | ~する(こと)あたはず | ~することができない | 能力がなくてできない。「能」の字がヒント。 |
| 不可 | ~すべからず | ~することができない | 物理的・状況的に妨げられてできない。 |
| 不得 | ~する(こと)をえず | ~することができない | 許可・機会が得られなくてできない。「得」の字がヒント。 |
これらの違いを具体的なシチュエーションで考えてみましょう。例えば、「川を渡れない」という状況でも、泳ぐ能力がないのであれば「不能渡」、川の流れが速すぎて物理的に無理なのであれば「不可渡」、そして渡ることが禁じられているのであれば「不得渡」といった使い分けが考えられます。
「不能」は、「能力」という言葉からも分かるように、主に能力がなくて「できない」というニュアンスで使われます。一方で「不得」は、「得る」という字から連想できるように、機会や許可が得られなくて「できない」という状況的な制約を表すことが多いです。
「不可」の二つの意味に注意
「不可」は「~できない」という不可能の意味だけでなく、「~してはいけない」という禁止の意味で使われることもあります。どちらの意味になるかは文脈から判断する必要があるため、特に注意が必要です。見分けるヒントとして、主語が人間で意志的な行動に関する場合は「禁止」、主語が物事や状況である場合は「不可能」と解釈できることが多いです。
例えば、「不可食」という表現は、「食べることはできない(毒があるなど)」という不可能の意味にも、「食べてはいけない(規則など)」という禁止の意味にも解釈できる可能性があります。前後の文をよく読んで、どちらの意味が適切かを見極めましょう。
禁止を表す表現

「~してはならない」という禁止の意味を表す句形も、漢文では非常に重要です。相手の行動を制したり、道徳的な戒めを示したりする文脈で頻繁に使われます。これらの表現を正しく読み取ることは、文章の主題や筆者の主張を理解する上で不可欠です。
禁止を表す代表的な句形は以下の通りです。
| 句形 | 読み方 | 意味 | ニュアンス |
|---|---|---|---|
| 勿 (毋) | ~する(こと)なかれ | ~してはならない | 命令形を伴う直接的で強い禁止。 |
| 無 | ~する(こと)なかれ | ~してはならない | 「勿」と同様に強い禁止として使われることがある。 |
| 不可 | ~すべからず | ~してはいけない | 「~するべきではない」という道徳的・規範的な禁止。 |
最も代表的なのは「勿」で、「~することなかれ」と読みます。これは強い禁止を表し、命令文の形でよく使われます。例えば、有名な論語の一節「己の欲せざる所は、人に施すこと勿かれ」は、「自分がしてほしくないことは、他人にしてはならない」という意味の普遍的な戒めです。
前述の通り、「不可」も「~すべからず」という読みで禁止の意味を表します。こちらは「勿」よりも客観的で、「~するべきではない」という、少し理性的・道徳的なニュアンスを含むことがあります。「初心忘るべからず」のように、一般的な教訓として使われることが多いのが特徴です。
「勿(なかれ)」は命令形なので、会話文や誰かに直接語りかけるような場面で使われる強い禁止だと覚えておきましょう。一方、「不可(べからず)」は、より普遍的なルールや教えを示す時に使われることが多いですよ。
例文で使い方を確認しよう
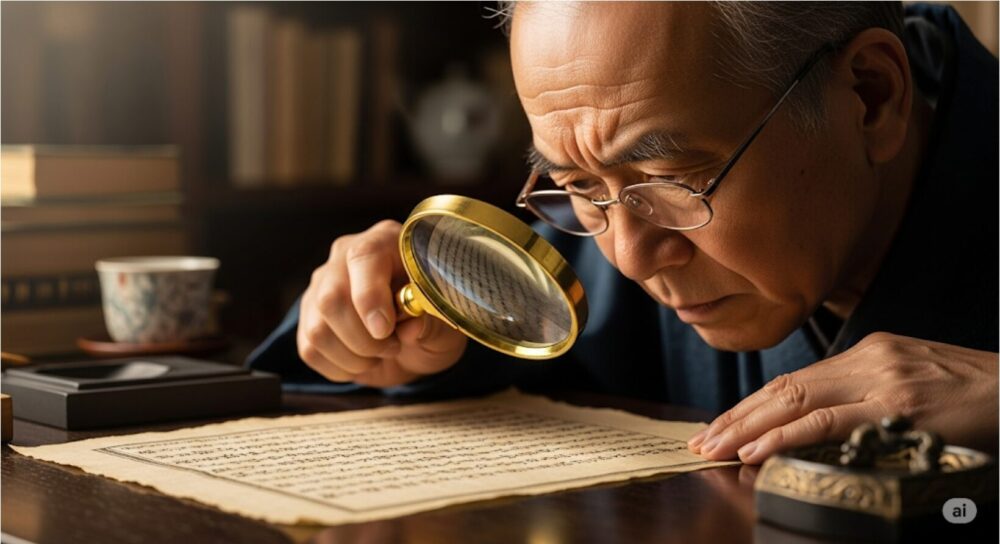
ここまでに学んだ基本的な否定・不可能・禁止の表現が、実際の文章でどのように使われているか、具体的な例文を通して確認してみましょう。古典の名文に触れることで、知識はより深く定着します。
例文1:単純否定「不」
- 原文:歳月不待人。(『雑詩』陶潜)
- 書き下し文:歳月は人を待たず。
- 現代語訳:年月は人の都合を待ってはくれない。
これは有名な句で、「待た」という動詞を「不」が打ち消しています。時間の流れという、人の力ではどうにもならない客観的な真理を、簡潔な否定形で表現しています。
例文2:断定の否定「非」
- 原文:城非不高也、池非不深也。(『孟子』)
- 書き下し文:城高くあらざるに非ず、池深くあらざるに非ず。
- 現代語訳:城が高くないのではなく、堀が深くないのでもない。
これは二重否定の形にもなっていますが、「非」が「高い」「深い」という状態そのものではなく、「高くない」「深くない」という断定を否定している点がポイントです。「問題はそこではない」という、筆者の主張を導くための表現です。
例文3:不可能「不能」
- 原文:食之不能尽其材。(『雑説』韓愈)
- 書き下し文:之を食ふに其の材を尽くさしむること能はず。
- 現代語訳:(十分な量の餌を)食べさせても、その才能を全て発揮させることはできない。
韓愈の『雑説』からの引用で、名馬も才能を発揮させる飼い主がいなければ力を出せない、という文脈です。「尽くさしむる(発揮させる)」という能力的な可能性を「能はず」で否定しています。
例文4:禁止「勿」
- 原文:過則勿憚改。(『論語』)
- 書き下し文:過てば則ち改むるに憚ること勿かれ。
- 現代語訳:過ちを犯したならば、改めることをためらってはならない。
こちらも論語の一節です。「憚る(ためらう)」という行為を「勿かれ」で強く禁止しています。過ちを認めてすぐに改めることの重要性を説く、普遍的な戒めの言葉です。これらの古典の原文や解釈は、国立公文書館アジア歴史資料センターなどのデジタルアーカイブで確認することもでき、学びを深める一助となります。
応用から実践まで|漢文の否定形をマスター
漢文の二重否定のパターン

漢文の応用的な表現として、否定の形を二つ重ねる「二重否定」があります。これは「~ないことはない」という形で、結果として強い肯定や断定、あるいは婉曲な肯定を表す重要な句法です。単に肯定するよりも、一度否定を挟むことで、表現に深みや強調のニュアンスが生まれます。
数学のマイナス×マイナスがプラスになるように、否定を否定することで肯定的な意味合いを持ちます。しかし、文脈によっては「〜しないわけではないが…」といった含みを持たせることもあります。代表的なパターンを網羅的に見てみましょう。
| 句形 | 読み方 | 意味 | ニュアンス |
|---|---|---|---|
| 無不~ | ~せざるはなし | ~しないものはない | 【強い肯定】例外なく全てが~する。 |
| 非不~ | ~せざるにあらず | ~しないのではない | 【婉曲な肯定】(表面的にはそう見えなくても)実は~する。 |
| 莫非~ | ~にあらざるはなし | ~でないものはない | 【強い断定】例外なく全てが~である。 |
| 非無~ | ~なきにあらず | ~がないのではない | 【婉曲な肯定】(ないように見えるが)実はある。 |
| 不可不~ | ~せざるべからず | ~しないわけにはいかない | 【強い義務】~しなければならない。 |
| 未嘗不~ | いまだかつて~ずんばあらず | 今まで~しなかったことはない | 【強い経験の肯定】いつも必ず~してきた。 |
例えば「無不勝」は、「勝たざるは無し」と読み、「勝たないことはない」、つまり「必ず勝つ」という強い肯定になります。また、「非不説」は、「説ばざるに非ず」と読み、「喜ばないのではない」、つまり「(口には出さないが)本当は喜んでいる」といった、少し控えめな肯定を表し、話し手の複雑な心情を表現します。
二重否定は、単なる肯定文よりも強調のニュアンスが加わることが特徴です。なぜ筆者がわざわざ回りくどい表現を選んだのか、その裏にある感情や意図を読み取ることが、高度な読解の鍵となります。
部分否定と全部否定の違いとは?

漢文の否定形の中でも特に混乱しやすく、しかし極めて重要なのが、「部分否定」と「全部否定」の見分け方です。この違いを読み間違えると、筆者の主張を全く逆の意味で捉えてしまう危険性さえあります。これは、否定語と特定の副詞(常、必、倶、尽など)の位置関係によって意味が大きく変わるという、漢文特有の精密なルールです。
違いは非常にシンプルで、語順によって明確に決まります。
語順による意味の変化
部分否定:「不」+ 副詞 の語順
- 訳:「いつも~するとは限らない」「必ずしも~ではない」
- 意味:100%ではない、という部分的な否定。例外があることを示す。
全部否定:副詞 +「不」 の語順
- 訳:「いつも~しない」「決して~しない」
- 意味:100%そうではない、という全面的な否定。例外がないことを示す。
具体例で比較
例えば、「常(いつも)」という副詞を使った場合で比べてみましょう。
部分否定:「不常有」
書き下し:常には有らず。
訳:いつもいるとは限らない。(いる時もあれば、いない時もある)
全部否定:「常不有」
書き下し:常に有らず。
訳:いつもいない。(全くいない)
このように、否定語である「不」が副詞「常」の前にあるか後にあるかで、意味が全く逆になります。部分否定は「100%そうである」という考えを打ち消すのに対し、全部否定は「100%そうでない」という事実を断定する表現なのです。このルールは、筆者の主張の強さや範囲を正確に読み取るために不可欠です。
部分否定と全部否定の覚え方
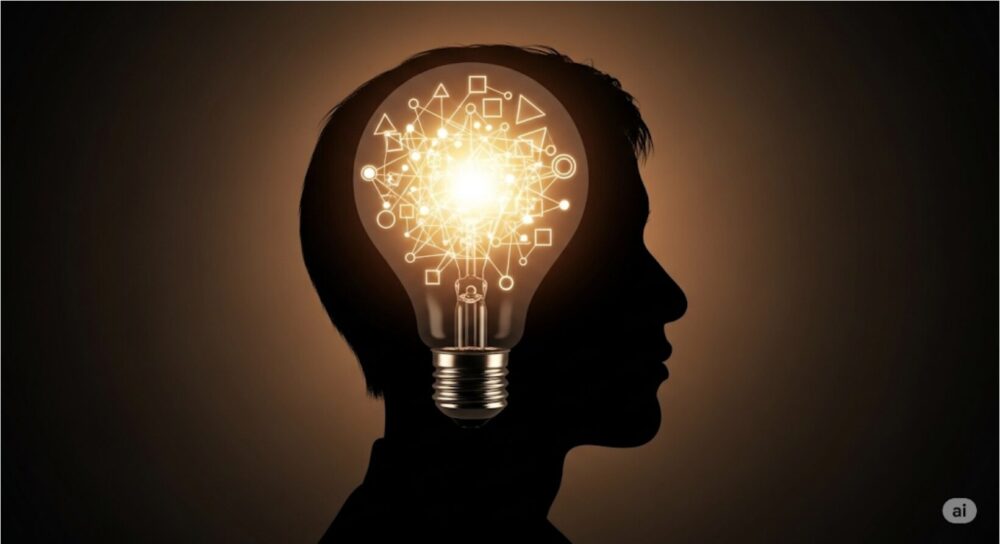
部分否定と全部否定のルールは、理屈で理解しても、いざテストや読解の場面で「どっちがどっちだっけ?」と混乱しがちです。そこで、一度覚えれば忘れにくい、簡単な覚え方のコツを紹介します。
覚え方のコツ:「否定が先なら部分的」
「不」のような否定語が、副詞(常、必など)よりも先に来ていれば、それは部分否定です。これを呪文のように覚えてしまいましょう。「不が先、だから部分」とリズムで覚えるのも効果的です。
なぜこの覚え方で良いのか、もう少し理屈を考えてみると、より記憶が定着しやすくなります。漢文の語順は基本的に「修飾語→被修飾語」です。これを当てはめてみましょう。もっと詳しく言うなら、漢文の否定語は原則下の語や句にかかると考えるのです。
- 部分否定:「不 [常 有]」
この構造は、「[常に有る]という状態を、不(否定する)」と捉えることができます。つまり、「常に有るわけではない」という意味になります。 - 全部否定:「常 [不 有]」
こちらの構造は、「常に、[有らず(いない)]という状態だ」と解釈できます。そのため、「いつもいない」という全部否定の意味になるのです。
書き下し文にする際の送り仮名も非常に重要なヒントになります。部分否定では「常には」「必ずしも」のように、「は」や「しも」といった助詞が付くのが鉄則です。

この送り仮名を見逃さないようにすれば、間違うことは格段に減りますよ!
部分否定の一覧

漢文の読解で特に重要なのが「部分否定」です。これは、特定の副詞と否定語「不」が結びつくことで、「100%〜というわけではない」という、一部分を否定するニュアンスを生み出す表現です。「不 + 副詞」という語順が原則となるこの形は、全部否定との区別がテストでも頻繁に問われます。ここでは、覚えておくべき代表的な部分否定の句形を一覧で詳しく解説します。
部分否定の基本ルール
語順は「不 + 副詞」となり、書き下す際は「〜には」「〜とは」「〜しも」といった送り仮名が付くのが特徴です。
| 句形 | 読み方 | 訳し方 | 意味と例文の解説 |
|---|---|---|---|
| 不常 | 常には~ず (つねには~ず) | いつも~するとは限らない | 100%の恒常性(いつもそうであること)を否定します。「そうである時もあれば、そうでない時もある」という状況を示します。 例文:伯楽不常有。(伯楽は常には有らず。) →名馬を見抜く名人である伯楽は、いつも世の中にいるとは限らない。 |
| 不必 | 必ずしも~ず (かならずしも~ず) | 必ずしも~するとは限らない | 100%の必然性(必ずそうであること)を否定します。例外の存在を示唆する表現です。 例文:有言者不必有徳。(言有る者は必ずしも徳有らず。) →口が達者な人が、必ずしも徳を備えているとは限らない。 |
| 不倶 | 倶には~ず (ともには~ず) | 両方とも~するわけではない | 複数の対象(主に二者)が、そろって同じ状態になることを否定します。「どちらか一方はそうならない」という意味合いです。 例文:其勢不倶生。(其の勢ひ倶には生きざらん。) →(二頭の虎が争えば)その成り行きとして、両方とも生き残るわけではない(どちらかは死ぬだろう)。 |
| 不尽 | 尽くは~ず (ことごとくは~ず) | すべてが~というわけではない | 範囲内のもの全てが、同じ状態であることを否定します。「知っている部分もあれば、知らない部分もある」という状況です。 例文:不尽知。(尽くは知らず。) →全てを知っているわけではない。 |
| 不甚 | 甚だしくは~ず (はなはだしくは~ず) | それほど~ではない あまり~しない | 程度が極端であることを否定する表現です。「全くしないわけではないが、程度は高くない」というニュアンスになります。 例文:好読書不求甚解。(書を読むを好めども甚だしくは解することを求めず。) →読書は好きだが、それほど深く理解することまでは求めない。 |
| 不重 | 重ねては~ず (かさねては~ず) | 再び~するとは限らない | 同じことが繰り返される必然性を否定します。「一度は勝てても、次も勝てるとは限らない」といった戒めの文脈で使われることがあります。 例文:兵不重勝。(兵は重ねては勝たず。) →軍は何度も勝ち続けるとは限らない。 |
【例外】意味が強くなる「不復」
部分否定の形(不+副詞)をとりながら、意味合いが全部否定に近くなる例外が「不復」です。
読み:復た~ず(また~ず)
訳:二度と~しない/決して~しない
これは「再び~することはない」という強い否定となり、部分否定の「~とは限らない」という訳にはならないため、特別な句形として覚えましょう。「二度と~しない/決して~しない」の使い分けは一度その行動したかどうか文脈で判断しましょう。
例文:黄鶴一去不復返。(黄鶴一たび去りて復た返らず。)
→黄色い鶴は一度飛び去って、二度と帰ってこなかった。
部分否定は、送り仮名が最大のヒントになります。「常には」「必ずしも」のように、「は」や「しも」が付いていたら「部分否定だ!」と判断するクセをつけると、テストでのミスがぐっと減りますよ。ただし、例外の「不復」だけは注意してくださいね!
覚えておきたい特殊な否定

これまで紹介した基本的な否定形や応用形以外にも、特定の漢字と組み合わさることで特殊な意味を持つ、いわば「熟語的」な否定表現が存在します。これらは頻出度も高く、意味を知らないと全く解釈できない場合があるため、個別に覚えてしまうのが最も効果的です。
敢へて~ず(不敢~):消極的な否定
「不敢~」は、「敢へて~ず」と読みます。これは「決して~しない」という強い意志の否定ではなく、「(恐れ多くて)進んで~しようとはしない」「~する勇気がない」といった、やや消極的・遠慮がちな否定を表します。話し手の謙遜や恐怖の感情を読み取ることができます。
- 例文:不敢仰視。(敢へて仰ぎ視ず。)
- 訳:(相手が偉すぎて恐れ多くて)進んで仰ぎ見ようとはしない。
~するに勝へず(不可勝~):数量の膨大さ
「不可勝~」は、「~するに勝へず」と読みます。直訳すると「~しきることができない」となり、数量が非常に多くて数えきれない、または全てを処理しきれないことを表す誇張表現です。
- 例文:其功不可勝計。(其の功は計ふるに勝へず。)
- 訳:その功績は(あまりに多くて)数えきれないほどだ。
無A無B(AもなくBもなく):区別の否定
「無A無B」は、「Aと無くBと無く」と読み、厳密には否定の並列ですが、特殊な使い方として重要です。「AもBもない」という意味ではなく、「AとかBとかの区別なく」という意味になります。
- 例文:無貴無賤。(貴と無く賤と無く。)
- 訳:身分が貴いとか賤しいとかの区別なく。
反語との関係性について
否定形は、文末に「乎」「哉」「也」などの疑問や詠嘆を表す助字が付くことで、反語(~だろうか、いや~ない)や詠嘆(なんと~ではないか)の意味に変化することがあります。例えば「不亦楽乎(亦た楽しからずや)」は「なんと楽しいことではないか」という詠嘆になります。文末の助字を見逃さず、文脈全体を見て、単なる否定なのか、それとも反語や詠嘆といった強調表現なのかを慎重に判断することが重要です。
練習問題で理解度をチェック
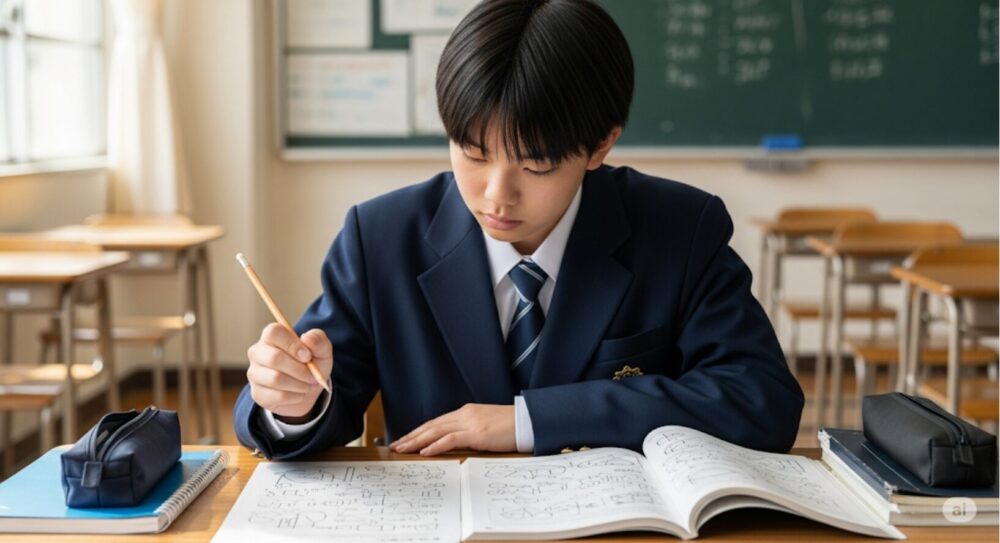
それでは、この記事で学んだ知識がしっかりと身についているか、少し難易度を上げた練習問題で最終確認をしてみましょう。解答と丁寧な解説は下にありますので、まずは時間を計って自力で解いてみてください。
問題
問1:次の文を書き下し文にし、現代語訳しなさい。
「未嘗不廃書而歎也。」
問2:「AとしてBせざるは無し」と読む二重否定の白文を完成させなさい。
「無( )不( )」
問3:「必ずしも仁有らず。」の白文として正しいものを次から選びなさい。
ア:必不有仁。
イ:不必有仁。
ウ:不有必仁。
問4:「不可勝数」の現代語訳として最も適切なものを次から選びなさい。
ア:数えることができない
イ:数えてはいけない
ウ:数えきれないほど多い
問5:次の文の「不可」は「不可能」と「禁止」のどちらの意味で使われているか答えなさい。
「一寸光陰不可軽。」
解答と解説
問1:
書き下し文:未だ嘗て書を廃して歎ぜずんばあらざるなり。
現代語訳:今まで(本を読んで)書物を手放して嘆息しなかったことはない。(=いつも必ず嘆息した)
解説:「未嘗不~」の二重否定です。「今まで~しなかったことはない」という、強い経験の肯定を表します。
問2:
答え:無(A)不(B)
解説:「どんなAでもBしないものはない」という意味の二重否定の構文です。非常に強い肯定を表します。
問3:
答え:イ
解説:「必ずしも~ない」は部分否定です。部分否定は「不+副詞」の語順になるため、「不必」となります。アは「必ず仁有らず」という全部否定です。
問4:
答え:ウ
解説:「不可勝~」は「~しきれないほど多い」という、数量の膨大さを表す特殊な否定形です。アの「数えることができない」は「不能数」に近くなります。
問5:
答え:禁止
解説:「ほんのわずかな時間も、軽んじてはいけない」という意味の文脈です。主語は人間(私たち)であり、その行動を戒めているため「禁止」の意味となります。
まとめ:漢文の否定形を攻略しよう
漢文の否定形は一見複雑ですが、基本となるパターンと応用的なルールを一つひとつ着実に押さえることで、必ず得意分野に変えることができます。この記事で学んだ重要なポイントを最後にリストで振り返り、あなたの知識を確実なものにしましょう。
- 漢文の否定の基本は不・非・無・未の4つの漢字から成る
- 不は動詞や形容詞など用言を否定し客観的な事実を示す
- 非は名詞など体言を否定し「~ではない」と断定を打ち消す
- 無は物理的・概念的な存在を否定し「~がない」と訳す
- 未は時間的な未完了を表し「まだ~ない」と訳す再読文字である
- 不可能は能力が欠ける「不能」、機会がない「不得」、物理的に無理な「不可」を使い分ける
- 禁止は直接的な命令の「勿(なかれ)」と規範的な「不可(べからず)」が代表的
- 二重否定は否定の否定で強い肯定や婉曲な肯定、強い義務などを表す
- 無不~は「~しないものはない」という例外なき肯定
- 非不~は「~しないのではない」という婉曲な肯定
- 不可不~は「~しなければならない」という強い義務を表す
- 部分否定と全部否定は否定語と副詞の語順で決まるという鉄則がある
- 「不+副詞」の語順なら部分否定(~とは限らない)
- 「副詞+不」の語順なら全部否定(決して~ない)
- 「否定が先なら部分的」と覚えるのが効果的
- 敢へて~ずは「進んで~しない」という消極的な否定
- 不可勝~は「~しきれないほど多い」という数量の多さを表す
- 否定形と文末の助字が結びつくと反語や詠嘆になる場合があるので注意が必要