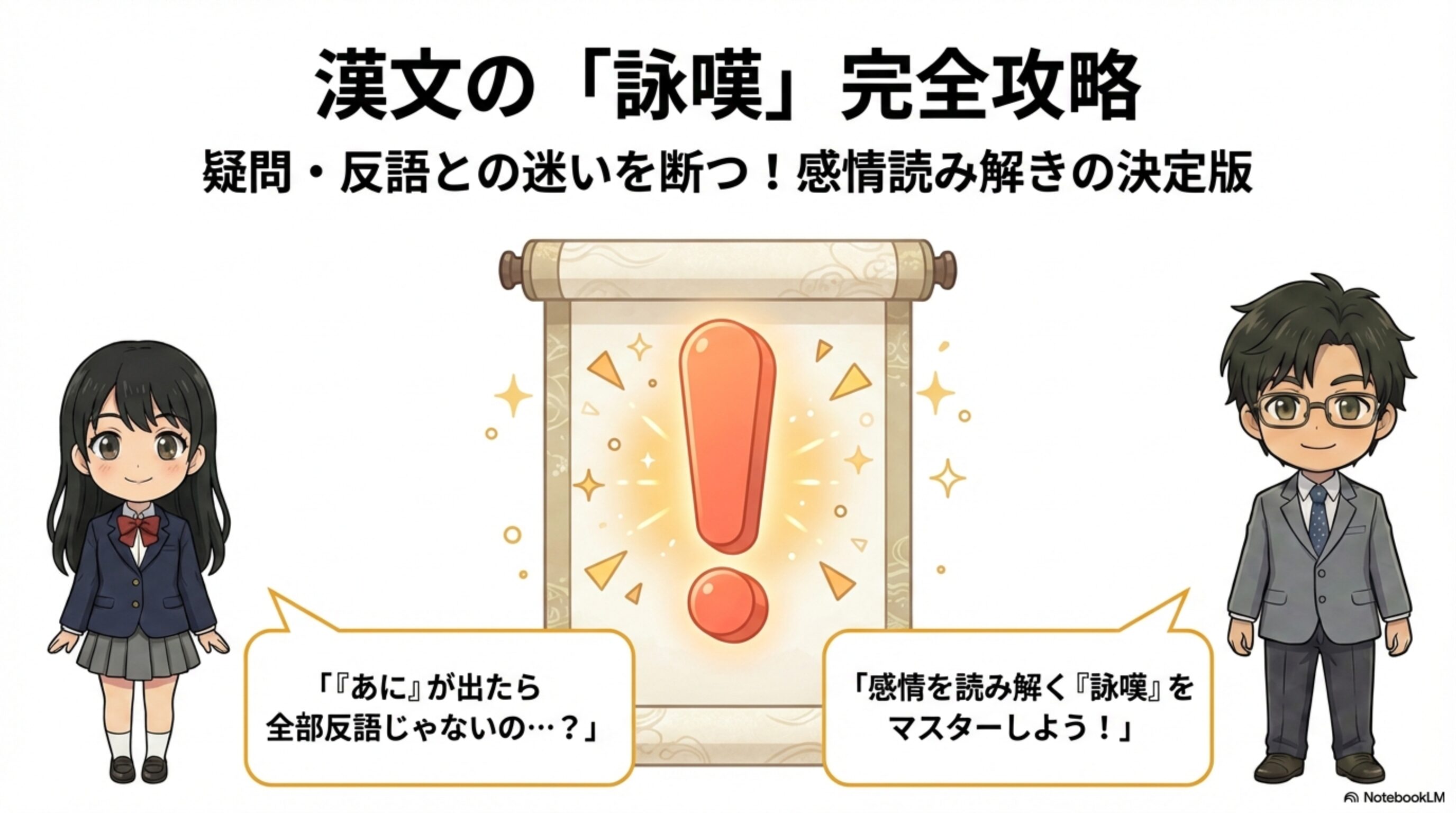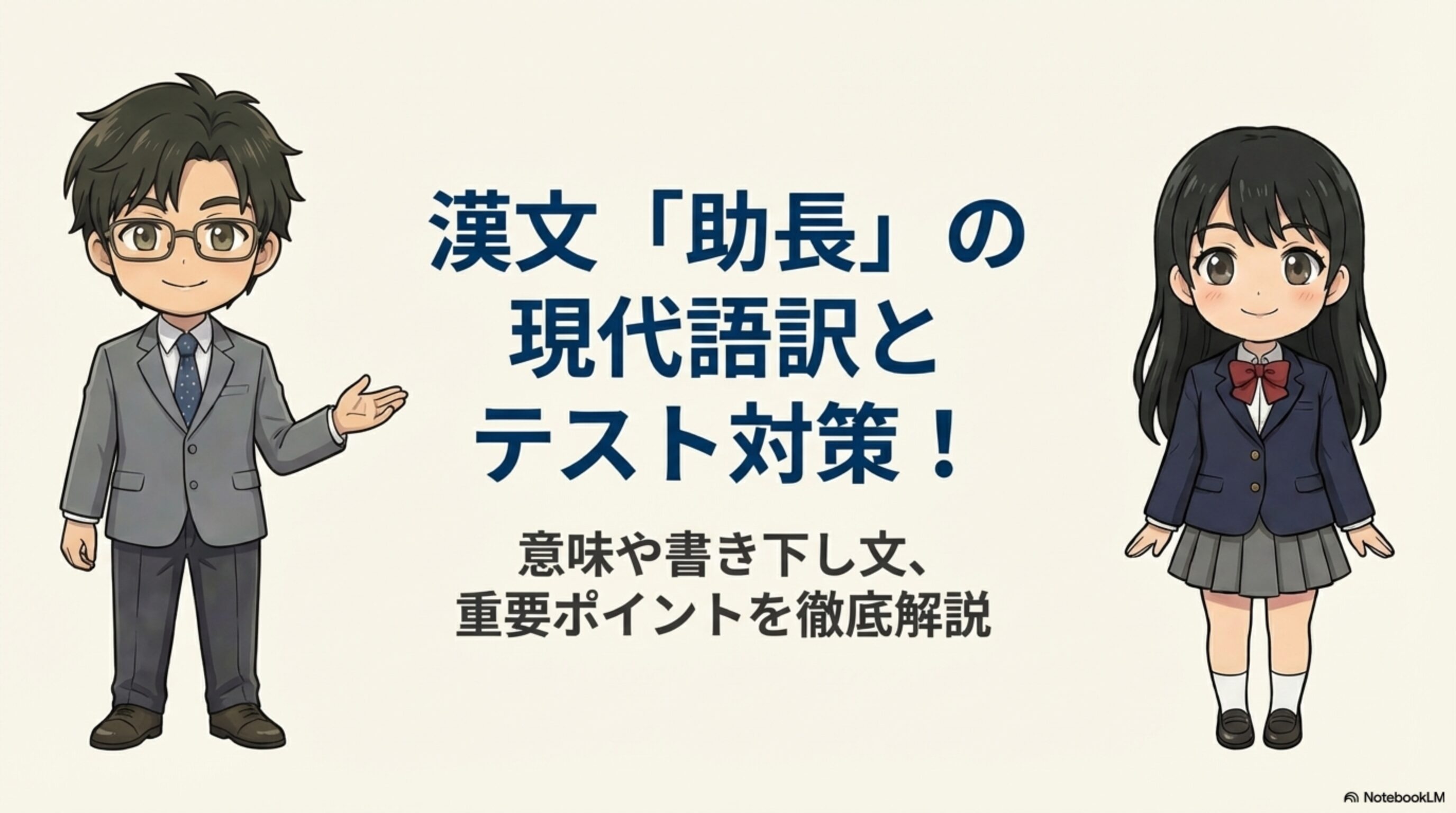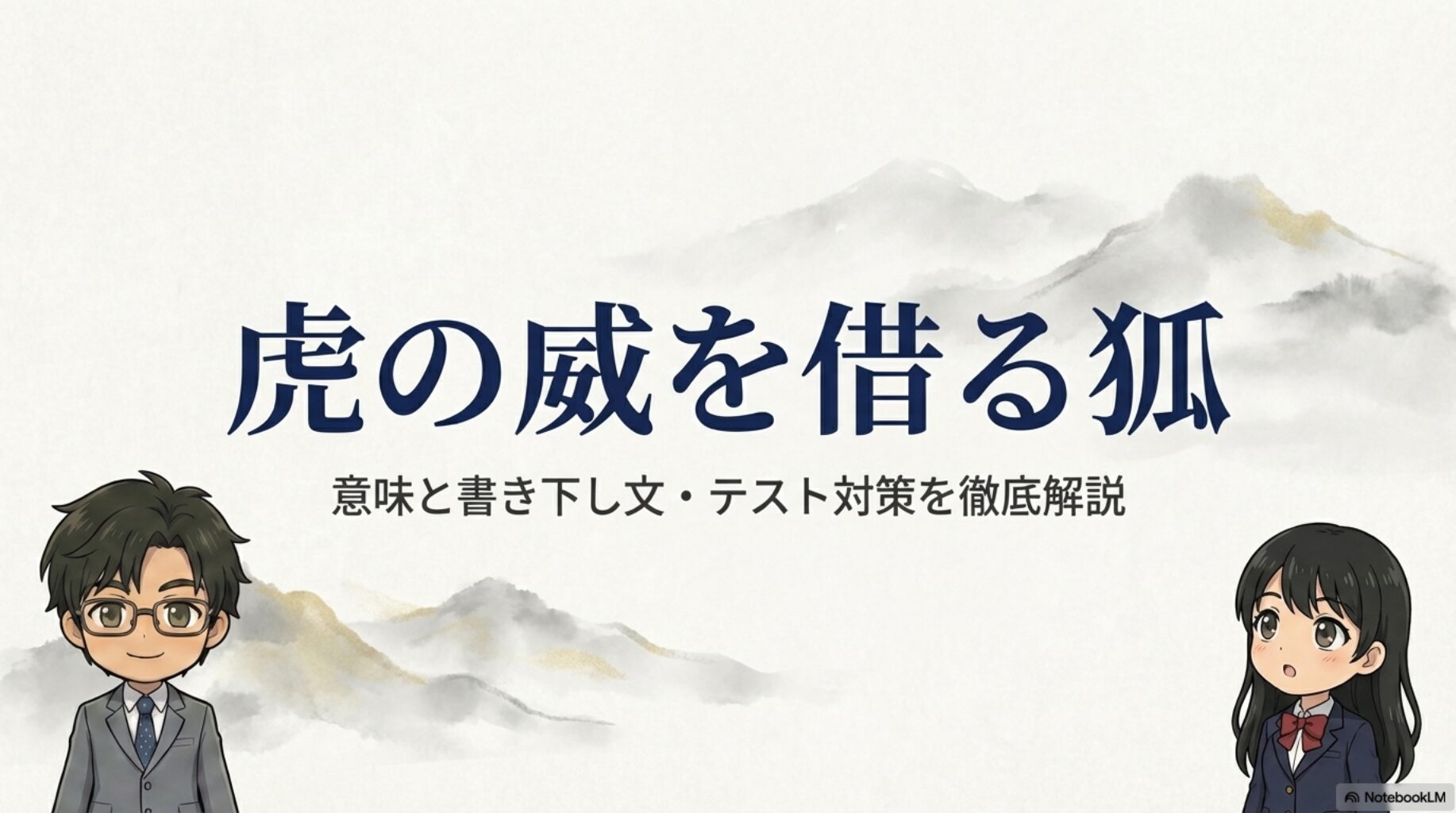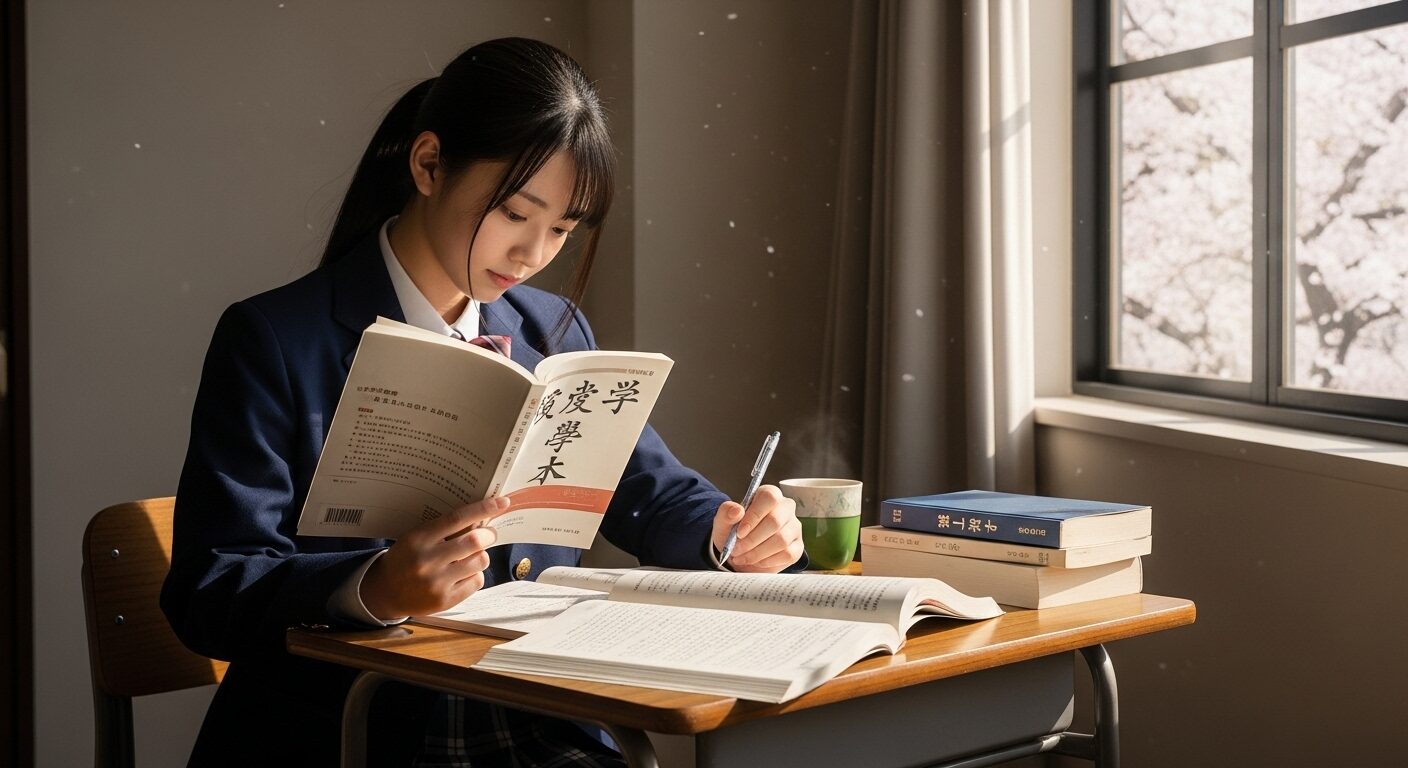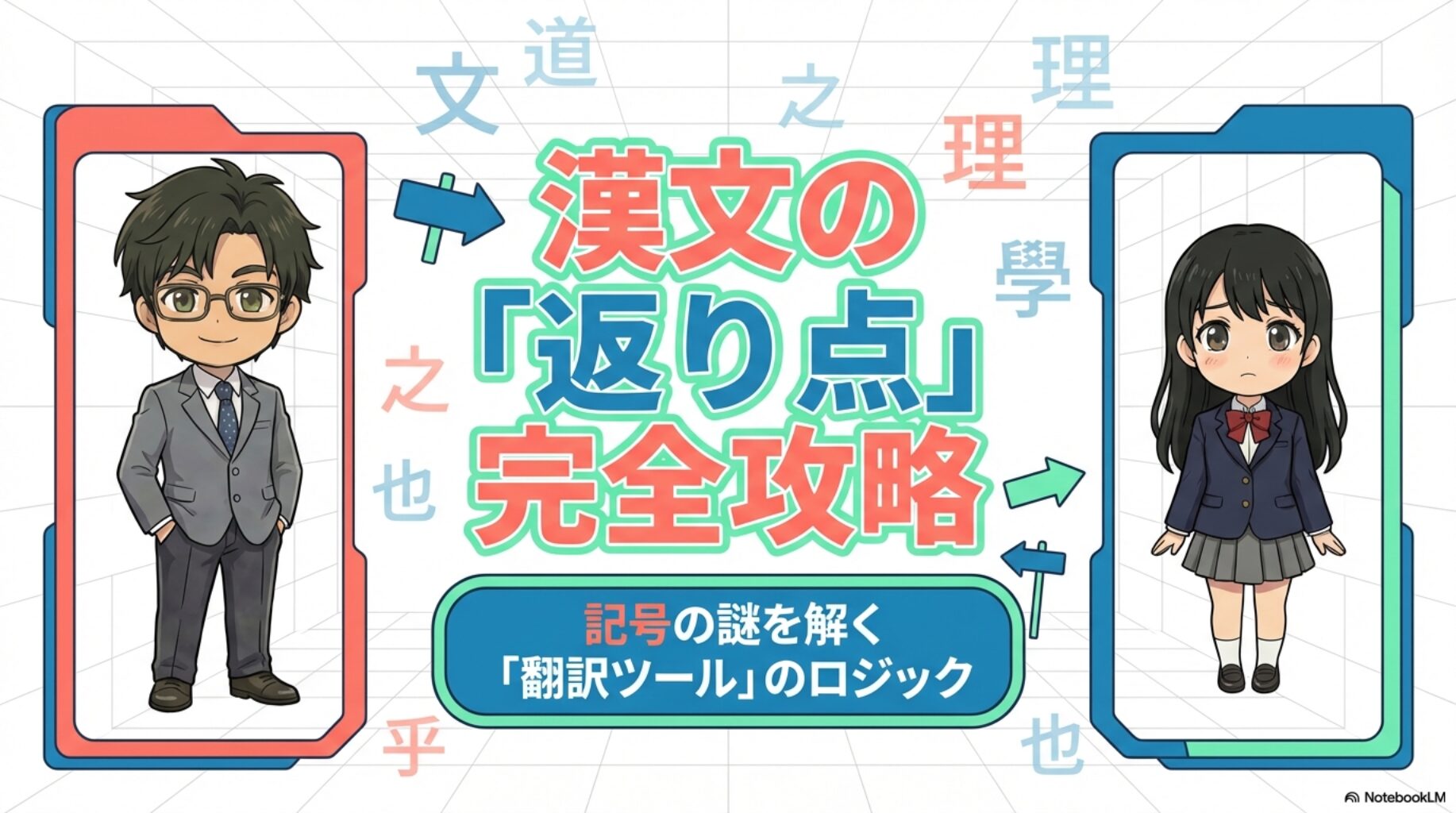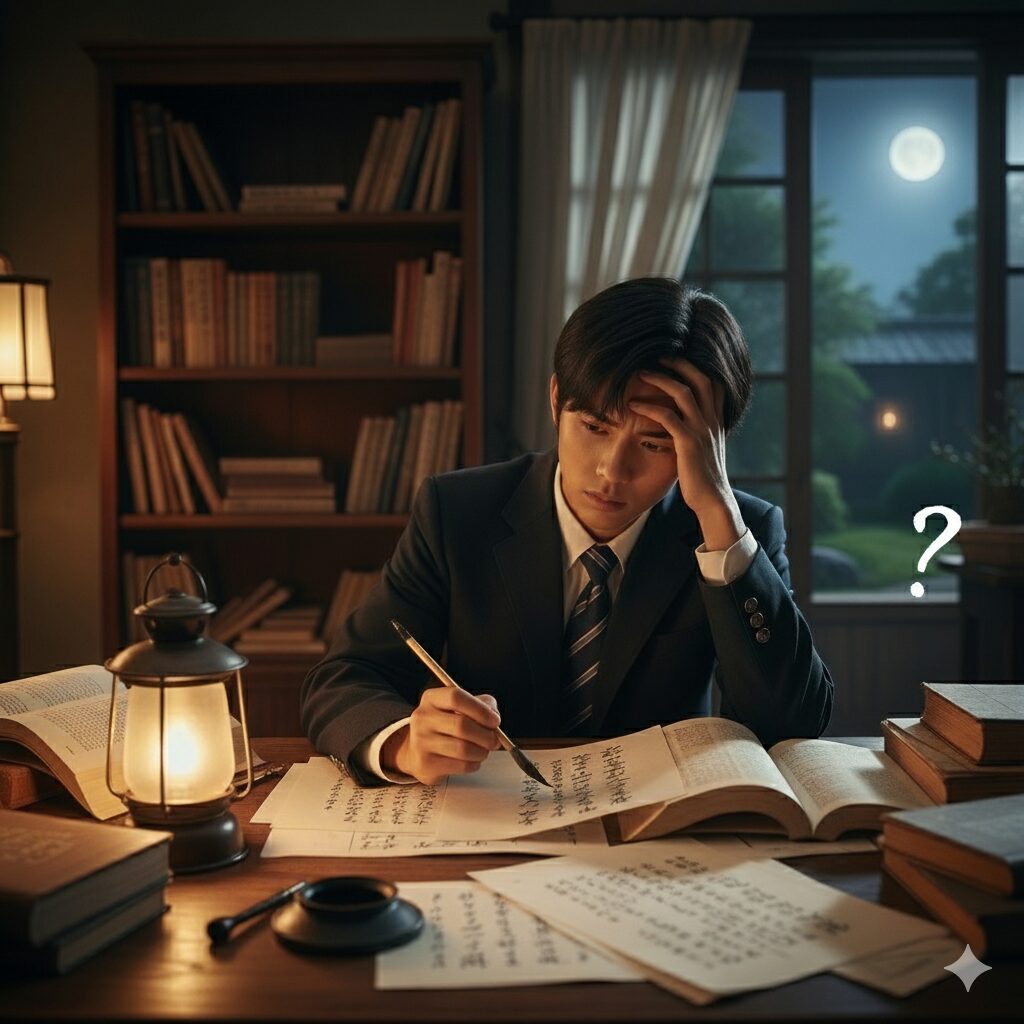漢文の白文の読み方を解説!基礎から学ぶ勉強法
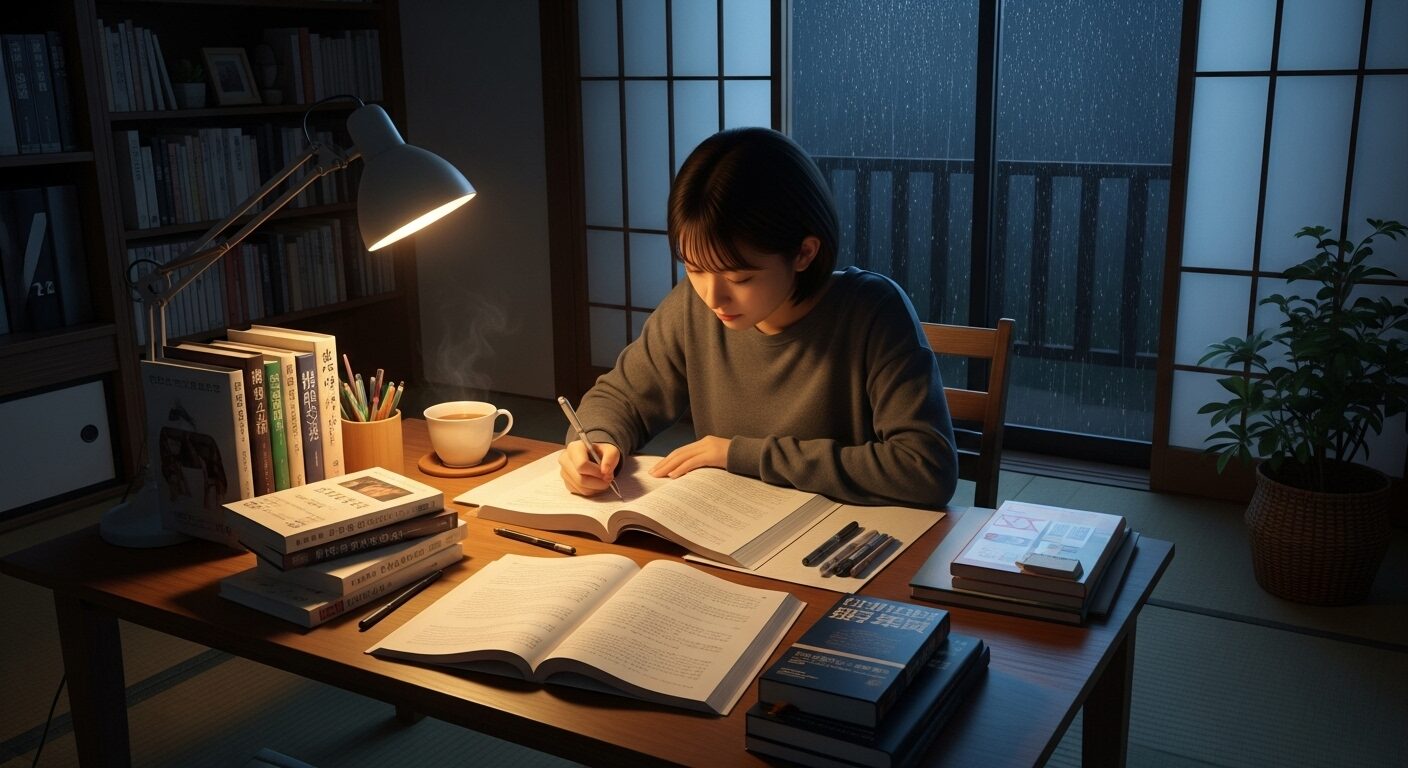
漢文の学習を進める上で、多くの高校生や大学受験生が大きな壁として感じる「白文」。返り点や送り仮名といった補助記号が一切ないため、「漢字が並んでいるだけで、どこからどう読めばいいのか全くわからない」と途方に暮れてしまう方も少なくないでしょう。
そもそも、普段目にする「漢文」と「白文」の違いが曖曖昧な方もいるかもしれません。しかし、ご安心ください。実は、難解に見える白文の読み方をマスターするには、いくつかの確かなコツが存在します。
その核心は、日本語とは根本的に異なる漢文特有の語順を理解し、意外にも共通点が多い英語の文構造と比較しながら学ぶアプローチにあります。
この記事では、白文読解の土台となる白文の句形や基本語彙・重要語、そして文のニュアンスを掴むヒントになる置字といった基礎知識から、具体的な白文の勉強法まで、段階的かつ網羅的に解説します
。最終的には、簡単な練習問題を通じて白文に訓点をつけるスキルを養い、自力で白文で読めるようになり、スラスラと白文の書き下し文を作成できるようになることを目指します。
漢文の白文とは?基本的な読み方を解説
漢文と白文の根本的な違いとは

漢文の学習を効率的に進めるためには、まず「漢文」と「白文」という言葉がそれぞれ何を指しているのかを正確に理解することが不可欠です。この二つの違いを明確にすることで、学習の目的意識がはっきりします。端的に言えば、白文は「漢文のありのままの原文」そのものを指す言葉です。
つまり、返り点(レ点、一二点など)や送り仮名、句読点といった、日本人が読みやすくするために後から付け加えられた補助的な記号が一切ついていない、純粋な漢字だけの文章が白文にあたります。言うまでもなく、古代中国で書かれた文章は、当然ながらこの形で存在していました。
それに対して、私たちが学校の授業などで普段「漢文」として学んでいる文章の多くは、この白文に日本人が読み解くための工夫である「訓点(くんてん)」を加えた「訓読文(くんどくぶん)」です。
歴史を遡ると、古代の日本人は中国語を外国語としてそのまま習得する道を選ぶのではなく、漢文を日本語の文法ルールに巧みに当てはめて読むという、世界でも類を見ない独自の方法を編み出しました。その画期的な発明品が、返り点をはじめとする訓点なのです。
漢文の3つの状態とその関係
漢文の学習では、この3つの状態を自由に行き来できる能力が求められます。
| 種類 | 特徴 | 役割・位置づけ | 例(春暁) |
|---|---|---|---|
| 白文 | 訓点などが一切ない、漢字のみで書かれた原文。 | 全ての基本となるスタート地点。最終的に読み解くべき対象。 | 春眠不覚暁 |
| 訓読文 | 白文に返り点や送り仮名などの訓点を付けたもの。 | 白文を日本語として読むための「設計図」や「指示書」。 | 春眠不レ覚レ暁 |
| 書き下し文 | 訓読文の指示に従い、日本語の語順と文法で記したもの。 | 読解の完成形。文の意味を理解するための日本語訳。 | 春眠暁を覚えず |
このように、学習のスタート地点である「白文」を正しく分析し、その構造を読み解くスキルこそが、漢文全体の理解度を飛躍的に向上させるための根幹となります。
返り点についてはこちらの記事にまとめています。

白文から書き下し文への変換方法

白文を書き下し文に変換する一連のプロセスは、初学者にとっては複雑で、まるで難解なパズルを解いているように感じられるかもしれません。しかし、その本質は「外国語の文章を、文法ルールに従って日本語に翻訳する作業」と捉えると、非常に論理的で分かりやすくなります。
変換の主なステップは、「文の構造を正確に分析し、必要な訓点を付け、最終的に日本語の自然な語順に並べ替える」という3段階の流れです。この手順が必要な根本的な理由は、前述の通り、漢文(古代中国語)と日本語では、文法の根幹をなす語順が決定的に異なるからです。
ここで、非常にシンプルな「登山」という白文を例に、具体的な変換プロセスを見ていきましょう。
変換プロセスの具体例:「登山」
- ステップ1:文構造の分析
まず、各漢字の役割(品詞)を特定します。「登」は「のぼる」という動作を表す動詞、「山」はその動作の対象となる目的語です。そして、漢文では原則として「動詞+目的語」という語順で単語が並びます。 - ステップ2:訓点を付ける
次に、これを日本語に直してみます。日本語では「山に登る」となり、目的語が動詞の前に来るため、語順が完全に逆転します。この語順の逆転を指示するために、下の字からすぐ上の字へ返って読むことを示す「レ点」を、「登」の左下に小さく付けます。これにより、「登レ山」という訓読文が完成します。 - ステップ3:書き下し文にする
最後に、訓点の指示に従って、下の「山」から読み始め、次に「登」へと返って読みます。その際、日本語として自然な文章になるよう、助詞の「に」や動詞の活用語尾「る」を補い、「山に登る」という書き下し文が完成します。
この一見単純な変換作業に慣れることが、白文読解の最も重要な基礎トレーニングです。最初は簡単な文章からで全く問題ありませんので、一つひとつの漢字が文中でどのような役割を果たしているのか(動詞なのか、目的語なのか、それとも主語なのか)を常に意識する癖をつけましょう。
もちろん、文章が長くなると、レ点だけでなく一二点や上下点といった、より複雑な返り点が登場します。しかし、基本的な考え方は全く同じです。つまり、どんなに複雑な文章であっても、その文構造を正しく把握し、各単語の役割を特定できれば、ルールに従って必ず書き下し文は作れるのです。
英語の文構造と漢文の語順
「漢文の語順がどうしても掴めない」と感じる方に、ぜひ試していただきたい画期的なアプローチがあります。それは「英語の文構造(SVO)で考える」という視点です。信じられないかもしれませんが、漢文の基本的な語順は、私たちが慣れ親しんだ日本語(SOV)よりも、むしろ英語(SVO)に非常に近いという驚くべき特徴があるのです。
語順の比較:漢文・英語 vs 日本語
- 漢文・英語:S(主語)→ V(動詞)→ O(目的語) の順で並ぶのが基本。
- 日本語:S(主語)→ O(目的語)→ V(動詞) の順で並ぶのが基本。
この違いを理解するために、有名な「我読書」という白文を例に考えてみましょう。
この文を英語のSVOに当てはめてみると、驚くほど綺麗に一致します。
- S (Subject / 主語):我 (I)
- V (Verb / 動詞):読 (read)
- O (Object / 目的語):書 (books)
このように、「I read books.」という英文と語順がほぼ完全に一致していることがわかります。一方で、これを日本語の書き下し文にすると「我書を読む」となり、目的語「書を」と動詞「読む」が入れ替わる、典型的な日本語のSOV構造になるのです。
漢文読解におけるSVOアプローチの注意点
もちろん、全ての漢文がこのような単純なSVOで完璧に説明できるわけではありません。しかし、「まず文の主語を探し、次にその主語が行う動作(動詞)を見つける」という、英語長文読解で培った基本的な姿勢は、漢文の骨格を掴む上で非常に有効な武器となります。
そして、あの複雑な返り点とは、このSVOの語順を日本語のSOVに変換するための、いわば「語順入れ替えの指示記号」なのだと考えると、その役割がより明確に理解できるはずです。
白文を目の前にして何をすべきか分からなくなったときは、まず「この文の動詞(述語)はどの漢字か?」と考えることから始めてみてください。動詞が見つかれば、その前にあるのが主語、そして後ろにあるのが目的語や補語である可能性が高いと、論理的に推測することができるようになります。
意味を左右する白文の句形
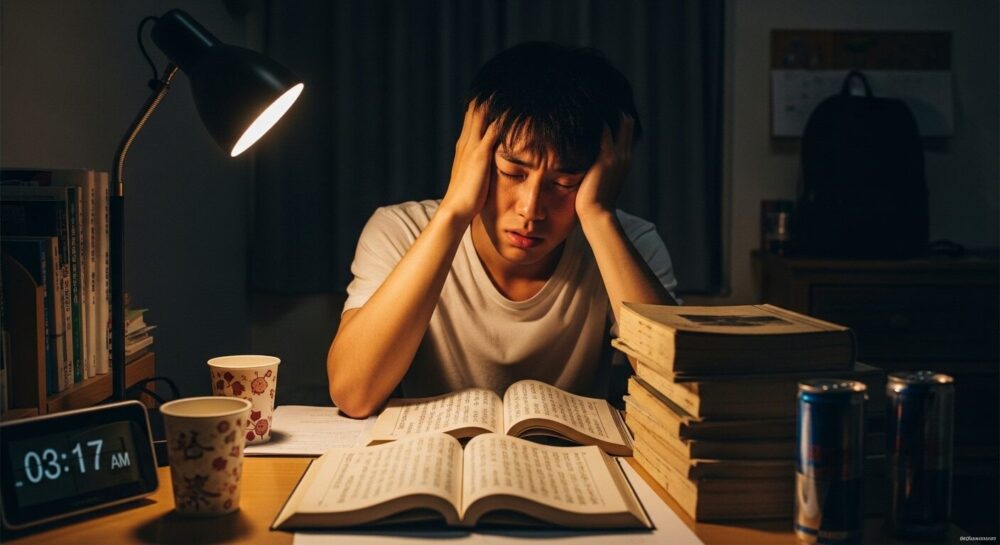
個々の単語の意味はなんとなく分かるのに、文全体の意味が掴めないという場合、その原因の多くは「句形(くけい)」の知識不足にあります。句形とは、簡単に言えば、文の基本的な構造や意味の方向性(否定・疑問など)を決定づける、一種の「決まり文句」や「文法公式」のようなものです。これを覚えていないと、たとえ全ての単語の意味を知っていても、正確な読解は極めて難しくなります。
句形には、否定、疑問、反語、使役、受身、仮定、限定など、様々な種類が存在します。ここでは、特に重要で頻出のものをいくつか具体的に紹介します。
最重要句形の例
否定形:「不」「非」「無」
最も基本的な句形で、「〜ず」と読み、単純な否定を表します。例えば「不読」は「読まず(よまず)」となります。
詳しくはこちらの記事にまとめています。

疑問形:「何」「誰」「安」
「なんぞ」「たれか」「いづくんぞ」などと読み、文字通り疑問を表します。文末が「〜か」のように連体形で終わることが多いのが特徴です。
詳しくはこちらの記事にまとめています。

反語形:「何不」「不亦」
「なんぞ〜ざる」「また〜ずや」といった形で現れます。見た目は疑問形ですが、その意図は「どうして〜ないのか、いや〜だ」という強い肯定や感動を表します。共通テストなどでも頻繁に問われる重要句形です。
再読文字
特に注意が必要なのが、一度目を副詞的に読み、返り点をまたいで二度目を助動詞や動詞として読む特殊な文字群「再読文字」です。これらは白文読解において、文構造を特定するための大きなヒントとなります。
| 再読文字 | 読み方(一度目 → 二度目) | 基本的な意味 | 例文(書き下し文) |
|---|---|---|---|
| 未 | いまだ → 〜ず | まだ〜ない | 未だ来たらず。(まだ来ていない) |
| 将 | まさに → 〜んとす | 今にも〜しようとする/〜するつもりだ | 将に日没せんとす。(今にも日が暮れそうだ) |
| 当 | まさに → 〜べし | 〜べきだ(当然)/きっと〜だろう(推量) | 当に故郷を思ふべし。(当然故郷を思うべきだ) |
| 宜 | よろしく → 〜べし | 〜するのがよい | 宜しく之を断つべし。(これを断つのがよい) |
白文の中にこれらの文字を見つけた瞬間に、「これは再読文字だから、必ず二回読む複雑な構造になるな」と予測できるようになることが理想です。
再読文字はこちらの記事に詳しくまとめています。

句形は基本的に暗記が中心となりますが、ただ丸暗記するのではなく、多くの例文に触れることで、その使い方を身体で覚えていくことが重要です。
読解の補助となる置字の知識

白文を読んでいると、書き下し文にする際には読まない、あるいは送り仮名の中に溶け込んでしまう漢字が登場します。これを「置字(おきじ)」と呼びます。「読まない字」と聞くと、無視してよいもののように感じてしまうかもしれませんが、それは大きな間違いです。実は、置字は文の構造や論理関係、筆者のニュアンスを示す上で非常に重要な役割を担っています。
置字は、主に文頭、文中、文末に置かれ、現代語の接続詞や前置詞、助詞、あるいは文末の終助詞のような多彩な働きをします。代表的な置字とその役割をあらかじめ覚えておくと、読解が格段にスムーズになります。
主な置字の役割と働き
- 而 (而して、而も):文中や文頭に置かれ、前の内容と後の内容を繋ぎます。文脈によって順接(そして、〜して)や逆接(しかし、〜けれども)の関係を示します。
- 於・于・乎 (に、を、より):場所(〜で)、時間(〜の時に)、対象(〜に)、比較(〜よりも)、受身(〜に〜される)など、非常に多くの意味を表します。英語で言えば at, in, from, than といった前置詞の働きを一手に引き受ける便利な文字です。
- 矣・焉 (や、かな):主に文末に置かれ、断定(〜である)や詠嘆(〜だなあ)といった、文を締めくくる強い気持ちを表します。
- 兮(けい):主に『楚辞』など、古代の詩の中で句の調子を整えるために使われる特殊な置字です。
例えば、「学びて思はざれば則ち罔し(まなびておもわざればすなわちくらし)」という『論語』の有名な一節を白文で書くと「学而弗思則罔」となります。この中の「而」が置字です。書き下し文では「学んで」のように、「て」という送り仮名にその機能が吸収されていますが、原文では「学ぶこと、そして考えること」という順接の関係を明確に示しているのです。
白文を読んでいて文のつながりや関係性が見えにくいと感じたとき、これらの置字が非常に重要なヒントになることが多々あります。「この『於』は場所を示しているから、次は地名が来るだろう」「文末に『矣』があるから、これは筆者の断定的な主張だな」といったように、置字から文の構造を予測できるようになると、読解の精度とスピードが飛躍的に向上します。
漢文の白文の読み方を攻略する勉強法
効果的な白文の勉強法を紹介
白文を自力で読めるようになるためには、ただ闇雲に問題と格闘するのではなく、段階的かつ戦略的な学習法を実践することが不可欠です。ここでは、多くの受験生が成果を出している、知識のインプットとアウトプットを効率的に組み合わせた、王道ともいえる勉強サイクルを紹介します。
白文攻略のための4ステップ・スパイラル学習法
- 【ステップ1:インプット期】句形・語彙の高速暗記
まずは、信頼できる参考書や単語帳を一冊用意し、そこに載っている基本的な句形と重要語の意味・読み方を覚えます。この段階で大切なのは、完璧主義に陥らないことです。全てを100%暗記しようとせず、まずは高速で全体に目を通し、「こういうものがあるのか」と全体像を掴むことを目標にしましょう。 - 【ステップ2:分析期】教科書の例文で構造を徹底解剖
次に、訓点がすでに付いている学校の教科書や、丁寧な解説付きの参考書の文章を使って、覚えた知識が実際の文でどのように機能しているかを確認します。「なぜここにレ点が付くのだろう?」「ああ、これはSVO構造だからだ」あるいは「この『将』は再読文字だから、こういう読み順になるのか」と、一つひとつ自分の頭で考え、分析しながら読む練習をします。 - 【ステップ3:アウトプット期】訓点付けと書き下しで実践
基礎知識が頭に入り、分析の視点が養われたら、いよいよ白文から訓点を付け、書き下し文を自力で作成する練習に入ります。最初は解答をすぐに見ても構いません。大切なのは、自力で文構造を判断し、「なぜその訓点になるのか」を他人に説明できるレベルまで理解を深めるトレーニングを積むことです。 - 【ステップ4:定着期】音読による反復練習で身体化
最後に、完成した書き下し文を何度も音読します。黙読だけでなく、実際に声に出して読むことで、漢文特有のリズムや語順がスムーズに身体に染み付きます。これにより、試験本番での速読力と、理屈を超えた直感的な読解力が飛躍的に向上します。
この4つのステップを「インプット→分析→アウトプット→定着」というサイクルで、螺旋階段を上るように繰り返すことが、白文読解マスターへの一番の近道です。特に、インプットした知識をその日のうちにアウトプットで試すことを強く意識してください。知識が使える「スキル」へと変わる瞬間を、きっと実感できるはずです。
基本語彙と重要語は必ず暗記

英語の長文を読むために英単語の暗記が欠かせないのと全く同じで、漢文の白文を正確に読み解くためには、基本語彙と重要語の知識が絶対的な土台となります。「漢字なのだから、現代日本語の意味から推測できるだろう」と安易に考えるのは非常に危険です。
なぜなら、現代日本語とは全く異なる意味で使われたり、文中での位置によって品詞(働き)ががらりと変わったりする単語が、驚くほど多いからです。
例えば、以下の単語は大学入試でも頻繁にその意味や用法が問われる、特に注意が必要な重要語です。
複数の意味・働きを持つ最重要語の例
| 重要語 | 主な品詞 | 読み方 | 意味 | 用例 |
|---|---|---|---|---|
| 故 | 名詞 | ふるき | 古いこと、昔なじみ | 温故知新 |
| 接続詞 | ゆゑ(に) | だから、そういうわけで | 故郷 | |
| 之 | 助詞 | の | 〜の(所有・所属) | 漁夫之利 |
| 代名詞 | これ(を) | これ(目的語) | 送孟浩然之広陵 | |
| 動詞 | ゆ(く) | 行く | 適于之楚 | |
| 与 | 助詞 | と | 〜と(並列) | 我与若 |
| 動詞 | あた(ふ) | 与える | 与民同楽 | |
| 助詞 | か、や | 〜か(疑問・反語) | 燕雀安知鴻鵠之志哉 |
これらの単語の代表的な意味を一つしか知らないと、文全体の解釈を180度誤ってしまう危険性があります。単語を覚える際には、ただ意味を覚えるだけでなく、その単語が持つ主な品詞(動詞、名詞、助詞など)もセットで意識することが、応用力を高める上で極めて重要です。
幸いなことに、漢文で覚えるべき重要単語の数は、英語の数千語に比べれば圧倒的に少ないと言われています。市販されている専用の単語帳などを一冊完璧に仕上げるだけでも、読解力は格段に向上します。頻出語から集中的に覚えていくのが最も効率的な学習法です。
白文に訓点をつける練習をしよう
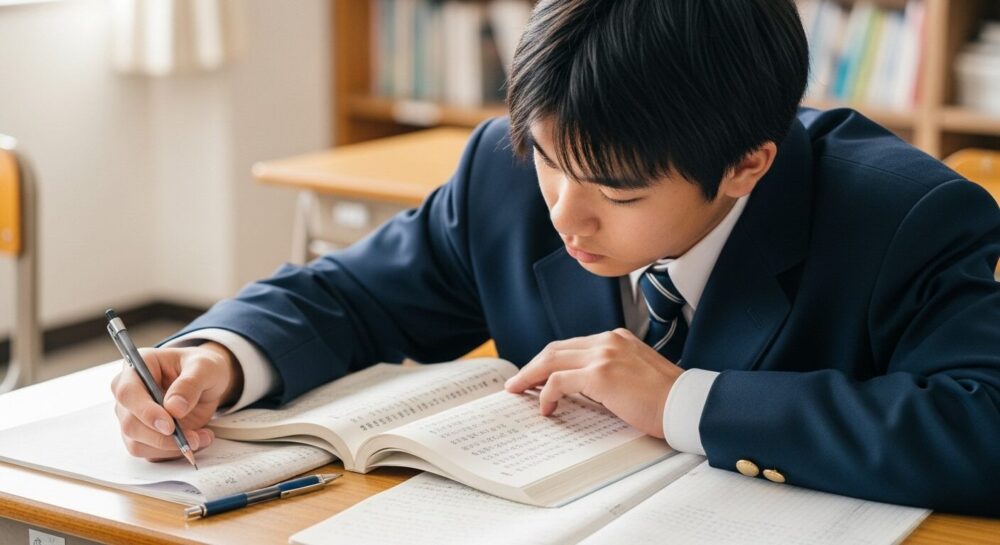
白文の読解力を測り、同時に鍛え上げるための最も実践的なトレーニングが、自分自身の力で白文に訓点をつける練習です。この作業は、決して単なる記号当てパズルではありません。その文の構造、すなわち主語・述語・目的語の関係や、適用されるべき句形のルールを、自分がどれだけ正確に理解しているかを確かめるための、いわば「読解力のアウトプットそのもの」なのです。
いきなり白文だけを見て訓点を付けるのは非常に難易度が高いため、まずは書き下し文がヒントとして与えられている問題から始めるのが定石です。
【訓点付け練習の基本手順】
- 書き下し文を熟読する
まず完成形である日本語の文を注意深く読み、文全体の意味と構造を把握します。ここで句形がある場合はチェックしておく。 - 読む順番を番号で振る
書き下し文で読まれる順番通りに、白文の各漢字の横(または上)に1, 2, 3…と読む順番を数字でメモしていきます。 - 番号の乱れ(逆行)に注目する
番号が上から下へ順番通り(1→2→3…)になっていない箇所、つまり番号が逆行している箇所が、返り点が必要な部分です。 - ルールに従い適切な返り点を付ける
番号の飛び方や範囲に応じて、最も適切な返り点を付けていきます。- すぐ下の漢字からすぐ上の漢字に返る → レ点
- 一字以上を挟んで下の漢字から上の漢字に返る → 一二点
複雑な返り点のルール
文の構造が複雑になり、一二点をまたいで、さらに大きく返る必要がある場合には、上中下点や甲乙丙点が使用されます。基本原則として、「まず範囲の小さな返り(レ点)から付け、次に中くらいの範囲の返り(一二点)、最後に最も範囲の大きな返り(上下点)」という優先順位を覚えておきましょう。これは、数学の計算における括弧の処理(小括弧→中括弧→大括弧)とよく似ています。
この練習を何度も繰り返すことで、単に機械的に返り点を付けるのではなく、「この動詞の目的語は文の後半にあるこの部分だから、ここに二点を打ち、動詞に一点を打つ必要がある」というように、文構造の論理的な分析に基づいて、必然性をもって訓点を導き出せるようになります。
練習問題で白文で読める力を養う
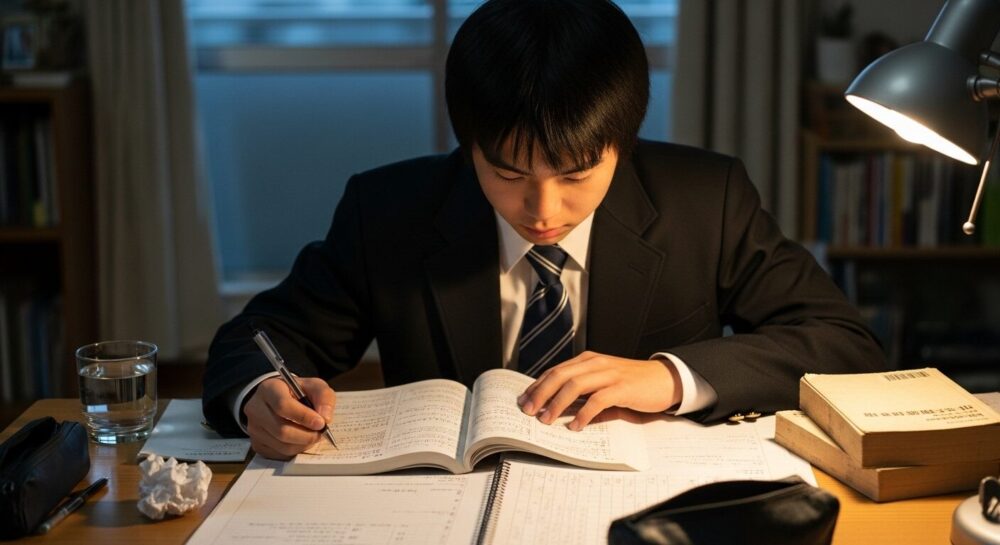
基礎知識をインプットし、訓点付けの反復練習を積んだら、学習の総仕上げとして、実践的な練習問題で自分の実力を試しましょう。実際の入学試験や定期テストで最終的に問われるのは、これまで見たことのない初見の白文を、自分の知識と読解スキルを総動員して読み解く応用力です。多種多様な問題に触れることでしか、その力は養われません。
まずは、構造がシンプルで有名な故事成語から始めてみるのが良いでしょう。
【練習問題】
次の白文に返り点を施し、書き下し文に直しなさい。
問:不入虎穴不得虎子
【考え方のヒント】
- まず文頭と文の中ほどにある「不」の字に注目します。これは否定の句形であり、「〜ず」と読むことが予測できます。
- 前半の「入虎穴」は「虎穴(目的語)に入る(動詞)」、後半の「得虎子」は「虎子(目的語)を得る(動詞)」と、それぞれSVO構造(この場合はVO構造)で読めそうです。
- 日本語では語順が逆になるため、それぞれ「虎穴に入ら」「虎子を得」となり、レ点が必要だと判断できます。
- 前半を仮定(〜しなければ)、後半を結果(〜できない)と解釈し、接続すると自然な文になります。
【解答】
返り点:不レ入二虎穴一不レ得二虎子一
書き下し文:虎穴に入らずんば、虎子を得ず。
このような短い故事成語は、漢文の基本構造が凝縮されており、練習素材として非常に優れています。これに慣れてきたら、独立行政法人大学入試センターが公開している大学入学共通テストの過去問題や、市販されている信頼性の高い問題集に挑戦することをおすすめします。
多くの問題を解くことで、今まで学んできた句形や語彙の知識が、実際の文章の中でどのように立体的に機能しているかを深く体感することができます。そして何より、間違えた問題こそが、あなたの弱点を的確に教えてくれる最高の教材です。なぜ間違えたのか、どの知識が不足していたのかを徹底的に分析し、知識を確実なものへと昇華させていきましょう。
漢文の白文の読み方は練習あるのみ
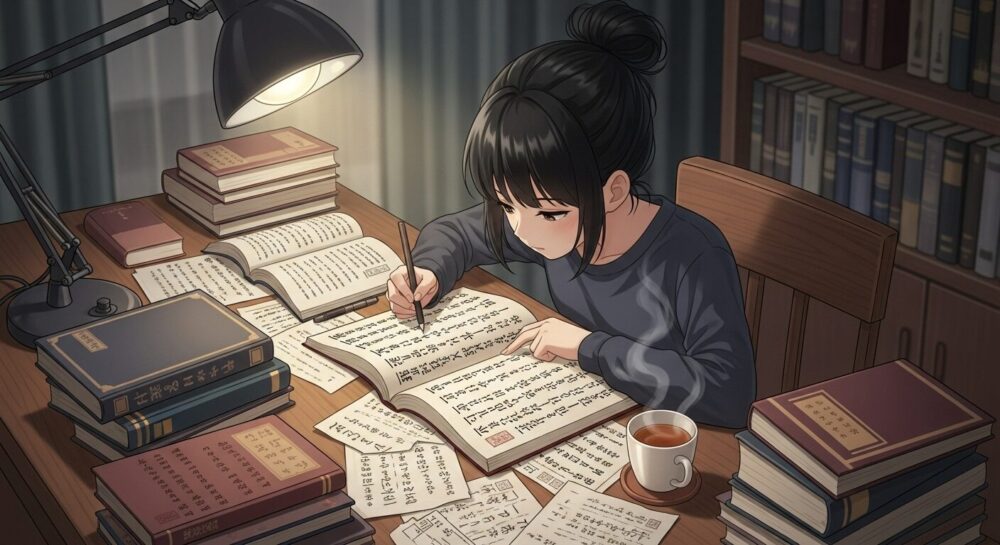
ここまで白文の読み方について、語順の根本的な理解から、句形や語彙の暗記、そして具体的な練習方法に至るまで、様々なテクニックや知識を解説してきました。しかし、最終的に白文を自在にスラスラと読めるようになるために、最も重要かつ不可欠な要素は、結局のところ地道で継続的な練習です。
このプロセスは、スポーツの名選手が毎日素振りを繰り返したり、ピアニストが地道な指の練習を欠かさなかったりするのと本質的に同じです。ルールや理論を頭で理解するだけではスキルは定着せず、何度も何度も反復練習を行うことを通じて、初めて知識が身体に染み込み、無意識レベルで使えるようになるのです。
「毎日漢文の問題を解く時間はない」という方もいるかもしれません。しかし、毎日少しずつでも漢文に触れることは可能です。例えば、通学中の数分間、教科書に載っている漢文を音読するだけでも、絶大な効果があります。実際に声に出して読むことで、漢文独特のリズム感や語順の流れが自然と身体にインプットされ、理屈で考えるよりも先に、直感的に文の構造が掴めるようになってきます。
学習を始めたばかりの頃は、たった数行の白文を読むのに何十分もかかってしまうかもしれません。しかし、そこで決して焦る必要はありません。一つひとつの文章と丁寧に向き合い、「この文の主語はこれで、動詞はこれだ」「ここには反語の句形が使われているな」と、自分の知識を総動員して分析する経験を地道に積み重ねていくうちに、必ずや読解のスピードと精度は劇的に向上していきます。
白文読解は、決して一部の才能ある人にしか乗り越えられない壁ではありません。正しい学習法を信じ、地道な練習を積み重ねれば、誰でも必ず攻略することが可能です。この記事で紹介した方法を道しるべとして、ぜひ粘り強く挑戦を続けてください。
漢文の白文の読み方は練習で身につく
- 白文は返り点や送り仮名などの補助記号が一切ない漢文の原文のこと
- 訓読文は白文に日本人が日本語として読むための訓点を加えたもの
- 書き下し文は訓読文の指示に従って日本語の語順と文法で書いた文章
- 漢文の基本的な語順は英語と同じSVO(主語→動詞→目的語)が中心
- 日本語はSOV(主語→目的語→動詞)であるため語順の転換ルールが必要
- 白文読解ではまず文の核となる動詞を見つけることがポイントになる
- 句形は文の意味や構造を決定づける文法公式のようなもので暗記が必須
- 否定・疑問・反語・使役・受身などの句形は頻出するため確実に覚える
- 再読文字は白文の中で二度読む特別な漢字で文構造の大きなヒントになる
- 置字は書き下し文では読まないが文の接続やニュアンスを示す重要な役割を持つ
- 「而(順接・逆接)」「於(場所・対象)」「矣(断定・詠嘆)」などが代表的な置字
- 効果的な勉強法は知識のインプットと実践的なアウトプットを繰り返すこと
- 現代語と意味が異なる重要語彙の暗記は正確な読解の土台となる
- 自分で白文に訓点をつける練習は文構造の理解度を測る最適なトレーニング
- 多くの練習問題に触れることで初見の文章への対応力が養われる