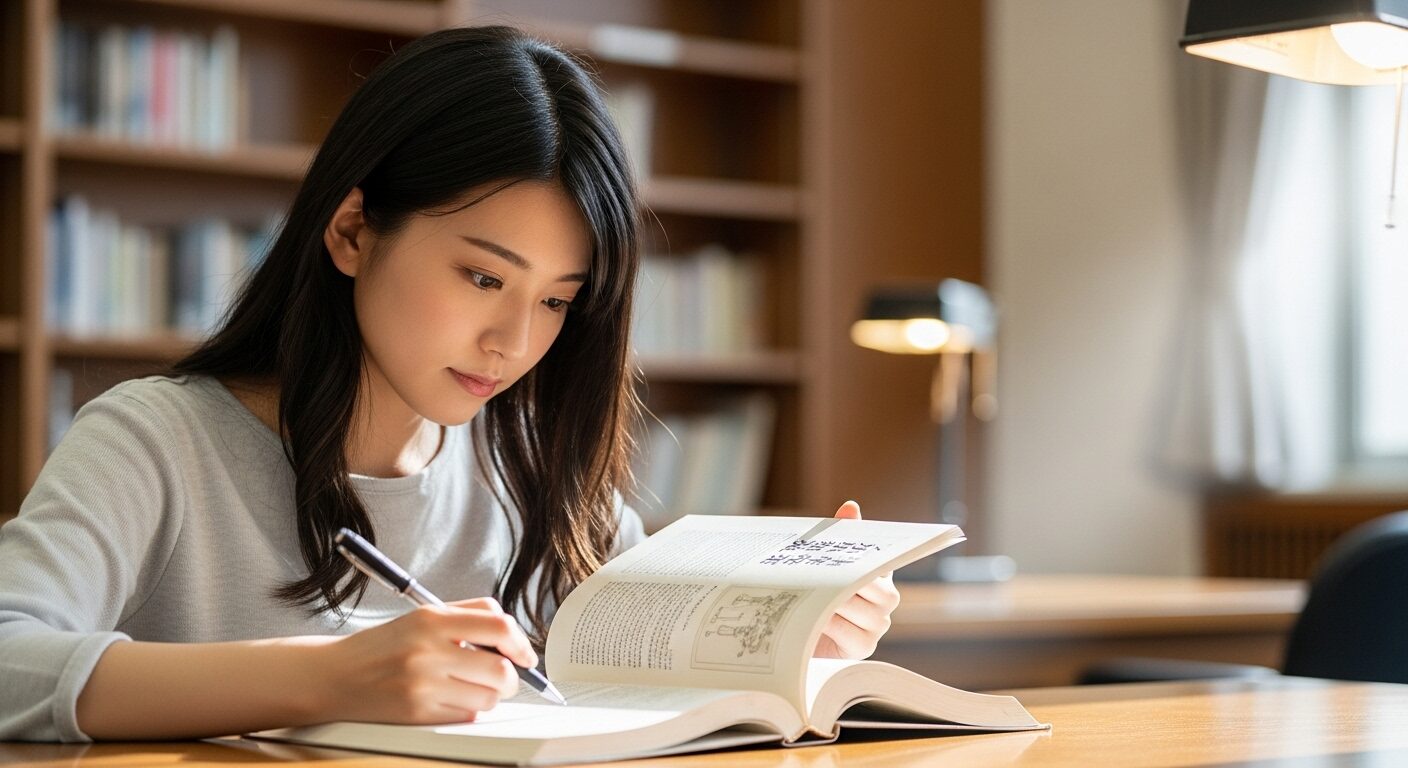古文の助動詞「けむ」「らむ」の簡単な見分け方【完全解説】

「古文の助動詞、特に『けむ』と『らむ』がややこしくて覚えられない…」と悩んでいませんか。古文の学習を進める中で、多くの人がこの二つの助動詞の壁にぶつかります。
活用表の暗記はもちろん、意味や接続のルール、さらには推量と原因推量の見分け方など、混乱しやすいポイントが満載です。特に、伝聞や婉曲といった複数の意味が絡み合ってくると、「一体どの意味で訳せばいいの?」と手が止まってしまいますよね。
さらに、よく似た助動詞「む」との関係性も、理解をさらに難しくさせる一因でしょう。これらの複雑な要素が重なり合うことで苦手意識が生まれ、多くの問題で失点してしまう…そんな悔しい経験をお持ちの方も少なくないはずです。
しかし、ご安心ください。助動詞「けむ」と「らむ」の識別は、決して当てずっぽうで解くものではなく、はっきりとした論理的なコツが存在します。正しい手順と考え方を一つずつ丁寧に身につければ、誰でも迷うことなく正確に見分けることが可能になります。
この記事では、複雑に見える「けむ」と「らむ」の活用、接続、意味、そして識別方法の全てを、体系的に、そしてこれ以上なく分かりやすく解き明かしていきます。この記事を読み終える頃には、あなたの漠然とした不安や苦手意識は、古文読解を楽しむための確かな自信へと変わっているでしょう。
古文の助動詞「けむ」「らむ」の基本を理解する
まずは「けむ」「らむ」の活用表から

何事も、まずは基本の形から押さえることが大切です。急がば回れ、ということわざがあるように、焦っていきなり意味の識別から入るのではなく、土台となる活用を完璧にすることが、結果的に最も効率的な学習法となります。
「けむ」と「らむ」は、一見すると複雑に感じられるかもしれませんが、その活用は非常にシンプル。どちらも動詞の四段活用と全く同じ形で変化するため、「四段型」と呼ばれています。
これは、基本的な推量の助動詞「む」の活用(ま・〇・む・む・め・〇)を既に覚えていれば、それに「け」や「ら」を付けるだけで応用できることを意味します。下の表で、具体的な活用の形をじっくりと確認し、頭に焼き付けましょう。
| 活用形 | らむ | けむ |
|---|---|---|
| 未然形 | ○ | ○ |
| 連用形 | ○ | ○ |
| 終止形 | らむ (らん) | けむ (けん) |
| 連体形 | らむ (らん) | けむ (けん) |
| 已然形 | らめ | けめ |
| 命令形 | ○ | ○ |
この表を見てわかる通り、実際に文章中で活用して使われるのは終止形・連体形・已然形のわずか3つの形だけです。未然形、連用形、命令形は存在しません。これは、「けむ」や「らむ」が文末に来ることが多く、下に他の用言が続くことが少ないためです。覚えるべきことが少ないというのは、学習者にとっては嬉しいポイントですね。また、終止形と連体形が同じ形であることも、シンプルで覚えやすい点と言えるでしょう。
豆知識:発音の変化と表記
時代が下るにつれて、「む」の音が「ん」に変化し、「らむ」は「らん」、「けむ」は「けん」と発音・表記されることが多くなりました。古文を読んでいると両方の表記が出てきますが、これらは完全に同じものだと考えて問題ありません。例えば「~けん」と出てきても、「ああ、『けむ』のことだな」と変換できるようにしておきましょう。
それぞれの助動詞の接続ルール

活用形と並んで絶対に覚えなければならないのが、直前の語にどの活用形を要求するかという「接続」のルールです。ここが「けむ」と「らむ」を区別する上で非常に大きな違いの一つなので、混同しないようにしっかりと区別して覚えましょう。
結論から言うと、接続は以下のようにはっきりと分かれています。
- らむ → 終止形に接続する
- けむ → 連用形に接続する
※ただし、「らむ」はラ変型活用語(「あり」など)には連体形で接続します。
「らむ」は原則として終止形、つまり動詞などの言い切りの形につきます。一方で「けむ」は連用形につきます。この違いを覚えることが、文法問題を解く上でも、長文を正確に読解する上でも極めて重要になります。なぜなら、例えば動詞の活用形を見れば、その下に来るのが「らむ」なのか「けむ」なのかを予測できるからです。
この違いは、それぞれの助動詞の成り立ちと関係があると言われています。「けむ」の「け」は、過去の助動詞「き」や「けり」の「け」と関連が深いと考えられており、それらと同じ連用形接続になった、と覚えておくと忘れにくいです。過去を表す助動詞は連用形に接続することが多い、というルールとも合致します。
覚え方のコツは、「けむの『け』は過去の『けり』の『け』!」と何度も唱えることです。これで「けむ=連用形接続」が定着します。そうすれば、残った「らむ」が終止形接続であると自動的に判断できますね。
ラ変型活用の例外に注意!
「らむ」の接続で唯一注意が必要なのが、ラ行変格活用(ラ変)の動詞「あり」「をり」「はべり」や、形容詞・形容動詞の補助活用(「~くあり」「~にあり」から生まれた形)です。これらの語に「らむ」がつく場合は、終止形「り」ではなく連体形「る」に接続します。これは、「~りらむ」だと発音しにくいため、発音しやすい「~るらむ」という形に変化したためです。
(例)花あり+らむ → 花あるらむ
(例)静かなり+らむ → 静かなるらむ
4つの意味は「すげえで」で暗記しよう

さて、活用の形と接続という土台が固まったところで、いよいよ意味の解説です。「けむ」と「らむ」には、共通して4つの文法的意味が存在します。これを一つ一つ丸暗記しようとすると大変ですが、ここでも非常に便利な語呂合わせがあります。
意味の覚え方は、「す・げ・え・で」と覚えてください!
これはそれぞれの意味の頭文字を取ったもので、驚くほど簡単に4つの意味を思い出すことができます。
- す:推量(現在推量/過去推量)…「~だろう」と物事を推し量る基本的な意味です。
- げ:原因推量(現在の原因推量/過去の原因推量)…「なぜ~だろうか」と物事の原因や理由を推量します。
- え:婉曲(現在の婉曲/過去の婉曲)…「~ような」と断定を避けて、表現を和らげます。
- で:伝聞(現在の伝聞/過去の伝聞)…「~という」「~とかいう」と、人から聞いた話として伝えます。
ここで重要なのは、「らむ」が現在のことについての4つの意味、「けむ」が過去のことについての4つの意味を表す、という点です。つまり、時制が違うだけで、意味のラインナップは同じなのです。まずは基本となる「推量」の意味さえしっかり押さえれば、あとは時制が過去になるだけ、あるいは少しニュアンスが変わるだけ、と考えれば、一気に理解しやすくなるはずです。
似ている「む」「らむ」「けむ」の関係を整理

古文には「む」「らむ」「けむ」という、発音も意味もよく似た推量の助動詞が3つあります。これらは「推量の三兄弟」とも呼ばれ、話し手がどの時点(時制)の事柄について推量しているかによって使い分けられます。この三者の関係性をはっきりと理解することが、正確な読解への最後の近道です。
それぞれの担当する時制と基本的な意味を、以下の表で比較しながら整理しましょう。
| 助動詞 | 担当する時制 | 話し手の心の向き | 基本的な意味 | 接続 |
|---|---|---|---|---|
| む | 未来・現在(一般的な推量) | これから起こること、一般的なこと | ~だろう、~よう | 未然形 |
| らむ | 現在(目の前にない事柄) | 今、ここではないどこかで起こっていること | (今ごろ)~ているだろう | 終止形 |
| けむ | 過去 | すでに過ぎ去った過去のこと | ~ただろう | 連用形 |
このように、単純に「(これから)~だろう」と未来や現在のことを一般的に推量するのが「む」です(※「む」には意志や勧誘など他の意味も多数あります)。
それに対して、「今ごろ、遠い故郷では雪が降っているだろう」のように、自分の目には見えない現在の状況を、まるで目の前にあるかのようにありありと想像するのが「らむ」です。
そして、「千年前の人々は、どんな暮らしをしていたのだろう」のように、自分が体験していない過ぎ去った過去の出来事に思いを馳せるのが「けむ」なのです。
この「話し手の心の向き」という時制のイメージと、前の見出しで確認した「接続」の違いをセットで完璧に覚えておけば、この三兄弟を混同することはなくなり、読解の精度が格段に向上するでしょう。
古文の助動詞「けむ」「らむ」の識別方法をマスター
意味の識別はフローチャートで考えよう

4つの意味を覚えたら、いよいよこの記事の核心である「見分け方」です。実際の文章中で出会ったとき、どの意味で訳すべきか迷うことは多いでしょう。そんなとき、闇雲に全ての可能性を試すのではなく、決まった手順でチェックしていくのが、最も速く、そして正確に正解へたどり着くための方法です。
以下のフローチャートのような思考プロセスを常に意識してください。これは、複雑な情報を整理し、論理的に答えを導き出すための強力な武器となります。
「けむ」「らむ」識別フローチャート
- 【位置の確認】まず、文のどこにあるかをチェックする(文中か、文末か)。これで可能性を大きく2つに絞る。
- 【周辺の確認】文末にある場合、疑問語(など、いかで、や、か等)が近くにあるかチェックする。
- 【状況の確認】推量している事柄が、話し手にとって目の前の事実かどうかを文脈から判断する。
- 【最終判断】全ての可能性を検討し、最も文脈に合う自然な訳を選ぶ。機械的に判断せず、必ず訳して確認する。
この流れは、いわば「名探偵の捜査手順」のようなものです。まずは大まかな状況証拠(位置)で容疑者を絞り込み、次に具体的な物証(周辺の語)や状況証拠(文脈)を集めて犯人(正しい意味)を特定していく。この思考の型を身につければ、どんな難問にも冷静に対処できるようになります。次の項目から、この手順に沿って具体的な見分け方を一つずつ詳しく見ていきましょう。
文中か文末かで見分ける第一歩

意味を識別するための最初の、そして最も重要なステップは、「けむ」や「らむ」が文のどの位置に登場しているかを確認することです。文の途中にあるのか、それとも文の最後にあるのか。これを確認するだけで、4つあった意味の可能性を一気に2つまで絞り込むことができます。これは識別作業における最大のショートカットと言えるでしょう。
文中にある場合 → 伝聞・婉曲
「けむ」や「らむ」が読点「、」や名詞(体言)の前など、明らかに文の途中に置かれている場合、その意味はほとんどのケースで伝聞または婉曲になります。これらの意味は、文の主要な述語としてではなく、下の語句を修飾するような形で機能するため、文中に現れやすいのです。
(例)向かひゐたりけむありさま、さこそ異様なりけめ。
(訳)(医者と)向かい合っていたような有様は、さぞかし奇妙であっただろう。
この例文では、「けむ」は文末ではなく、直後に「ありさま(有様)」という名詞が続いています。このような形を見たら、即座に「伝聞か婉曲だな」と判断できるようになりましょう。
文末にある場合 → 推量・原因推量
一方、「けむ」や「らむ」が文末(または引用の「と」の前など、文の結びとなる位置)にある場合は、その基本的な意味である推量または原因推量のどちらかになります。
(例)雲のいづこに月宿るらむ
(訳)(今ごろ)雲のどこに月が宿っているのだろう。
この例文では、「らむ」が和歌の最後に置かれ、文を締めくくっています。このような場合は、まず基本的な推量の意味を考えて訳してみるのが定石です。
例外中の例外:挿入句に注意
『源氏物語』などの物語文学で頻出する「~にやありけむ」という表現は、形式上は文中にありますが、これは筆者の感想や推測が括弧でくくられるように差し込まれた「挿入句」と見なされます。そのため、婉曲や伝聞ではなく、文脈から独立した過去推量(~だったのだろうか)で訳します。これは例外的な用法として、形ごと覚えてしまうのが得策です。
推量と原因推量の見分け方のポイント
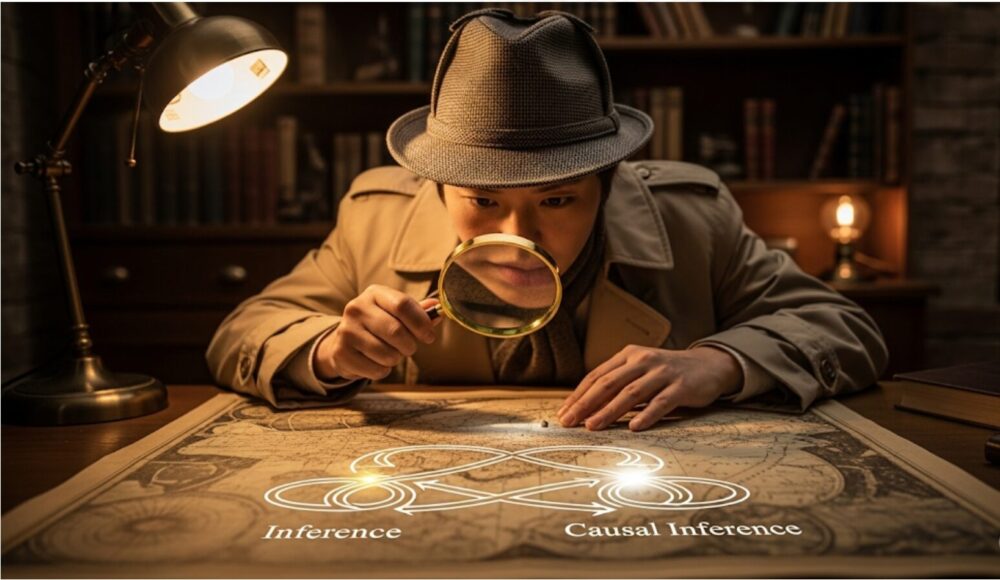
文末にある場合、「推量」と「原因推量」のどちらで訳すかが次の重要な課題となります。この二つの見分け方は、推量の対象が話し手にとって「目の前にある事実」なのか、それとも「目の前にない事柄」なのかという点で明確に区別されます。
推量(現在推量・過去推量)【目の前にない事柄】について想像を巡らせます。話し手から空間的・時間的に遠く離れた場所で起こっていること、あるいは起こったことについて、「~だろう」と思いを馳せる用法です。
(例)子泣くらむ → (私が今いない家で、今ごろ)子供が泣いているだろう。(※子供は目の前にいません)
(例)昔、人はかくありけむ → 昔、人はこのようであったのだろう。(※昔の人の様子は目の前にありません) 原因推量(現在の原因推量・過去の原因推量)【目の前にある事実】の理由・原因について、「どうして~なのだろうか」と推量します。話し手が現に見たり聞いたりしている事象について、その背景を探る用法です。
(例)など花散るらむ → (目の前で花が散っているが)どうして花は散るのだろう。(※花が散る様子は目の前にあります)
(例)京や住み憂かりけむ → (あの人が都を捨てて東国へ下ったのは)都が住みづらかったからだろうか。(※都を捨てたという事実の原因を推量しています)
つまり、普通の「推量」は見えない世界への想像力であるのに対し、「原因推量」は見える世界の背後を探る洞察力である、という違いがあります。この話し手の視点の違いを意識することが、正確な読解の鍵となります。
目の前の事実かどうかが鍵

前の項目で説明した「目の前の事実かどうか」という判断基準は、特に短い言葉の中に豊かな情景や心情を詠み込む和歌の解釈において、非常に重要になります。和歌を正しく味わうためには、作者が今、何を見て、何を感じているのかを正確に読み取る必要があるからです。
このポイントを理解するために、百人一首にも選ばれている紀友則の有名な和歌を改めてじっくりと見てみましょう。
ひさかたの光のどけき春の日に しづ心なく花の散るらむ
この歌のクライマックスである「花の散るらむ」は、現在推量でしょうか、それとも原因推量でしょうか。
まず、歌の上旬「光のどけき春の日に」と詠んでいることから、作者は日差しが穏やかな春の日に屋外にいることがわかります。そして、その目の前で、風も吹いていないのに桜の花がはらはらと絶え間なく散っている光景を見ています。つまり、作者にとって「花が散る」という現象は、想像ではなく紛れもない目の前の事実なのです。
目の前の事実に対して「らむ」が使われている。このことから、これは原因推量であると断定できます。「こんなに穏やかな日であるのに、どうして桜の花だけは、落ち着いた心もなく、せわしなく散っていくのだろうか」と、その美しい散り際の理由に思いを巡らせ、不思議に思っているのです。もしこれを現在推量で「(どこかで)花が散っているだろう」と訳してしまうと、歌の感動が半減してしまうことがわかるでしょう。
読解のヒントになるキーワード
文中に「思ひやる(遠く離れた人や場所を想像する)」といった動詞があれば、それは目の前にないことを考えている強力な証拠なので「推量」の可能性が非常に高まります。逆に「見ゆ(見える)」や、五感で感じていることを示す描写があれば、目の前の事実なので「原因推量」を考える大きなヒントになります。
伝聞と婉曲の見分け方は「+体言」

次に、文中で使われる「伝聞」と「婉曲」の見分け方についても、さらに詳しく確認しておきましょう。先述の通り、文中に「けむ」「らむ」が出てきた場合、そのほとんどがこの二つのどちらかの意味になります。
見分ける最大のポイントは、「けむ」「らむ」が連体形になって、その下に名詞(体言)が続いているという形です。この形は「連体修飾語」として機能していることを示しており、伝聞・婉曲の意味になる典型的なパターンです。
(例)人の言ふらむこと → 人が言うようなこと(婉曲)
(例)翁丸死にけむこそ → 翁丸が死んだということは(伝聞)
「~ような」と訳すのが婉曲で、断定を避けて表現を柔らかくぼかすニュアンスを持ちます。
「~という」「~とかいう」と訳すのが伝聞で、他人から聞いた情報であることを示すニュアンスを持ちます。
どちらで訳すかは最終的に文脈で判断する必要がありますが、経験上、まずは婉曲で訳してみて、意味が通じなければ伝聞を試すという手順で考えると、うまくいくことが多いです。婉曲は日本語のコミュニケーションにおいて非常に多用される表現であり、古文でもその登場頻度は高めだからです。
婉曲は、現代の私たちが「~みたいな感じ」「~っぽいこと」と言うときのニュアンスに近いかもしれません。はっきり言い切らずに、少しぼかして表現を和らげる。この感覚がわかると、古文の世界がより身近に感じられますよ。
練習問題で理解度をチェック

ここまでの知識がしっかりと身についたか、実際の入試問題でも問われるレベルの例文で力試しをしてみましょう。それぞれの傍線部の「らむ」「けむ」の意味として最も適当なものを一つ選んでください。じっくり考えて、これまで学んだ識別フローチャートを実践してみましょう。
練習問題
問1. 憶良らは今はまからむ子泣くらむそれその母も我を待つらむそ
- 現在推量
- 原因推量
- 婉曲
問2. いかなるゆゑか侍りけむ。
- 過去推量
- 過去の原因推量
- 過去の伝聞
問3. 唐土の人は、これをいみじと思へばこそ、記しとどめて世に伝へけめ、~。
- 過去推量
- 過去の原因推量
- 過去の婉曲
解答と解説
問1. 解答:1. 現在推量
これは『万葉集』の山上憶良の歌で、宴席から家に帰ろうとする作者が、家で待つ家族の様子を想像している場面です。宴席にいる作者にとって、家で「子が泣いている」様子は目の前の事実ではありません。遠く離れた場所の現在の状況を推量しているので、正解は現在推量となります。
問2. 解答:2. 過去の原因推量
これは非常に分かりやすい例です。文頭に「いかなるゆゑか(どのような理由で)」という明確な疑問語があります。このように、疑問語(など・なに・いかで・や・か)とセットで使われる「けむ」は、原因推量になる典型的なパターンです。「どのような理由があったのだろうか」と、過去の事柄の原因を問うています。
問3. 解答:2. 過去の原因推量
文末が已然形「けめ」で終わっている点に注目します。これは係り結びではなく、下に逆接の接続助詞「ど」や「ども」が省略されていると考えられます。「唐土の人がこれをすばらしいと思ったからこそ、書き留めて世に伝えたのだろうけれども…」という文脈です。「書き留めて伝えた」という過去の事実の理由を「すばらしいと思ったから」と推量しているため、原因推量と判断できます。「~ばこそ、~けめ」という形も、原因推量を示す重要なパターンのひとつです。
古文の助動詞「けむ」「らむ」は訳で最終確認
この記事では、多くの受験生を悩ませる助動詞「けむ」と「らむ」について、その活用の基本から、意味の覚え方、そして最も重要な識別方法について、段階を踏んで詳しく解説してきました。最後に、この記事で学んだ最も重要なポイントを、復習しやすいようにリスト形式でまとめます。これらのポイントを定期的に見返し、ご自身の知識として定着させることで、今後の学習や実際の試験で必ず役立つはずです。
- 「けむ」「らむ」の活用は、どちらも動詞の四段活用と同じ「四段型」である
- 接続は明確に異なり、「らむ」が終止形接続、「けむ」が連用形接続と覚える
- 「けむ」の「け」は過去の「けり」の「け」と関連付け、連用形接続と記憶すると忘れにくい
- 4つの意味は「すげえで」(推量・原因推量・婉曲・伝聞)の語呂合わせで暗記する
- 推量の三兄弟「む・らむ・けむ」は、それぞれ「未来・現在・過去」という時制を担当する
- 意味の識別の第一歩は、文中にあるか文末にあるかという「位置」を確認すること
- 文中にあれば、下に続く語を修飾する「婉曲」または「伝聞」の可能性が極めて高い
- 文末にあれば、文を締めくくる「推量」または「原因推量」の可能性が高い
- 「推量」と「原因推量」の決定的な違いは、推量の対象が「目の前の事実」かどうか
- 話し手の視界にない事柄を想像するのが「推量」
- 話し手の視界にある事実の理由を探るのが「原因推量」
- 文中に疑問語(など・いかで・や・か)があれば、「原因推量」を強く示唆するサイン
- 「婉曲」と「伝聞」は、下に名詞(体言)を伴う連体修飾の形を取ることが多い
- まずは万能な「婉曲(~ような)」で訳してみて、不自然なら「伝聞(~という)」を検討する
- これまで述べた識別法はあくまで強力な手がかりであり、100%のルールではない
- 最終的には、必ず文脈に当てはめてみて、最も自然で意味の通る訳を選択するという「訳での確認作業」を怠らないことが最も重要である
古文の勉強法、お疲れ様でした!
「よし、やるぞ!」と思っても、「でも、文法をゼロから体系的にやり直すのって、独学だと不安だなぁ…」と感じていませんか?
もし、あなたが「元・古文が苦手」だった先生から、センスに頼らない「論理的な解き方」を学びたいなら…
今、多くの受験生から「神授業」と呼ばれている「スタディサプリ 古文」を、私が徹底的に分析した記事がきっと役立つはずです。
なぜ岡本先生の授業がそこまで支持されるのか、ゼロから始める具体的な受講順番まで詳しく解説しています。
古文を「苦手」から「得意」に変える、その具体的な方法に興味がある方は、ぜひ覗いてみてくださいね。
→ 関連記事:スタディサプリ古文が神授業と言われる理由|ゼロから始める最適ルートも解説
この記事を読んで、古文の理解がまた一つ深まりましたね。
でも、古文は「単語」「文法」「読解」「常識」など、全ての知識が有機的につながって初めて高得点が取れる科目です。
「次はどこを勉強すればいいの?」
「苦手なあの分野、どうやって対策しよう?」
そんな迷子にならないよう、ミチプラス内の古文記事を「勉強する順番」に整理した「完全攻略マップ」を作成しました。
辞書代わりにブックマークして、最短ルートで志望校合格を目指しましょう!