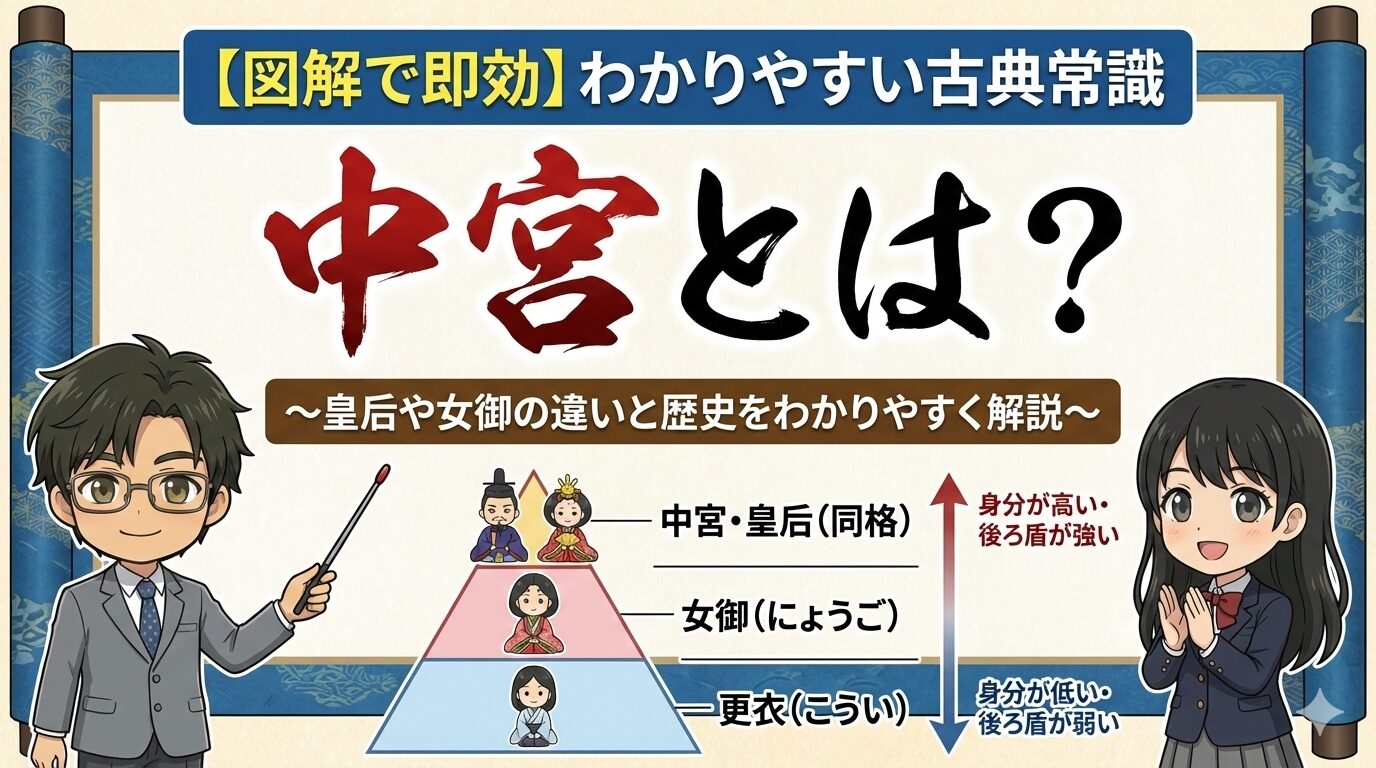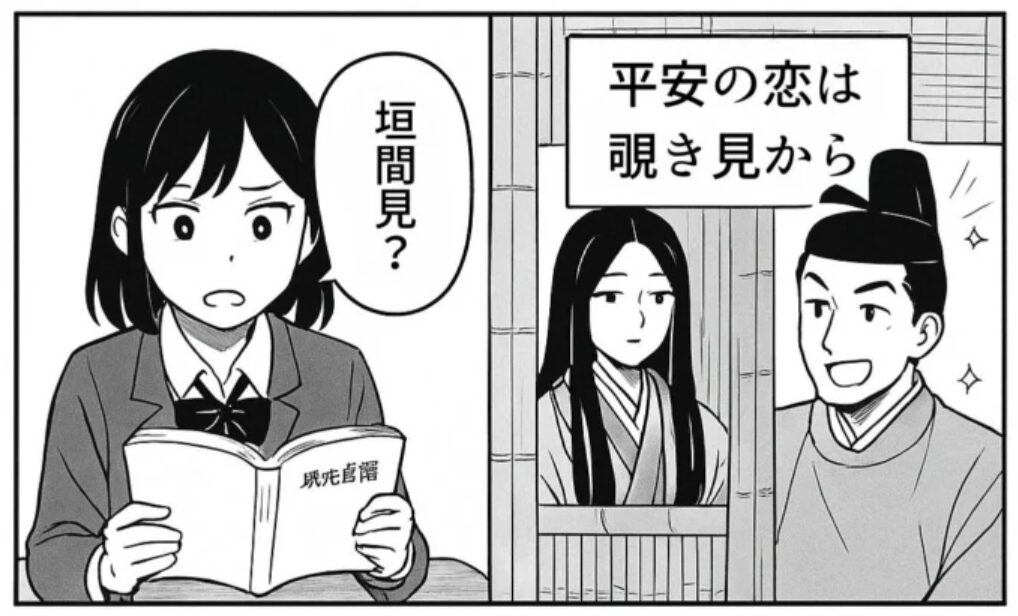古文の助動詞「まじ」と「じ」を完全攻略!意味や違いは?

古文の世界へようこそ。数ある文法項目の中でも、多くの学習者が「難しい」「見分けがつかない」と感じるのが、助動詞の「まじ」と「じ」ではないでしょうか。形が似ている上に、どちらも否定的な意味を持つため、品詞分解の際につい手が止まってしまったり、テストで失点してしまったりするケースは少なくありません。しかし、ご安心ください。これらの助動詞は、ある特定の関係性さえ理解してしまえば、驚くほどクリアに識別できるようになります。
この記事では、古文の助動詞「まじ」と「じ」について、単なる丸暗記ではない、本質的な理解を目指します。それぞれの意味、活用、接続のルールはもちろんのこと、なぜそうなるのかという背景にある「む」と「じ」の関係や、「べし」と「まじ」の関係といった文法システムそのものに光を当てていきます。
さらに、記憶を助ける効率的な覚え方や語呂合わせ、そして知識を本物の応用力に変えるための実践的な問題まで、網羅的に解説します。この記事を最後まで読み終える頃には、これまで曖昧だった知識が一本の線でつながり、自信を持って古文を読み解くための一生の武器を手にしていることでしょう。
古文の助動詞「まじ」と「じ」の基本を解説
助動詞「まじ」と「じ」が持つ意味
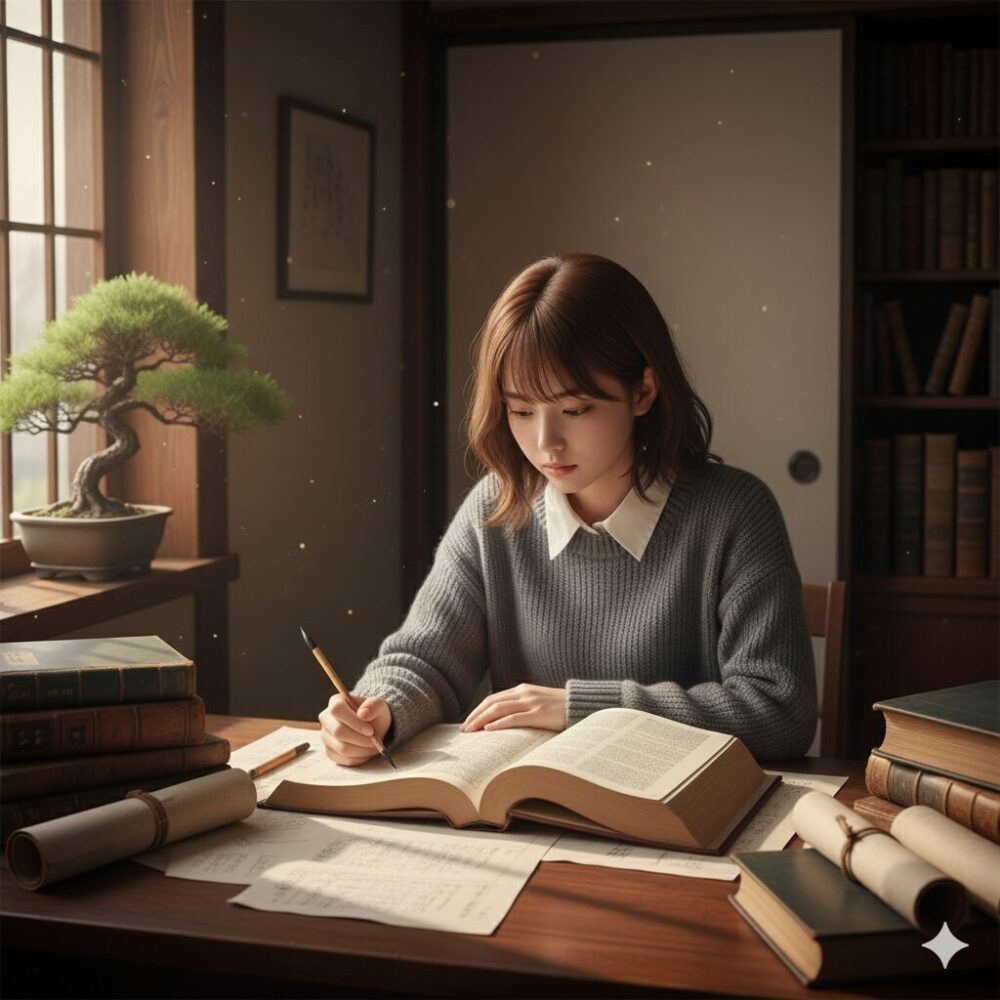
古文における助動詞「じ」と「まじ」は、どちらも打消(否定)のニュアンスを持つ点で共通していますが、その意味の範囲や強さには明確な違いが存在します。この違いを理解するための最大の鍵は、それぞれの助動詞がどの肯定形の助動詞に対応しているかを知ることにあります。結論から言うと、「じ」は助動詞「む」の打消しであり、「まじ」は助動詞「べし」の打消しです。この基本原則を念頭に置きながら、それぞれの具体的な意味を見ていきましょう。
助動詞「じ」の意味
助動詞「じ」は、推量の助動詞「む」が持つ中心的な意味である「推量」と「意志」を、そのまま打ち消した意味を表します。そのため、文法的な意味は以下の2つに絞られ、比較的シンプルです。
- 打消推量(~ないだろう):ある事柄について、そうはならないだろう、そうであるまいと否定的に推量する意味を表します。物語の地の文など、客観的な描写でよく見られます。
(例)月ばかりおもしろきものはあらじ。(徒然草) → 月ほど趣深いものはないだろう。 - 打消意志(~ないつもりだ、~まい):話者が「~するつもりはない」「決して~しないぞ」という、自身の行動に対する否定的な意志を示す意味です。会話文や心情を吐露する場面で頻繁に登場します。
(例)今は帰りて、また参り来じ。(竹取物語) → 今は帰って、二度とやって来るつもりはない。
これらの意味は、文の主語に注目することである程度判断できます。主語が三人称(物事や自分以外の人物)であれば「打消推量」、主語が一人称(私・我)であれば「打消意志」となるのが基本的なセオリーです。
助動詞「まじ」の意味
一方、助動詞「まじ」は、より強い推量や多様な意味を持つ助動詞「べし」を打ち消すため、その意味のバリエーションは「じ」よりも格段に豊富になります。「べし」が持つ6つの意味(推量・意志・可能・当然・命令・適当)をすべて否定の形でカバーします。
「べし」と「まじ」の意味対応一覧
「べし」の意味を覚えていれば、「まじ」の意味は自動的に導き出せます。
| 「べし」の意味 | 「まじ」の意味(打消) | 訳し方 | 例文(まじ) |
|---|---|---|---|
| 推量 | 打消推量 | ~ないだろう | 冬枯れの気色こそ、秋にはをさをさ劣るまじけれ。(徒然草) |
| 意志 | 打消意志 | ~するつもりはない | わが身は女なりとも、敵の手にはかかるまじ。(平家物語) |
| 可能 | 不可能 | ~できそうにない | えとどむまじければ、泣きをり。(竹取物語) |
| 当然 | 打消当然 | ~はずがない | 必ずしもあるまじきわざなり。(土佐日記) |
| 命令 | 禁止 | ~してはならない | つかのまも忘るまじきなり。(徒然草) |
| 適当 | 不適当 | ~べきではない | 妻といふものこそ、男の持つまじきものなれ。(徒然草) |
このように、「じ」が単純な打消推量・意志を表すのに対し、「まじ」はそれに加えて「~はずがない」「~してはならない」といった、話者の強い判断や倫理観、規範意識を含む否定を表すことができるのが大きな特徴です。この根本的な違いを理解するためにも、元となる助動詞「む」と「べし」の理解がいかに重要であるかがわかります。
助動詞「まじ」と「じ」の接続ルール

助動詞「じ」と「まじ」を文法的に正確に識別する上で、最も確実な手がかりとなるのが「接続」のルールです。意味が似ていても、直前の活用語がどの活用形になっているかを見れば、どちらの助動詞なのかを明確に区別することができます。
助動詞「じ」の接続
助動詞「じ」は、活用語の未然形に接続します。これは、「まだそうではない」という未然の状態に対する打消の推量や意志を表すため、理にかなったルールと言えます。そして、この接続ルールは、元となる肯定の助動詞「む」と全く同じです。
未然形接続の確認方法
動詞の活用がわからない場合、下に打消の助動詞「ず」を付けてみると未然形がわかります。
- 動詞「言ふ」→言は(ず)→未然形は「言は」。よって「言はじ」
- 動詞「見る」→見(ず)→未然形は「見」。よって「見じ」
- 動詞「す」→せ(ず)→未然形は「せ」。よって「せじ」
この「未然形+じ」の形は、古文読解において絶対的なルールですので、しっかりと頭に入れておきましょう。
助動詞「まじ」の接続
一方、助動詞「まじ」は、活用語の終止形に接続するのが原則です。これも、元となる助動詞「べし」と共通のルールです。「いったん言い切りの形(終止形)で示された事柄に対して、それはあり得ない、すべきではない」という強い判断を加えるニュアンスと捉えると理解しやすいでしょう。
(例)動詞「行く(四段)」の場合 → 終止形「行く」+まじ → 行くまじ
最重要例外:ラ変型活用語には連体形に接続
終止形接続の助動詞に共通する非常に重要な例外があります。それは、直前の活用語がラ変型(ラ変動詞、形容詞、形容動詞、およびラ変型の助動詞)である場合、終止形ではなく連体形に接続するというルールです。要はウ段の音に接続するということです。
- ラ変動詞「あり」:終止形「あり」ではなく連体形「ある」に接続 → あるまじ
- 形容詞「うつくし」:終止形「うつくし」ではなく連体形「うつくしかる」に接続 → うつくしかるまじ
- 助動詞「なり」(断定):終止形「なり」ではなく連体形「なる」に接続 → なるまじ
このルールは、文化庁が示すような日本語の歴史的変遷の中で、発音のしやすさから生まれたものとされています。助動詞「べし」「らし」「めり」「なり(伝聞推定)」など、他の終止形接続の助動詞にも適用されるため、必ずマスターしておくべき重要事項です。
助動詞「まじ」と「じ」の活用を覚えよう
助動詞自体の活用(形の変化)を覚えることも、文法理解には欠かせません。「じ」と「まじ」は活用の仕方が全く異なるため、この点も両者を区別する大きなポイントになります。
助動詞「じ」の活用
助動詞「じ」の活用は、驚くほどシンプルです。なんと、文中に出てくるとき、その形は一切変化しません。このような活用を「無変化型」と呼びます。そのため、活用表も非常に覚えやすくなっています。
これは助かりますね!一度「じ」という形を覚えてしまえば、どんな文脈でも見つけることができます。活用を覚える負担がほとんどないのが「じ」の魅力です。
| 活用形 | 基本形 | 文中での働き |
|---|---|---|
| 未然形 | (じ) | ー |
| 連用形 | (じ) | ー |
| 終止形 | じ | 文を言い切る |
| 連体形 | じ | 体言(名詞)に続く |
| 已然形 | じ | 「ども」などに続く |
| 命令形 | ー | ー |
※未然形と連用形は理論上存在しますが、実際の古典作品中で使われることはほぼ皆無であるため、通常は覚える必要はありません。終止形・連体形・已然形がすべて「じ」の形であると覚えておきましょう。
助動詞「まじ」の活用
助動詞「まじ」の活用は、「じ」とは対照的に複雑です。これは形容詞のシク活用と全く同じ活用をします。肯定形の「べし」が形容詞ク活用型であるのと対応しており、ここでも両者の関係性が見て取れます。
「まじ」の活用表(形容詞シク活用型)
| 活用形 | 活用語尾 | 主な用法 | |
|---|---|---|---|
| 未然形 | まじく | まじから | 「まじくは」の形で使われることがある |
| 連用形 | まじく | まじかり | 下に用言が続く場合や、「て」が付く場合 |
| 終止形 | まじ | 文を言い切る | |
| 連体形 | まじき | まじかる | 下に体言が続く場合や、係り結びで文末に来る場合 |
| 已然形 | まじけれ | 「ども」「ど」などが続く場合や、係り結びで文末に来る場合 | |
| 命令形 | ー | 命令形はない | |
右側の「から・かり・かる」で終わる補助活用は、下にさらに助動詞が付く場合に用いられます(例:まじからむ)。まずは基本となる左側の本活用(まじく、まじく、まじ、まじき、まじけれ)を呪文のように唱えて覚えるのがおすすめです。
現代語でも「あるまじき行為」という表現が残っているように、特に連体形「まじき」は頻出です。この言葉は、単に「ない」のではなく、「絶対にあってはならない」という強い倫理的な否定のニュアンスを含んでおり、「まじ」が持つ意味の強さを象徴しています。
「む」と「じ」の関係性を理解する
これまで何度も触れてきましたが、助動詞「じ」を本質的に理解する上で、助動詞「む」との関係性は避けて通れません。文法を個別の暗記事項としてではなく、一つのシステムとして捉えることで、応用力のある知識が身につきます。「じ」は、「む」という肯定の助動詞を打ち消すために存在する、対の存在であると考えることができます。
助動詞「む(ん)」は古文における最重要助動詞の一つで、非常に多くの意味を持ちますが、その中核は「未来」や「不確定な事柄」に対する話者の心的態度を示すことです。
助動詞「む」の主な意味
- 推量(~だろう):未来の出来事や見えない事柄を推測する。
- 意志(~しよう、~するつもりだ):未来の行動に対する決意を示す。
- 適当・勧誘(~するのがよい、~しないか):相手への提案や勧め。
- 仮定・婉曲(~としたら、~のような):ぼかした表現や仮の話。
この中で、最も基本的で中心的な意味が「推量」と「意志」です。そして、「じ」は、この二つの意味をそっくりそのまま打ち消す役割を担っています。
「む」に関してはこちらに詳しくまとめています。

「む」と「じ」の見事な対応関係
- 【肯定】「む」(推量:~だろう) ↔ 【否定】「じ」(打消推量:~ないだろう)
- 【肯定】「む」(意志:~しよう) ↔ 【否定】「じ」(打消意志:~まい、~するつもりはない)
この関係は、意味だけでなく接続ルールにも及びます。どちらも活用語の未然形に接続します。これは、「まだ実現していない事柄(未然)」に対する推量や意志を示すという共通の機能を持つためです。
したがって、「じ」について考えるときは、常に「む」をセットで思い浮かべる習慣をつけましょう。「この文の『じ』は打消推量か、打消意志か?」と迷ったときは、「もし肯定文だったら『む』の推量と意志のどちらが自然か?」と考えてみるのが、正解への有効なアプローチとなります。
「べし」と「まじ」の関係は正反対
「む」と「じ」の関係と同様に、助動詞「まじ」を理解するためには、助動詞「べし」との完全な対立関係を把握することが不可欠です。「べし」が持つ多様で強力な肯定の意味を、一つ残らず打ち消すのが「まじ」の役割です。その対応関係は実に見事であり、古文の文法が持つ論理的な整合性を象徴しています。
助動詞「べし」は、「む」が持つ推量や意志の意味をさらに強め、そこに「当然」や「義務」といった客観的・社会的なニュアンスを加えた助動詞です。その多義性から、多くの学習者が覚えるのに苦労しますが、有名な語呂合わせ「すいかとめて」が強力な助けとなります。
「すいかとめて」とそれを打ち消す「まじ」
「べし」の6つの意味を網羅した語呂合わせ「すいかとめて」と、それを一つひとつ打ち消していく「まじ」の意味は、以下の表のように完璧に対応しています。この表は、両助動詞をマスターするための設計図と言えるでしょう。
| 「べし」の肯定的な意味 | 「まじ」の否定的な意味 | 対比のポイント | |
|---|---|---|---|
| す | 推量(~にちがいない) | 打消推量(~ないだろう) | 確信度の高い推量とその否定 |
| い | 意志(きっと~しよう) | 打消意志(決して~まい) | 強い意志とその否定 |
| か | 可能(~できる) | 不可能(~できそうにない) | 能力や状況の肯定と否定 |
| と | 当然(~べきだ、~はずだ) | 打消当然(~はずがない) | 道理や常識の肯定と否定 |
| め | 命令(~しなさい) | 禁止(~してはならない) | 強制的な指示とその否定 |
| て | 適当(~するのがよい) | 不適当(~ないほうがよい) | 推奨される行為とその否定 |
この表からわかるように、「べし」の意味を正確に覚えてしまえば、「まじ」の意味はわざわざ個別に暗記する必要がほとんどありません。「べしの反対」と覚えておけば十分です。接続がどちらも原則終止形(ラ変型には連体形)である点も、このペアを強固に結びつけています。

面白いでしょう?古文の文法は、このようにパズルのように肯定と否定、強い意味と弱い意味が組み合わさってできています。このシステムがわかると、一気に古文が身近に感じられますよ!
古文の助動詞「まじ」と「じ」の識別法と関係性
「まじ」と「じ」の違いはどこにある?
これまでの解説で両者の違いはかなり明確になったかと思いますが、ここで改めて重要なポイントを整理し、比較してみましょう。助動詞「じ」と「まじ」は、主に①意味の範囲と強さ、②接続、③活用という3つの点で明確に区別することができます。これらの違いをまとめた以下の表を、最終確認としてご活用ください。
「じ」と「まじ」の総合比較表
| 比較項目 | 助動詞「じ」 | 助動詞「まじ」 |
|---|---|---|
| ① 意味 | 【範囲が狭い・意味が弱い】 打消推量・打消意志が中心。 「む」の単純な打消であり、話者の主観的な推測や決意を表すことが多い。 | 【範囲が広い・意味が強い】 打消推量・意志に加え、不可能・打消当然・禁止・不適当など意味が豊富。「べし」の打消であり、客観的な道理や社会的規範に基づく強い否定・判断を含むことが多い。 |
| ② 接続 | 未然形に接続する。 | 終止形に接続する。 (※ラ変型には連体形に接続するという重要例外あり) |
| ③ 活用 | 無変化型。 文中では常に「じ」の形で現れるため、発見しやすい。 | 形容詞シク活用型。 「まじく」「まじき」「まじけれ」など文脈に応じて形が変化するため、活用形の知識が必須。 |
端的に言えば、「じ」は「~ないだろうな」「~するつもりはない」といった、比較的シンプルで個人的なレベルの否定を表します。それに対して、「まじ」は「常識的に考えて~であるはずがない」「倫理的に~しては絶対にいけない」といった、より公的で強い確信を伴う否定を表すことができるのです。
実際の読解においては、まず接続の形に注目するのが最も確実な識別法です。助動詞らしきものを見つけたら、その直前の語の活用形を確認しましょう。それが未然形であれば「じ」、終止形(またはラ変の連体形)であれば「まじ」と、機械的に判断することが可能です。
簡単な見分け方のポイント

文法的なルール(接続・活用)による識別が基本ですが、それと並行して、文脈から意味をより正確に読み解くためのヒントも存在します。これらのポイントを活用することで、読解のスピードと精度をさらに高めることができます。
ポイント1:主語に注目する
これは特に「打消推量」と「打消意志」を区別する際に非常に有効な手段です。古典の文章では主語が省略されることが多いですが、文脈から主語を補って考える習慣をつけましょう。
- 主語が一人称(私、我、われ、筆者など)の場合 → 打消意志(~まい、~するつもりはない)の意味になる可能性が高い。
- 主語が三人称(光源氏、花、都、人々など)の場合 → 打消推量(~ないだろう)の意味になる可能性が高い。
「まじ」の場合もこの傾向は当てはまりますが、前述の通り意味が豊富なため、主語だけで全ての意味を判断することはできません。あくまで判断材料の一つとして活用してください。
ポイント2:特定の副詞との呼応(陳述の副詞)を探す
文中に特定の副詞があると、それが文末の表現を規定することがあります。これを「副詞の呼応(陳述の副詞)」と呼びます。「じ」や「まじ」といった打消推量の助動詞と特に結びつきが強い副詞を覚えておくと、強力な武器になります。
「じ」「まじ」とセットで覚えたい副詞
- よも~じ(まじ):
「まさか~ないだろう」「決して~あるまい」という意味の、非常に強い否定の推量を表します。「よも」を見つけたら、文末は高い確率で「じ」か「まじ」です。 - え~じ(まじ):
「とうてい~できそうにない」という意味の、不可能を表します。「え」という副詞は下に打消の語を伴って不可能を表すため、これがある場合は「まじ」の意味の中でも「不可能」に特定しやすくなります。 - さらに~じ(まじ):
「全く~ないだろう」「決して~ないつもりだ」という意味で、打消の意味を全面的に強めます。
ポイント3:文脈から話者の感情の強さや主張を読み取る
最終的には、文全体の流れや話者の置かれている状況、文章のジャンル(物語、説話、日記など)から総合的に判断する力が求められます。
- 客観的な描写や個人の感想 → 「じ」や「まじ」の「打消推量」が多い。
- 登場人物の決意表明 → 「じ」や「まじ」の「打消意志」が多い。
- 道徳的な教訓や社会的規範に関する記述 → 「まじ」の「禁止」「不適当」「打消当然」が多い。
(例)『徒然草』など、筆者の思想が述べられる随筆ではこの用法がよく見られます。
これらの判断基準を組み合わせることで、単語レベルの知識から文章レベルの深い読解へとステップアップしていくことができます。ぜひ実際の文章で用例を確認してみてください。(参照:国文学研究資料館 新日本古典籍総合データベース)
おすすめの覚え方を紹介

「じ」と「まじ」を、そしてそれらに関連する「む」と「べし」を効率的に覚えるためのおすすめの方法は、4つの助動詞の相関関係を図にして視覚的に覚えることです。知識をバラバラに詰め込むのではなく、相互の関連性を意識することで、記憶はより強固になり、忘れにくくなります。
【最強の暗記法】推量系助動詞4つの関係図
この図を自分で何度も書けるようになれば、知識は完璧です。
む(接続:未然形) ←ーーー【打消】ーーー→ じ(接続:未然形)
【強意】↓ ↓【強意】
べし(接続:終止形) ←ーーー【打消】ーーー→ まじ(接続:終止形)
この図が示す重要なポイントを改めて確認しましょう。
- 横の関係は「肯定 ↔ 否定(打消)」
左側(む、べし)が肯定的な意味、右側(じ、まじ)がそれを打ち消す否定的な意味を表します。 - 縦の関係は「意味の強弱(弱 ↓ 強)」
上段(む、じ)が基本的な推量・意志であるのに対し、下段(べし、まじ)はそれを強め、より多くの意味(当然、可能など)を含みます。 - 接続ルールもペアで覚えられる
上段の「む・じ」ペアはどちらも未然形接続。下段の「べし・まじ」ペアはどちらも終止形接続(ラ変の例外あり)。
学習の際には、まずこの関係図をノートに書き出すことから始めてみてください。そして、例えば「まじ」について問われたら、頭の中でこの図を思い浮かべ、「べしの打消で、終止形接続だったな」と情報を引き出す練習を繰り返します。この体系的な理解こそが、丸暗記から脱却し、忘れにくく応用しやすい知識を身につけるための最も効果的な方法です。
便利な語呂合わせで暗記しよう

体系的な理解と並行して、記憶を助けるためのツールとして「語呂合わせ」を活用するのも非常に有効です。特に意味の数が多い助動詞「べし」と、それに対応する「まじ」については、語呂合わせが絶大な効果を発揮します。
基本となる「べし」の語呂合わせ「すいかとめて」
多くの高校の授業でも教えられる、最も有名で優れた語呂合わせが「すいかとめて」です。まずはこの基本をしっかりとマスターしましょう。
「庭に大きなスイカが置いてあって邪魔だから、誰かに『スイカ、止めて!』と命令している」…そんな光景を想像すると、意味と語呂が結びつきやすくなりますよ!
- す:すい量
- い:い志
- か:か能
- と:とう然
- め:めい令
- て:てき当
「まじ」はそれを打ち消すだけ!「打消すいかとめて」
ここが重要なポイントです。「べし」の語呂合わせさえ覚えてしまえば、「まじ」のために新しい語呂合わせを発明する必要は全くありません。先ほどの「すいかとめて」の各意味の前に「打消」や「不」を付けるだけで、「まじ」の意味が完成します。
- 打消推量(すいりょうの打消)
- 打消意志(いしの打消)
- 不可能(かのうの打消。打消可能より自然な表現)
- 打消当然(とうぜんの打消)
- 禁止(めいれいの打消。打消命令より自然な表現)
- 不適当(てきとうの打消。打消適当より自然な表現)
このように、関連する知識はセットで覚えることで、脳への負担を半分にすることができます。まずは肯定形の「すいかとめて」を完璧に暗唱できるようにし、それから「まじ」はその反対、と覚えるのが最も効率的な学習ステップです。
練習問題で理解度をチェック

それでは、ここまでの知識が本当に身についているか、実際の古典文学からの用例を使って腕試しをしてみましょう。各文の下線部の助動詞「じ」「まじ」について、文法的意味と活用形を答えてください。じっくり考えてみましょう。
問題
問1. 謗(そし)るとも苦しかるまじ。誉むとも聞き入れじ。(徒然草)
問2. 冬枯れのけしきこそ、秋にはをさをさ劣るまじけれ。(徒然草)
問3. わが身は女なりとも、敵の手にはかかるまじ。(平家物語)
問4. をる人だにたやすく見るまじきものを、まして、外より来たらむ人の見るべきかは。(竹取物語)
問5. 人のたはやすく通ふまじからむ所に、跡を絶えてこもりゐなむ。(堤中納言物語)
解答と解説
答1.【意味】打消意志【活用形】終止形
解説:主語は省略されていますが文脈から筆者自身(一人称)とわかります。「(他人が)悪口を言っても(私は)気にしないつもりだ。(他人が)褒めても聞き入れないつもりだ」という、世評に惑わされない強い意志を表しています。文末なのでどちらも終止形です。
答2.【意味】打消推量【活用形】已然形
解説:「冬枯れの景色は、秋の景色に比べて少しも劣らないだろう」という筆者の推量を表しています。文中に係助詞「こそ」があるため、文末が係り結びの法則によって已然形「まじけれ」に変化しています。
答3.【意味】打消意志【活用形】終止形
解説:「わが身は」と明確に一人称が主語です。「たとえ女であっても、敵の手に捕まるつもりはない」という、登場人物の断固たる決意が示されています。
答4.【意味】不可能【活用形】連体形
解説:「(姫に)お仕えしている人でさえ容易に見ることができそうもないのに」という意味です。「たやすく~できそうもない」という文脈から「不可能」と判断できます。また、直後に体言(名詞)である「もの」が来ているため、活用形は連体形「まじき」となります。
答5.【意味】不可能【活用形】未然形
解説:「人が簡単に通うことができそうもないような所に…」という意味です。直後に推量の助動詞「む」が来ているため、「まじ」は未然形「まじから」に活用しています。これは補助活用の例です。
古文の助動詞「まじ」と「じ」はセットで攻略
今回は、古文の学習における大きな壁の一つ、助動詞「じ」と「まじ」について、その本質的な違いから具体的な覚え方、実践問題までを詳しく解説しました。単語や文法を一つひとつバラバラに覚える学習法には限界があります。しかし、今回学んだように、助動詞同士の関係性という「システム」を理解することで、知識は有機的につながり、忘れにくく、応用しやすいものになります。
最後に、本記事で学んだ最重要ポイントをもう一度リストで確認しましょう。これらの知識は、今後のあなたの古文読解にとって、間違いなく大きな武器となるはずです。
- 助動詞「じ」と「まじ」はどちらも打消の意味を持つ重要な助動詞
- 「じ」は肯定の助動詞「む」と対になる打消バージョンである
- 「まじ」は肯定の助動詞「べし」と対になる打消バージョンである
- 「じ」の主な意味は打消推量(~ないだろう)と打消意志(~まい)の2つ
- 「まじ」は打消推量、打消意志、不可能、打消当然、禁止、不適当の6つの意味を持つ
- 「じ」は活用語の未然形に接続する(「む」と同じ)
- 「まじ」は活用語の終止形に接続する(「べし」と同じ)
- ただしラ変型の活用語には連体形で接続するという最重要例外がある
- 「じ」の活用は形が一切変わらない無変化型で覚えやすい
- 「まじ」の活用は形容詞シク活用型で、形の変化を覚える必要がある
- 意味の識別は、接続のルール、主語、文脈、呼応の副詞などが大きな手がかりになる
- 「む・じ・べし・まじ」の4つを関係図で体系的に覚えるのが最も効率的
- 「べし」の語呂合わせ「すいかとめて」を覚えれば「まじ」の意味は簡単に導き出せる
- 接続の形に注目すれば、文法的な識別は機械的に行うことが可能
- これらの助動詞をマスターすれば、文章の細かいニュアンスまで正確に読み取れるようになる
今回の学習をきっかけに、ぜひ多くの古典作品に触れてみてください。きっと、文法知識を使って文章が読解できたときの喜びを、より深く感じられるはずです。
古文の勉強法、お疲れ様でした!
「よし、やるぞ!」と思っても、「でも、文法をゼロから体系的にやり直すのって、独学だと不安だなぁ…」と感じていませんか?
もし、あなたが「元・古文が苦手」だった先生から、センスに頼らない「論理的な解き方」を学びたいなら…
今、多くの受験生から「神授業」と呼ばれている「スタディサプリ 古文」を、私が徹底的に分析した記事がきっと役立つはずです。
なぜ岡本先生の授業がそこまで支持されるのか、ゼロから始める具体的な受講順番まで詳しく解説しています。
古文を「苦手」から「得意」に変える、その具体的な方法に興味がある方は、ぜひ覗いてみてくださいね。
→ 関連記事:スタディサプリ古文が神授業と言われる理由|ゼロから始める最適ルートも解説
この記事を読んで、古文の理解がまた一つ深まりましたね。
でも、古文は「単語」「文法」「読解」「常識」など、全ての知識が有機的につながって初めて高得点が取れる科目です。
「次はどこを勉強すればいいの?」
「苦手なあの分野、どうやって対策しよう?」
そんな迷子にならないよう、ミチプラス内の古文記事を「勉強する順番」に整理した「完全攻略マップ」を作成しました。
辞書代わりにブックマークして、最短ルートで志望校合格を目指しましょう!