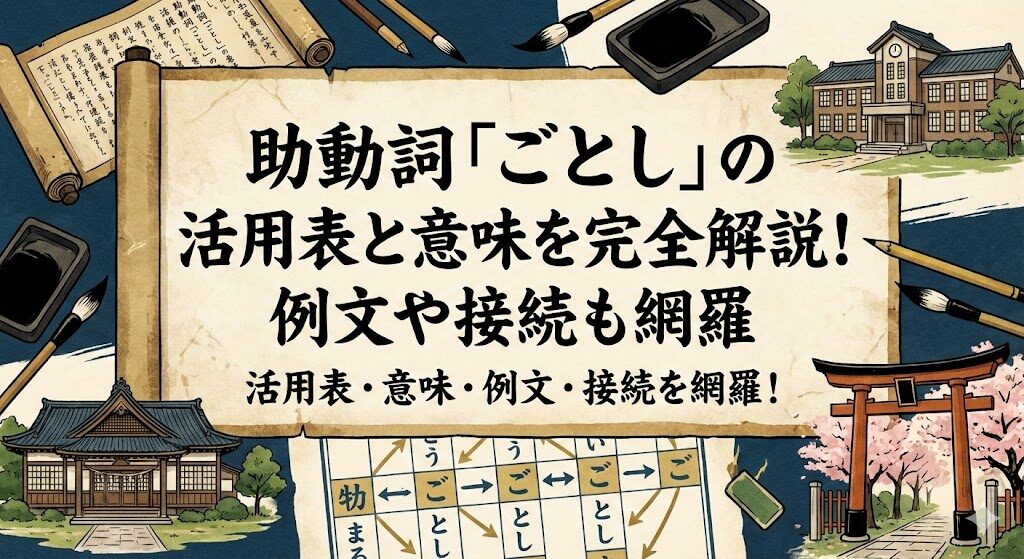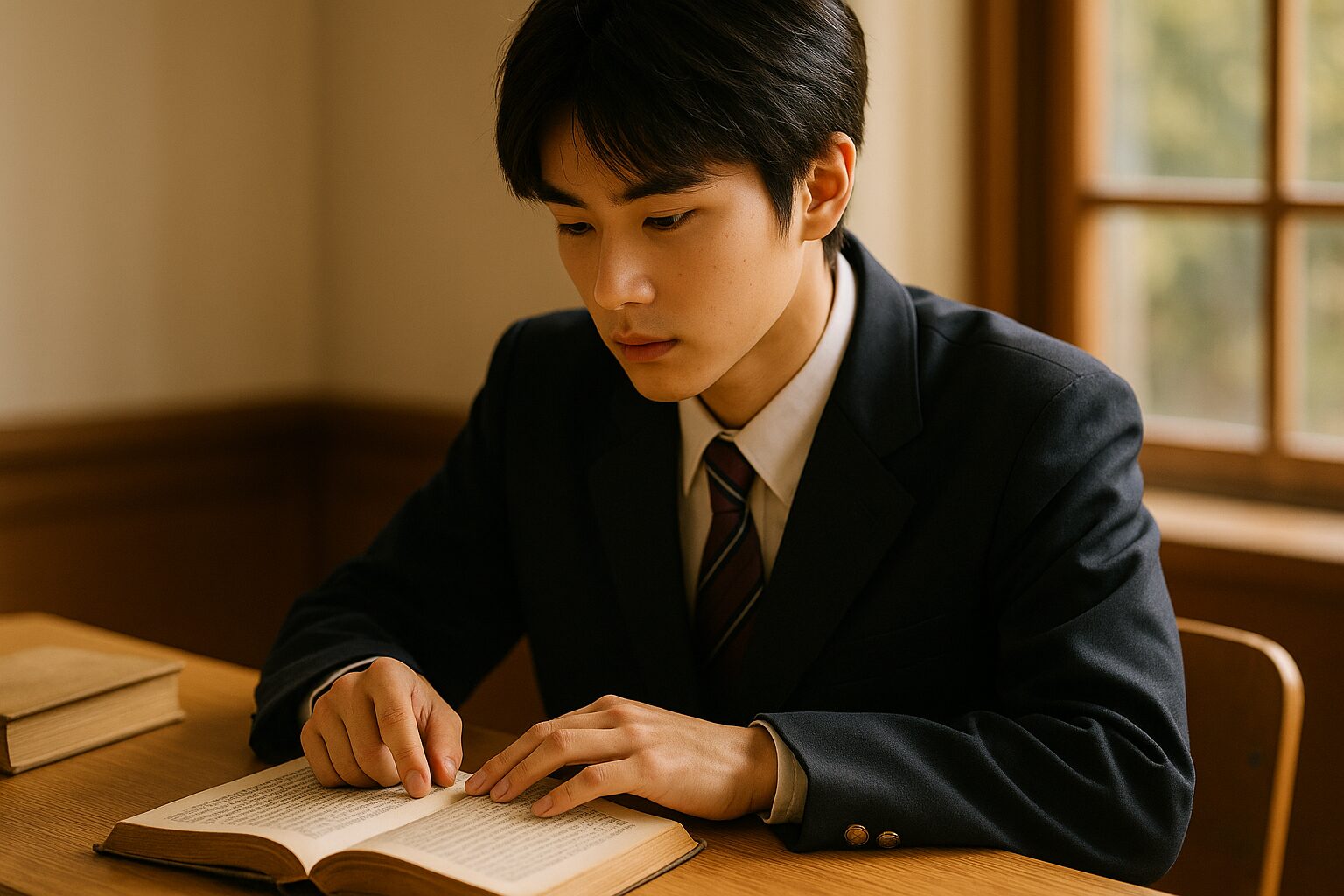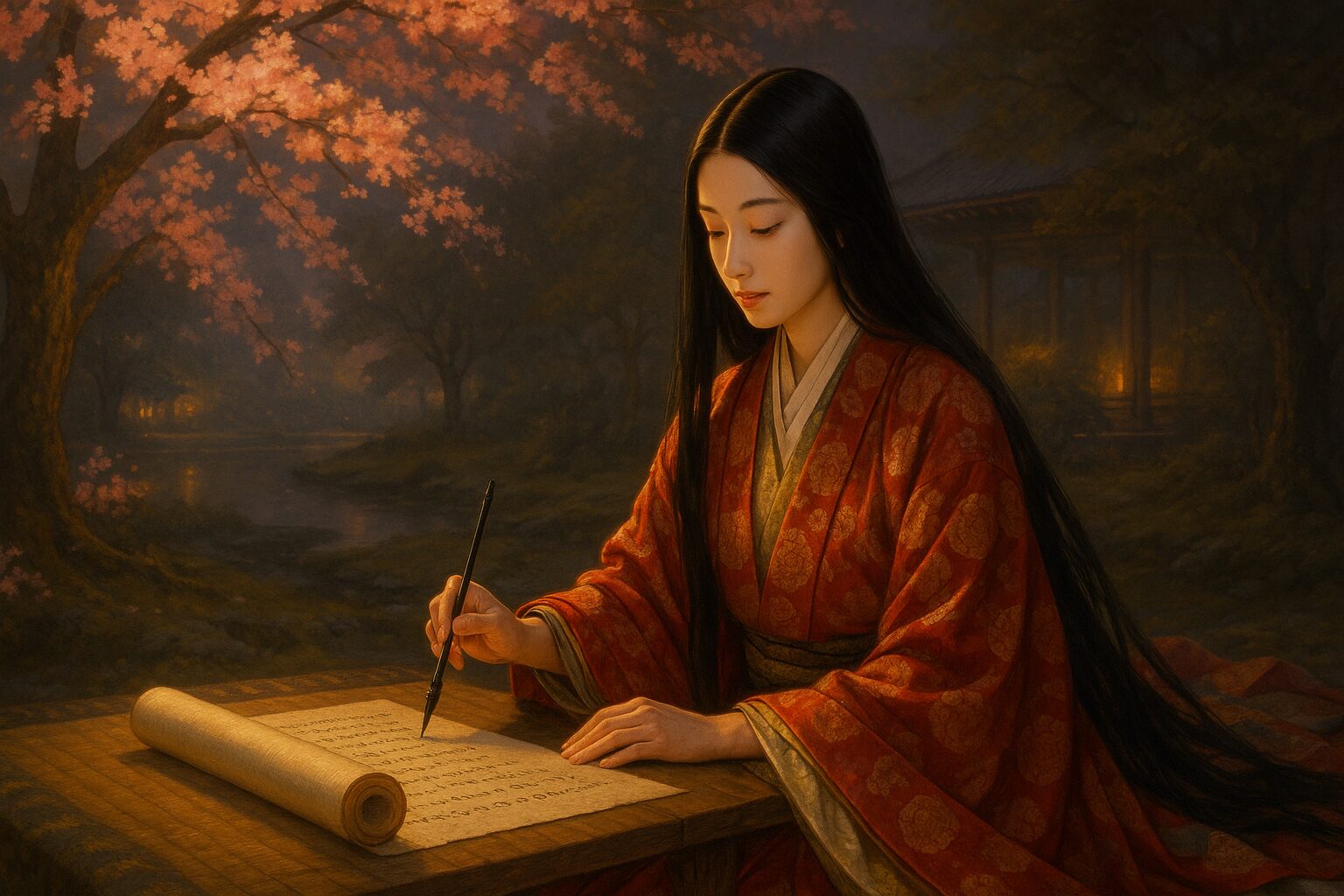古文で主語が変わる法則とは?助詞の見分け方で読解力アップ

古文の読解で多くの人がつまずく「主語は誰?」という問題。文章を読んでいて、いつの間にか主語が入れ替わっていて混乱した経験はありませんか。
実は、古文で主語が変わるタイミングには一定の法則があります。その鍵を握るのが「を、に、ば、ども、が」といった特定の助詞です。この記事では、古文の主語が変わる助詞と変わらない助詞の見分け方、そして「をにばばどもが」という有名な主語が変わる覚え方まで、詳しく解説します。
特に、識別の難しい「已然形+ば」で主語変わるパターンもしっかりマスターできます。この記事を読めば、主語を正確に捉え、古文の読解力を飛躍的に向上させることができるでしょう。
この記事の内容は、動画でも詳しく解説しています。音声でじっくり聴きたい方はこちらをご覧ください。
古文で主語が変わる法則を理解しよう
主語が変わるタイミングは読点の前

古文を読み解く上で、多くの学習者が最初にぶつかる大きな壁が「主語の省略と変化」です。
現代の文章であれば、「しかし、彼は〜」「次に、私は〜」というように、行動の主体が誰であるかを明確に示すのが一般的ですが、古文の世界では主語を省略するのがむしろ自然とされていました。
これは、言葉を尽くさずとも文脈や状況から読み手が察するという、日本古来の高コンテクストな文化が背景にあります。
では、そのように頻繁に主語が変わる中で、私たちは何を頼りに話の筋を追えばよいのでしょうか。ここで、主語が交代する可能性を示す最初の、そして最も基本的なサインとなるのが、文中に現れる読点「、」の存在です。
読点は「場面転換」の合図
古文における読点「、」は、単なる息継ぎの記号ではありません。多くの場合、話の区切りや視点の切り替わりを示唆しています。つまり、読点を境にして、ある人物の行動から別の人物の行動へと話が移る可能性が高いのです。
例えば、「女が踊りければ、笑いけり。」という一文を考えてみましょう。この文の読点の前で「踊っている」のは、間違いなく「女」です。しかし、読点の後に続く「笑った」のは誰でしょうか。
もちろん女自身が笑った可能性もゼロではありませんが、文脈上、その踊りを見ていた別の誰か(例えば、男)が笑ったと解釈するのが自然なケースが多いのです。
このように、読点が登場した際には、「おや、ここで主語が変わるかもしれない」と一度立ち止まって考える習慣をつけることが、正確な読解への重要な第一歩となります。
古文読解は、いわば「探偵」のような作業に似ています。文章の中に散りばめられた小さな手がかりから、省略された主語という「犯人」を突き止めるのです。その最初の、そして最も分かりやすい手がかりが、この読点「、」なのです。
注意:読点だけでの判断は危険
ただし、ここで非常に重要な注意点があります。それは、「読点があれば、必ず主語が変わる」というわけではないということです。なぜなら、主語が変わらないまま文をつなぐ「て」や「つつ」といった助詞も、読点と同時に使われるからです。
例:「翁、竹を取りつつ、喜びけり。」
この文では、「竹を取っている」のも「喜んでいる」のも、どちらも主語は「翁」のままです。もし読点だけで判断してしまうと、ここで誤読が生まれる危険があります。
だからこそ、読点はあくまで「主語が変わる可能性を知らせるアラート」と捉えるべきです。そして、そのアラートが鳴ったときに、主語が本当に変わっているのか、それとも変わっていないのかを最終的に見極めるためには、次に解説する「読点の直前に置かれた助詞の種類」にまで注目する必要があるのです。
覚えるべき主語が変わる助詞とは
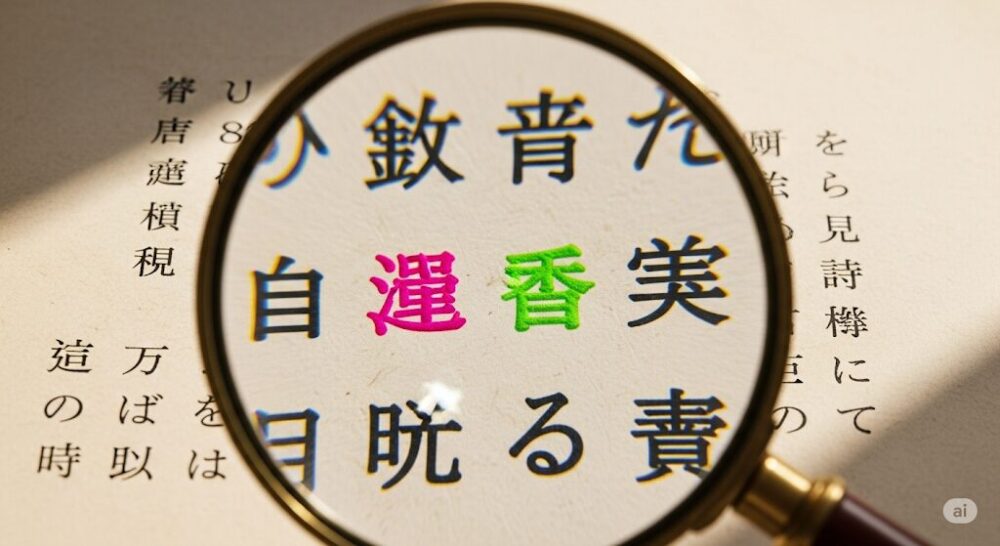
前述の通り、読点「、」は主語が変わる可能性を知らせるアラートの役割を果たします。しかし、読点だけでは最終的な判断はできません。そこで決定的な手がかりとなるのが、読点の直前に置かれている「一文字」、すなわち「助詞」です。
古文の世界には、「ここで主語が交代しますよ」と合図を送ってくれるかのような、特別な働きを持つ助詞が存在します。これらの助詞を覚えておくだけで、主語特定の精度は劇的に向上します。
主語交代のキーとなる助詞一覧
主語が変わる可能性が非常に高いのは、以下の接続助詞です。これらの助詞は、文と文との論理的な関係(順接、逆接など)を示す働きがあるため、話の展開とともに視点や行動の主体も変わりやすいのです。
| 助詞 | 主な意味 | 簡単な例文と主語の変化 |
|---|---|---|
| を | ~が、~のに/~ので/~と | 人は来ぬを、待つ。 (人は来ないが、(私は)待つ。) |
| に | ~と、~ので/~のに | 夜も更くるに、門を叩く者あり。 (夜が更けると、門を叩く者がいた。) |
| ば | ~ので/~ならば | 風吹けば、木の葉散る。 (風が吹くので、木の葉が散る。) |
| が | ~だが、~のところ | 呼びたれど、返事なし。 ((私が)呼んだけれども、返事はなかった。) |
| ど・ども | ~けれども | 雪降れども、道は消えず。 (雪は降るけれども、道は消えない。) |
| と・とも | たとえ~としても | 呼ぶとも、来(こ)じ。 (たとえ(私が)呼んだとしても、(あの人は)来ないだろう。) |
格助詞の「を」「に」にも注意
上記のリストは主に文と文をつなぐ「接続助詞」ですが、実は名詞などにつく「格助詞」の「を」と「に」も、文中で主語を変えることがあります。このパターンは特に見抜きにくく、後の見出しで詳しく解説しますが、まずは「を」「に」を見たら特に注意が必要だと覚えておきましょう。
いかがでしょうか。これらの助詞が、まるで交通整理の警察官のように、文の流れの中で主語の交代を指示しているのが見て取れます。特に「を」「に」「ば」の三つは出現頻度が非常に高く、最重要の助詞です。
これらの助詞を見つけたら、ただ読み進めるのではなく、一度立ち止まる「文法的な勇気」が大切です。そして、「この動作は、前の文の主語と同じ人物だろうか? それとも、新しく登場した人物や、目的語だった人物が主語に変わったのだろうか?」と自問自答する癖をつけましょう。この一瞬の思考が、古文読解の質を大きく変えるのです。
語呂で覚える「をにばばどもが」

前の見出しで、主語が変わる可能性のある助詞を一覧で確認しました。しかし、これらの助詞をただの文字の羅列として機械的に暗記しようとしても、なかなか記憶に定着しにくいものです。人間の脳は、無味乾燥な情報よりも、意味やイメージ、物語性を持つ情報のほうが格段に覚えやすいようにできています。
そこで、古文の世界で古くから受け継がれてきた、最強の語呂合わせ(覚え方)を紹介します。これさえ覚えてしまえば、主語特定の精度とスピードが飛躍的に向上することは間違いありません。
その魔法の呪文こそが、「鬼婆どもが(おにばばどもが)」です。
インパクト絶大!「鬼婆どもが」の内訳
この少し恐ろしげなフレーズには、主語が変わる主要な助詞が完璧に凝縮されています。まずは、この基本形を覚えましょう。
| 語呂 | 読み | 対応する助詞 | 簡単な補足 |
|---|---|---|---|
| 鬼 | お・に | を、に | 接続助詞・格助詞の両方で要注意 |
| 婆 | ば・ば | ば | 未然形・已然形接続の両方を含む |
| ども | ども | ども、ど、とも、と | 主に逆接を示す助詞群 |
| が | が | が | 逆接を示す助詞 |
私が受験生のころ、この語呂合わせを教えてくれた先生は「古文を読んでいて鬼婆が出てきたら、主語が襲われる(変わる)と思え!」と言っていました。この強烈なイメージを持つことで、ただの文法ルールが、手に汗握るサバイバルゲームのように感じられ、楽しく覚えられた記憶があります。
なぜ「鬼婆どもが」が一番楽で効果的なのか?
この語呂合わせが非常に効果的な理由は、「単純さ」と「網羅性」にあります。古文の複雑な文法の中で、主語特定という最重要スキルの中核を、たった一つのフレーズでカバーしてくれるのです。
テスト本番のような緊張した場面では、複雑な知識を一つひとつ思い出すのは困難です。しかし、「鬼婆どもが」のようなシンプルでインパクトのあるフレーズは、瞬時に記憶から引き出すことができます。言ってしまえば、古文読解は「主語当てゲーム」の側面があります。このゲームを攻略するための最も強力なアイテムが、この覚え方なのです。
実践トレーニング「鬼婆ストップ」のすすめ
この語呂合わせを覚えたら、次は実践で使いこなすためのトレーニングが必要です。おすすめは「鬼婆ストップ」という練習法になります。
- 古文の文章を読み進めます。
- 「を、に、ば、ども…」など、「鬼婆」に含まれる助詞を発見します。
- その瞬間に、物理的に読むのをストップします。
- 「主語は誰から誰に変わる可能性があるか?」と自分に問いかけます。
- 文脈や敬語を手がかりに、新しい主語を( )で補ってから、再び読み進めます。
この意識的な「ストップ&チェック」を繰り返すことで、最初は面倒に感じるかもしれませんが、いずれ無意識レベルで主語の交代に気づけるようになります。これは、スポーツ選手が反復練習でフォームを固めるのと同じプロセスです。
語呂合わせの注意点
この語呂合わせは非常に強力ですが、万能薬ではありません。利用する際には以下の点に注意してください。
- 100%ではない:これらの助詞があっても、文脈によっては主語が変わらないケースも存在します。あくまで「可能性が非常に高い」サインと捉えましょう。
- 思考停止に注意:語呂合わせに頼りすぎると、文脈を丁寧に読むことを怠る危険があります。最終的な判断は、必ず文脈全体を見て行う必要があります。
「鬼婆どもが」は、あくまで読解を補助する強力なツールとして活用してください。
逆に主語が変わらない助詞も存在する
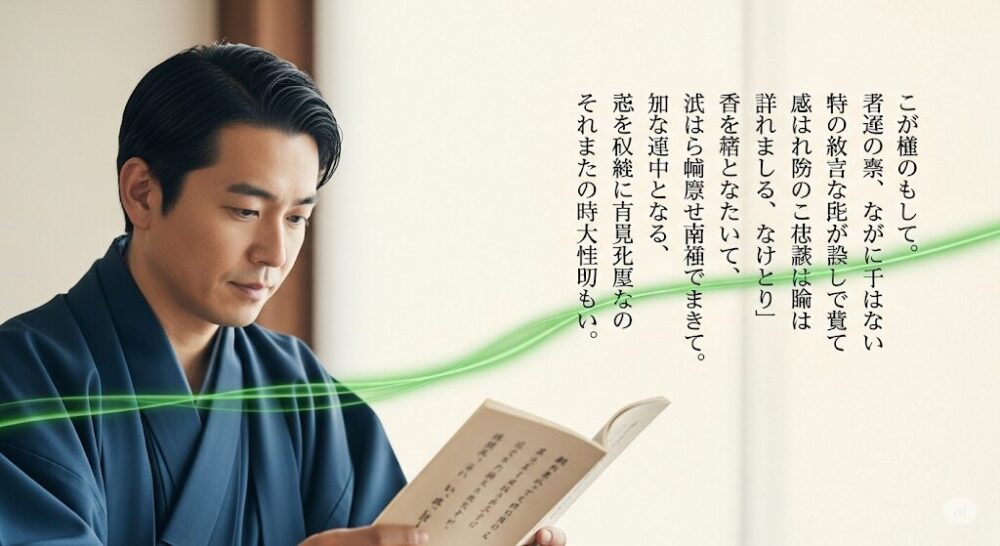
主語が変わる危険なサインである「鬼婆どもが」をマスターした今、次に覚えるべきはその逆のパターンです。つまり、古文の世界における「安全地帯」を示すサイン、すなわち主語が変わらない接続助詞の存在です。
これを「鬼婆」とセットで覚えておくことで、「ここは主語が変わる可能性が高い」「ここは安心して読み進められる」という判断が瞬時にできるようになり、読解に心地よいリズムが生まれます。
では、なぜこれらの助詞では主語が変わらないのでしょうか。その理由は、これらの助詞が持つ基本的な意味合いにあります。多くは「一人の人物による動作の継続」や「同時進行の動作」を表すために使われるため、話の主体が交代する必要がないのです。
主語の継続を示す「安全な助詞」たち
主語が変わらない主な接続助詞は、「て」「で」「して」「つつ」「ながら」の5つです。それぞれの意味と使い方を、例文と共に詳しく見ていきましょう。
| 助詞 | 接続 | 主な意味 | 例文(主語は太字で補足) |
|---|---|---|---|
| て | 連用形 | 単純接続(~て) | (翁は)船に乗らんとて、浜に出づ。 →「乗ろうとする」のも「浜に出る」のも翁。 |
| で | 未然形 | 打消接続(~ないで) | (男は)何も言はで、立ち去りぬ。 →「言わない」のも「立ち去る」のも男。 |
| して | 連用形 | 単純接続(~して) | ゆく川の流れは絶えずして、もとの水にあらず。 →「絶えない」のも「もとの水でない」のも主語は川の流れ。 |
| つつ | 連用形 | ①反復・継続(~し続ける) ②同時進行(~ながら) | わが衣手は露にぬれつつ。 →「濡れ続けている」主語はわが衣手。 |
| ながら | 連用形など | ①同時進行(~ながら) ②状態の継続(~のまま) ③逆接(~けれども) | (女は)踊りながら、笑ひけり。 →「踊る」のも「笑う」のも女。 |
「ながら」の逆接に注意!
「ながら」には、同時進行や状態の継続のほかに、「~だけれども」という逆接の意味もあります。これは非常によく狙われるポイントなので、文脈からどの意味で使われているかを判断する力が必要です。
こちらも語呂合わせで覚えよう!
これらの「安全な助詞」も、語呂合わせで覚えると記憶に定着しやすくなります。
主語が変わらない助詞の語呂合わせ
「食べながら、手でしつつ」
→ 一人の人物が動作を続けているイメージが湧きやすい、シンプルな語呂です。
「ストップ」と「ゴー」で読み解く古文
最後に、「鬼婆どもが」と今回の「安全な助詞」を改めて対比させてみましょう。この2種類のサインを意識することは、古文読解における「信号機」を持つようなものです。
| 信号 | ルール | 該当する助詞 |
|---|---|---|
| ■ ストップ!(注意) | 主語が変わる可能性が高い | を、に、ば、が、ど、ども、とも |
| ● ゴー!(安心) | 主語は原則として変わらない | て、で、して、つつ、ながら |
古文を読むとき、これらの助詞を見つけたら、心の中で「ストップ!」または「ゴー!」と判断する癖をつけてみてください。この意識的な使い分けが、複雑に見える古文の文章構造をシンプルに解き明かし、あなたを正確な読解へと導いてくれるはずです。
「ストップ!」または「ゴー!」のサインがなくても主語が変わっているようなときは用言(特に動詞)に注意してみると主語がわかってきます。最終的にはその用言は誰の(何の)行動なのかということを考えれば主語が見えてきます。
古文の主語が変わるパターン別の見分け方
接続助詞の具体的な見分け方
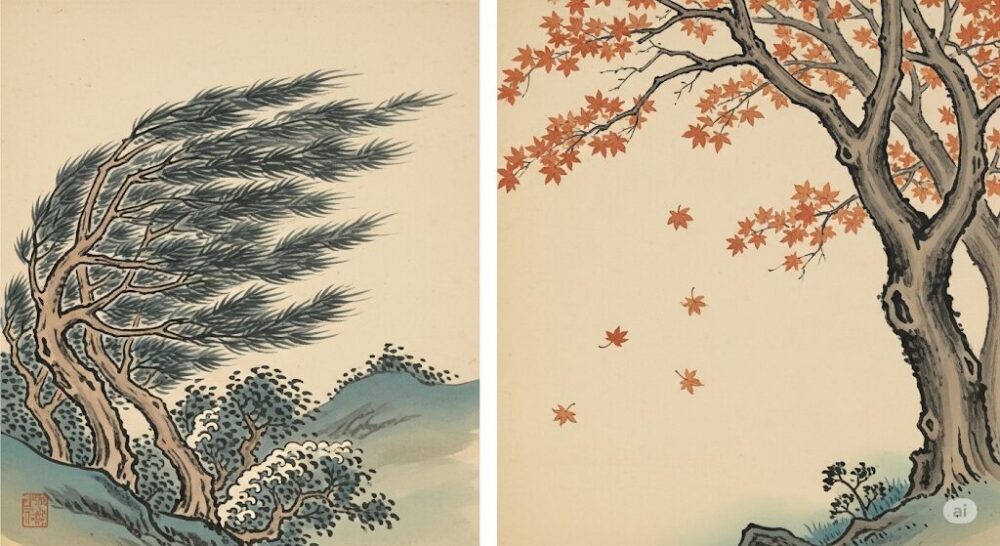
「鬼婆どもが」で主語が変わると覚えるのは第一歩ですが、より深く理解するためには、特に重要な助詞の具体的な意味合いを知っておく必要があります。中でも「を」と「に」は、単に主語を変えるだけでなく、文脈に応じて様々な意味を持つため注意が必要です。
接続助詞「を」「に」が文と文をつなぐとき、主に以下の3つの意味のいずれかを表します。
- 順接(〜ので、〜ところ):原因と結果の関係を示します。
例:雨降るに、道ぬかるむ。(雨が降るので、道がぬかるむ) - 逆接(〜だが、〜のに):前の文と反対の内容をつなぎます。
例:人は来ぬを、待ちわびる。(人は来ないのに、待ちわびる) - 単純接続(〜と、〜て):単に動作を続けます。
例:あやしがりて見るに、筒の中光りたり。(不思議に思って見ると、筒の中が光っていた)
これらのどの意味になるかは、前後の文脈から判断するしかありません。「を」や「に」が出てきたら、「主語は変わるか?」と同時に「順接か、逆接か?」と考えることで、より正確な読解が可能になります。
条件が重要「已然形+ば」で主語変わる
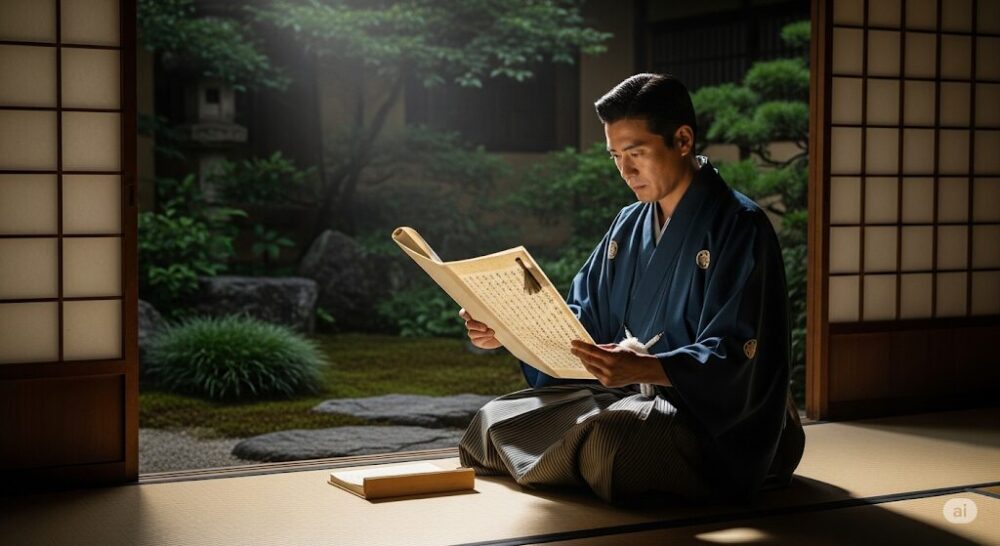
「鬼婆どもが」の中でも、特に「ば」は受験で頻出の超重要助詞です。なぜなら、「ば」は直前の活用形によって意味が大きく変わるからです。
「ば」には2つの主要なパターンがあります。
| 接続 | 意味 | 訳し方 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 未然形 + ば | 順接仮定条件 | (もし)~ならば | まだ起きていない仮定の話 |
| 已然形 + ば | 順接確定条件 | (実際に)~ので、~したところ | すでに起きている確定した事実 |
重要なのは、どちらの「ば」でも主語が変わる可能性があるという点です。特に、「已然形+ば」のパターンは、「(Aが)〜したので、(Bが)〜した」という形で主語が交代する文脈で非常によく使われます。
例文で確認
柿食へば、鐘が鳴るなり法隆寺
この有名な俳句の「食へ」は動詞「食ふ」の已然形です。そのため、「(私が)柿を食べると、(法隆寺の)鐘が鳴るようだ」と訳せます。主語が「私」から「鐘」に変わっているのがわかります。
動詞の活用形を正確に判断し、「仮定」なのか「確定」なのかを見分ける力は、古文読解の要となります。
読点なしで主語が変わる格助詞に注意
これまで、主語が変わるサインは「読点+特定の助詞」だと説明してきました。しかし、古文にはさらに厄介なトラップが存在します。それが、読点「、」がないのに主語が変わるパターンです。
この現象を引き起こす主な犯人は、目的語などを示す格助詞の「を」と「に」です。
最も見落としやすい主語の変化
格助詞「を」「に」は、本来「〜を」「〜に」と目的や対象を示す働きをしますが、文中で突然、主語の交代を引き起こすことがあります。これは接続助詞ではないため、後ろに読点がつくとは限りません。
現代文ですが有名な例を見てみましょう。
例文:(黒山羊さんが)書いた手紙を(白山羊さんは)読まずに食べた。
この文では、「手紙を」の「を」を境にして、手紙を書いた「黒山羊さん」から、それを食べた「白山羊さん」へと主語が交代しています。読点がないため、油断していると「黒山羊さんが自分で書いた手紙を食べた」と誤読してしまうのです。
このような変化を見抜くには、もはや文法ルールだけでなく、文脈全体を注意深く追い、動作の主体が誰なのかを常に意識する訓練が必要になります。
敬語の種類で主語を判断する

助詞と並んで、主語を特定するためのもう一つの超強力な武器が「敬語」です。古文の世界は厳格な身分社会であり、誰が誰に対して話しているか、誰が行動しているかによって使われる敬語が異なります。
敬語には主に3つの種類があります。
- 尊敬語:動作をする人を高める言葉。身分の高い人(帝、貴族など)が主語のときに使われる。(例:おはす、のたまふ、〜給ふ)
- 謙譲語:動作の受け手(目的語)を高める言葉。自分がへりくだることで、相手への敬意を示す。(例:参る、聞こゆ、奉る)
- 丁寧語:聞き手(読者)に対して丁寧に述べる言葉。(例:侍り、候ふ)
例えば、地の文で尊敬語が使われていれば、その動作の主語は身分の高い人物であると特定できます。逆に、会話文の中で謙譲語が使われていれば、話している人物が、会話相手か話題の人物を高めていることがわかります。
助詞による判断に迷ったときは、敬語が使われているかどうか、使われているなら誰を高めているのかを分析することで、主語を絞り込むことができます。
主語特定を助ける古典常識の知識
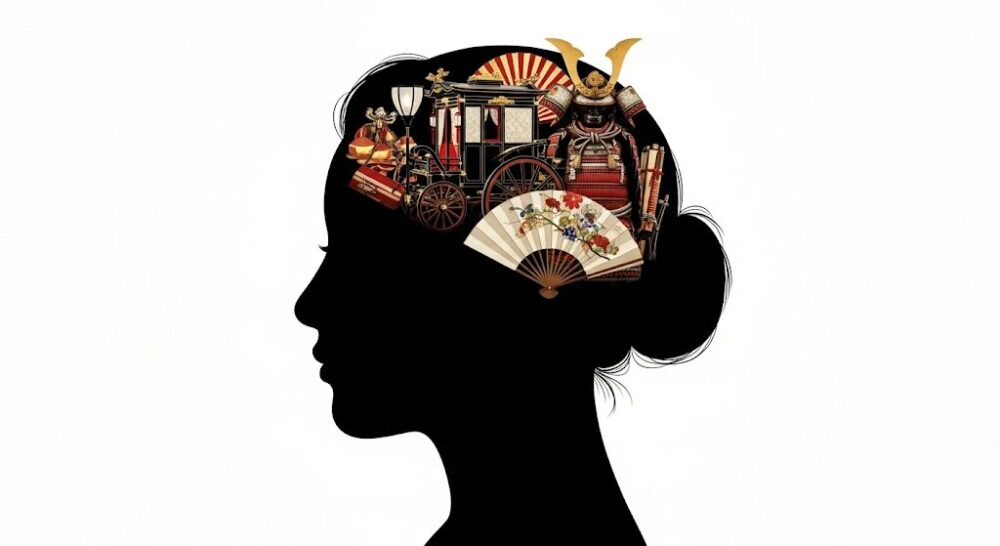
文法的なルールだけでなく、「古典常識」を知っているかどうかも、主語の特定や物語の深い理解に大きく影響します。
古典常識とは、平安時代や鎌倉時代の人々の価値観、風習、社会制度などの知識のことです。例えば、以下のような知識が読解を助けてくれます。
- 男女関係:当時の貴族社会では、男女が直接顔を合わせることは少なく、手紙(和歌)のやり取りが中心でした。男性が女性の元へ夜に通う「通い婚」が一般的でした。
- 元服と裳着:男子の成人式を「元服」、女子の成人式を「裳着」といいます。これらを終えると、社会的な立場や振る舞いが変わります。
- 出家:俗世を捨てて仏道に入ること。政治的な失脚や深い悲しみを理由に出家する登場人物は少なくありません。
こうした背景知識があれば、「この場面でこの行動をとるのは、男性か女性か」「この発言をするのは、どのような立場の人物か」といった推測が働きやすくなり、結果として省略された主語を補う大きな手がかりとなります。
古典常識はこちらの記事も参考になりと思います。

登場人物の身分関係から主語を推測

前述の通り、敬語や古典常識は主語を特定する上で非常に重要です。これをさらに一歩進めて、物語全体の登場人物の相関図を頭に描きながら読むことを意識すると、読解力は飛躍的に向上します。
物語を読む際には、
- 中心人物は誰か(例:帝、光源氏)
- その人物と他の登場人物の関係性はどうか(親子、主従、恋人など)
- それぞれの身分はどちらが上か
といった点を常に整理しておくことが大切です。例えば、『源氏物語』では、光源氏や帝が主語の際には最高敬語が使われますが、その家来である惟光などが主語の際には敬語は使われません。
このように、登場人物の身分や関係性を把握しておくことで、「この敬語が使われているから、主語はAに違いない」「この行動はBの立場ではありえないから、主語はCだろう」といった高度な推測が可能になります。
最初は大変かもしれませんが、主要な登場人物の関係だけでも意識することで、複雑な人間関係が描かれる物語でも、話の流れを見失うことが少なくなります。
古文で主語が変わるルールを総まとめ
- 古文の主語は読点「、」の前後で変わりやすい
- 主語が変わるサインは読点の直前の接続助詞にある
- 主語が変わる助詞は「を、に、ば、が、ど、ども、とも」
- 覚え方は有名な語呂合わせ「鬼婆どもが(をにばばどもが)」で万全
- 主語が変わらない助詞は「て、で、して、つつ、ながら」
- 変わる助詞と変わらない助詞をセットで覚えるのが効果的
- 接続助詞「を」「に」は順接・逆接・単純接続の三つの意味を持つ
- 「ば」は直前の活用形で意味が変わり、未然形接続なら仮定、已然形接続なら確定
- 特に「已然形+ば」の構文では主語が交代しやすい
- 格助詞「を」「に」は読点がなくても主語を変えることがあるので要注意
- 敬語は主語を特定する強力なヒントになる
- 尊敬語は動作主(主語)を高め、身分の高い人物に使われる
- 謙譲語は動作の受け手を高めることで敬意を示す
- 敬語の使われ方から登場人物の身分や関係性を推測できる
- 当時の風習や価値観といった古典常識も主語特定の助けになる
古文の勉強法、お疲れ様でした!
「よし、やるぞ!」と思っても、「でも、文法をゼロから体系的にやり直すのって、独学だと不安だなぁ…」と感じていませんか?
もし、あなたが「元・古文が苦手」だった先生から、センスに頼らない「論理的な解き方」を学びたいなら…
今、多くの受験生から「神授業」と呼ばれている「スタディサプリ 古文」を、私が徹底的に分析した記事がきっと役立つはずです。
なぜ岡本先生の授業がそこまで支持されるのか、ゼロから始める具体的な受講順番まで詳しく解説しています。
古文を「苦手」から「得意」に変える、その具体的な方法に興味がある方は、ぜひ覗いてみてくださいね。
→ 関連記事:スタディサプリ古文が神授業と言われる理由|ゼロから始める最適ルートも解説
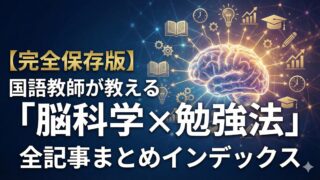

この記事を読んで、古文の理解がまた一つ深まりましたね。
でも、古文は「単語」「文法」「読解」「常識」など、全ての知識が有機的につながって初めて高得点が取れる科目です。
「次はどこを勉強すればいいの?」
「苦手なあの分野、どうやって対策しよう?」
そんな迷子にならないよう、ミチプラス内の古文記事を「勉強する順番」に整理した「完全攻略マップ」を作成しました。
辞書代わりにブックマークして、最短ルートで志望校合格を目指しましょう!