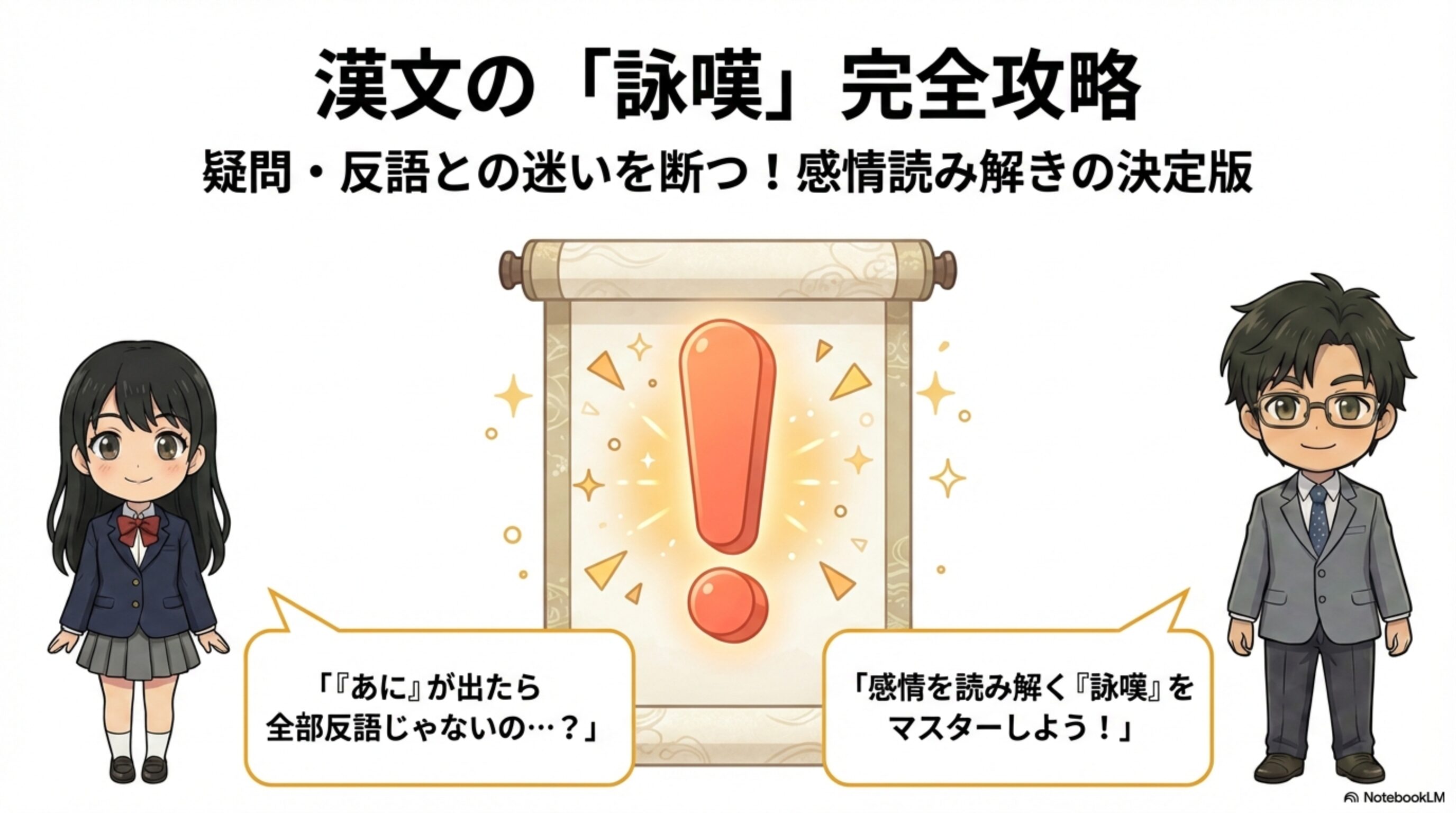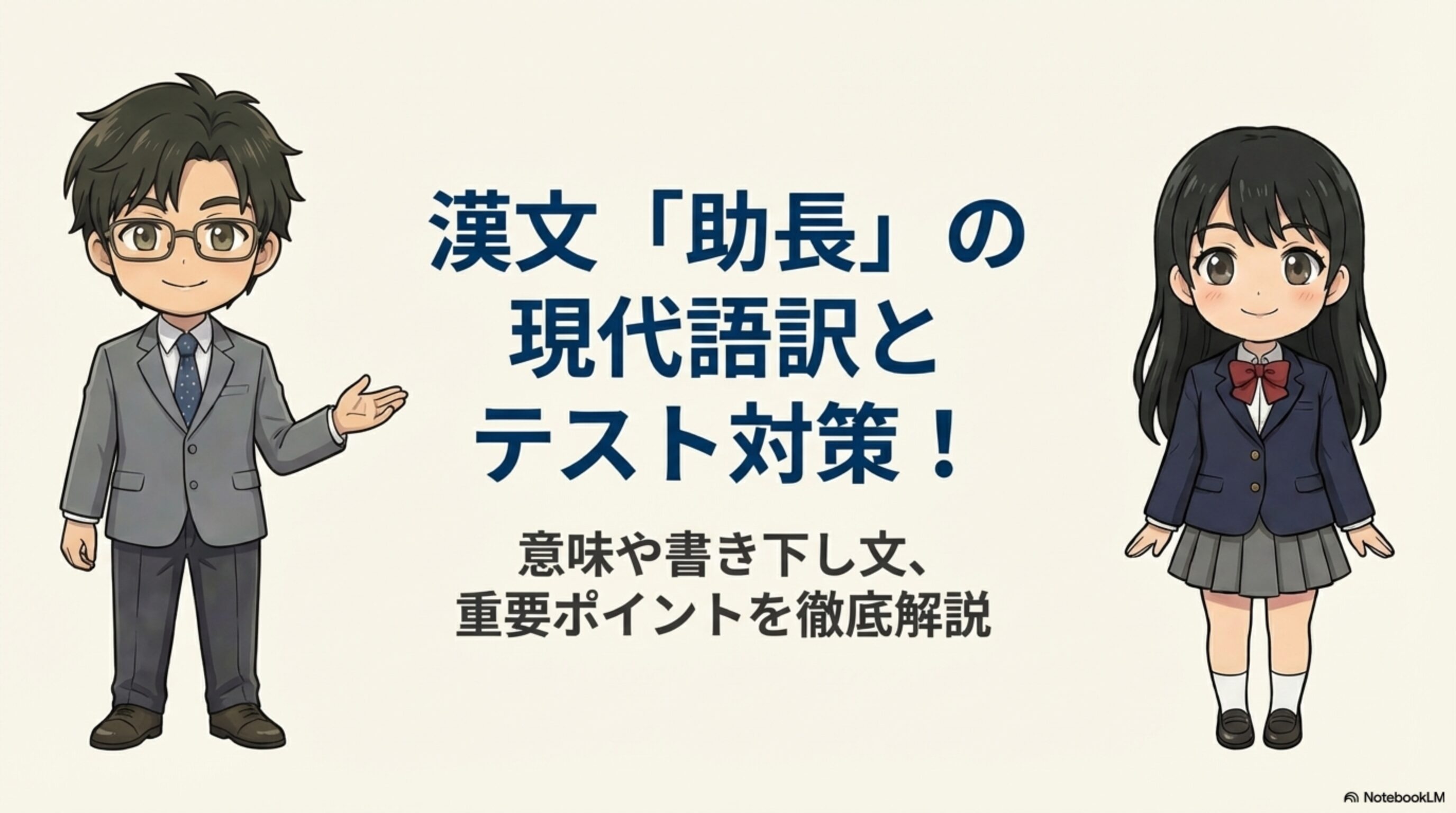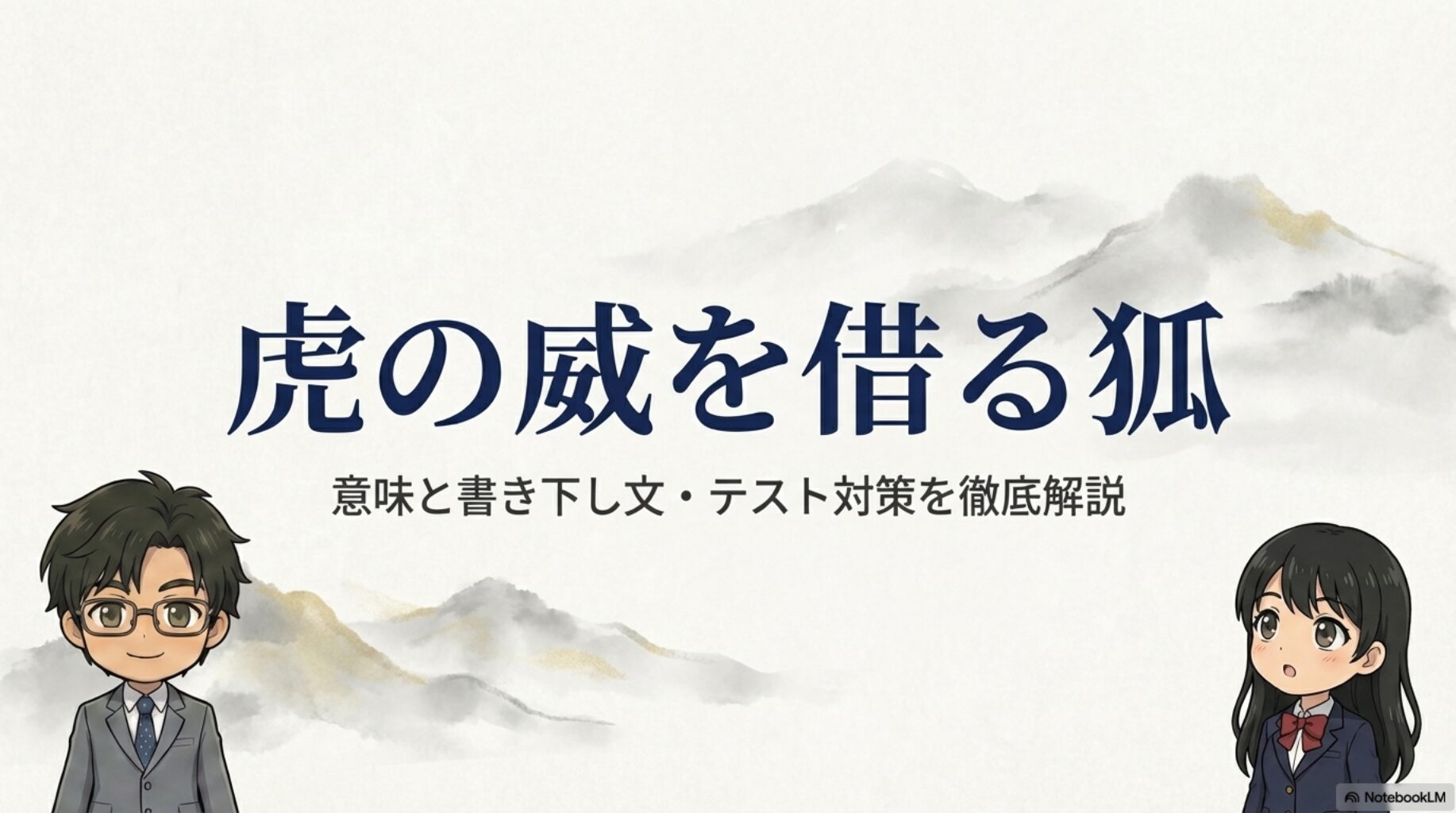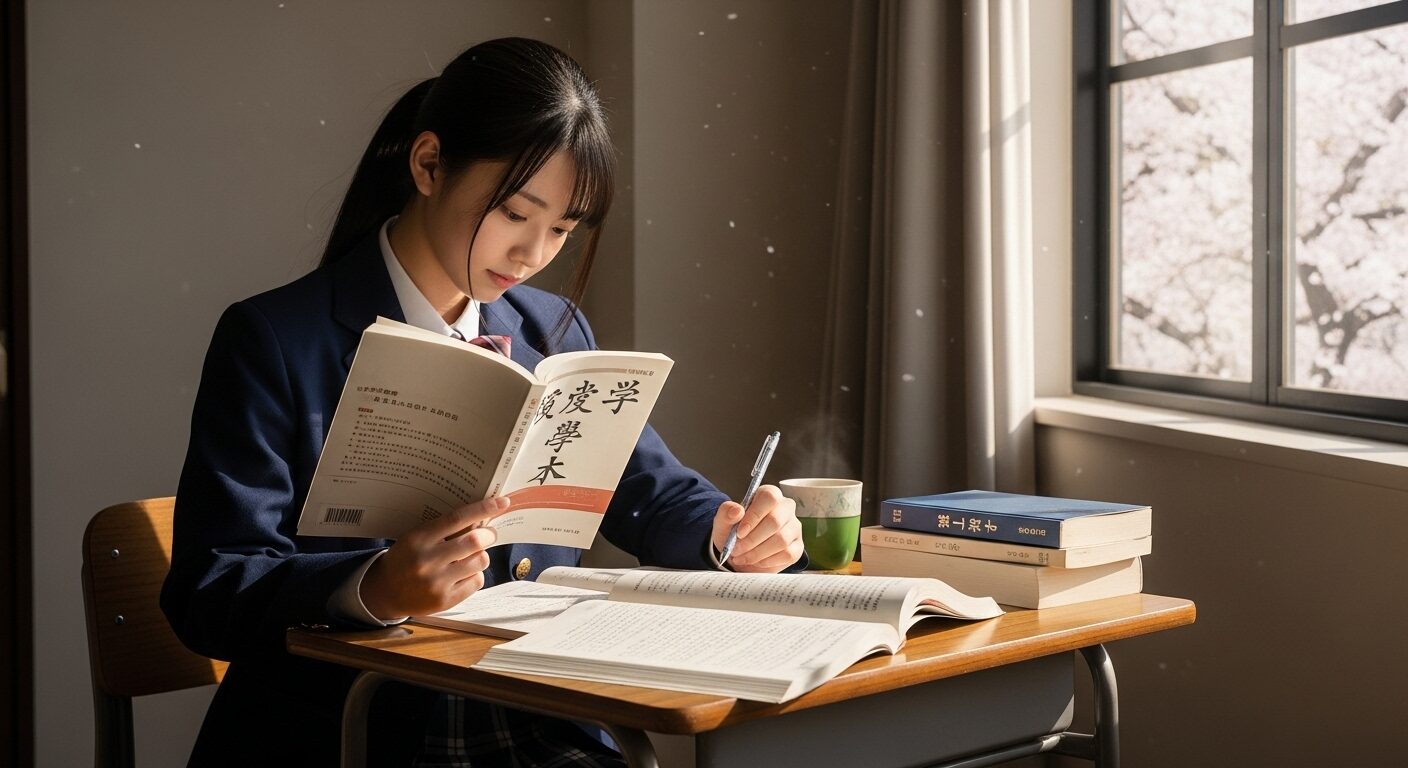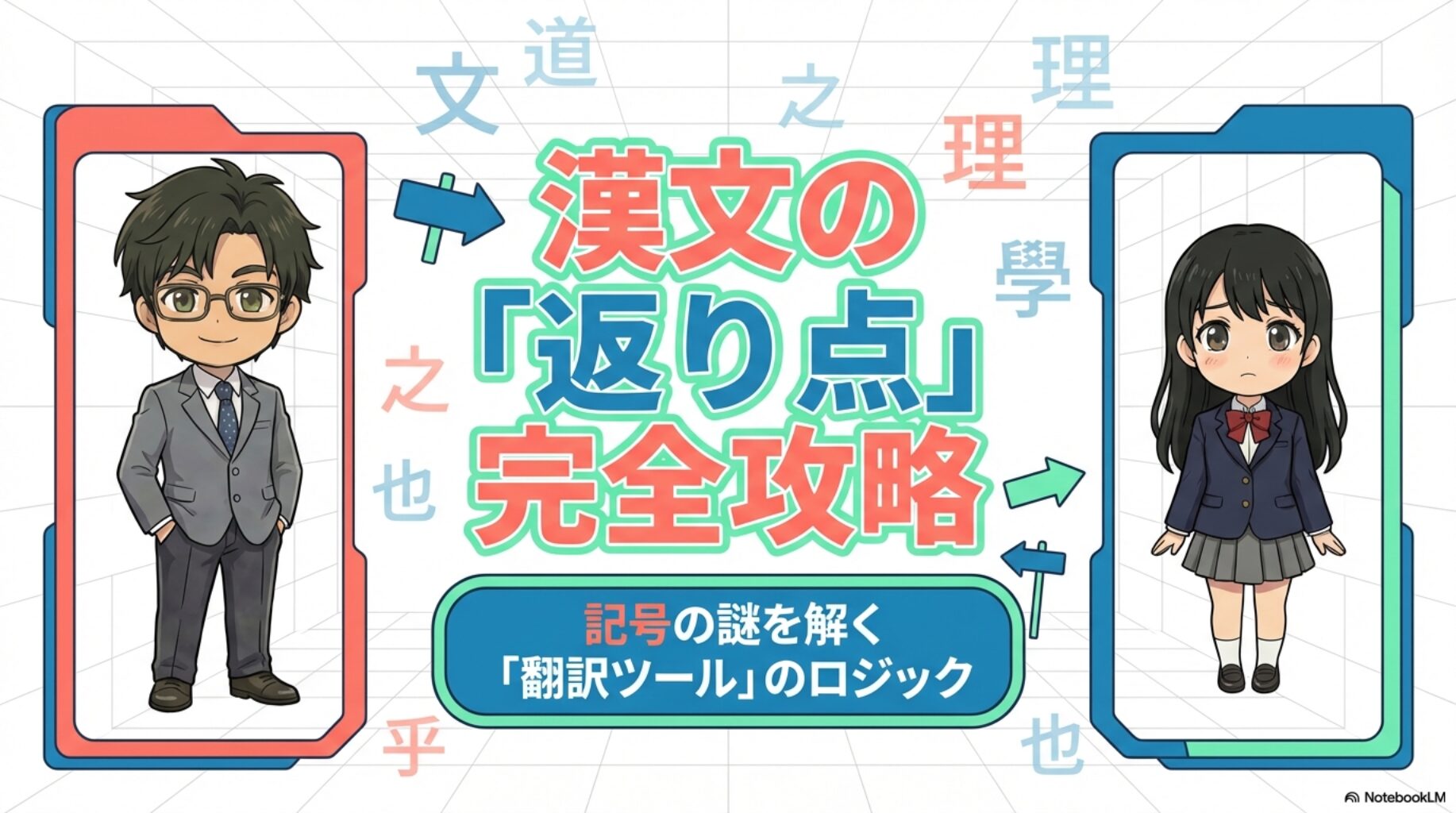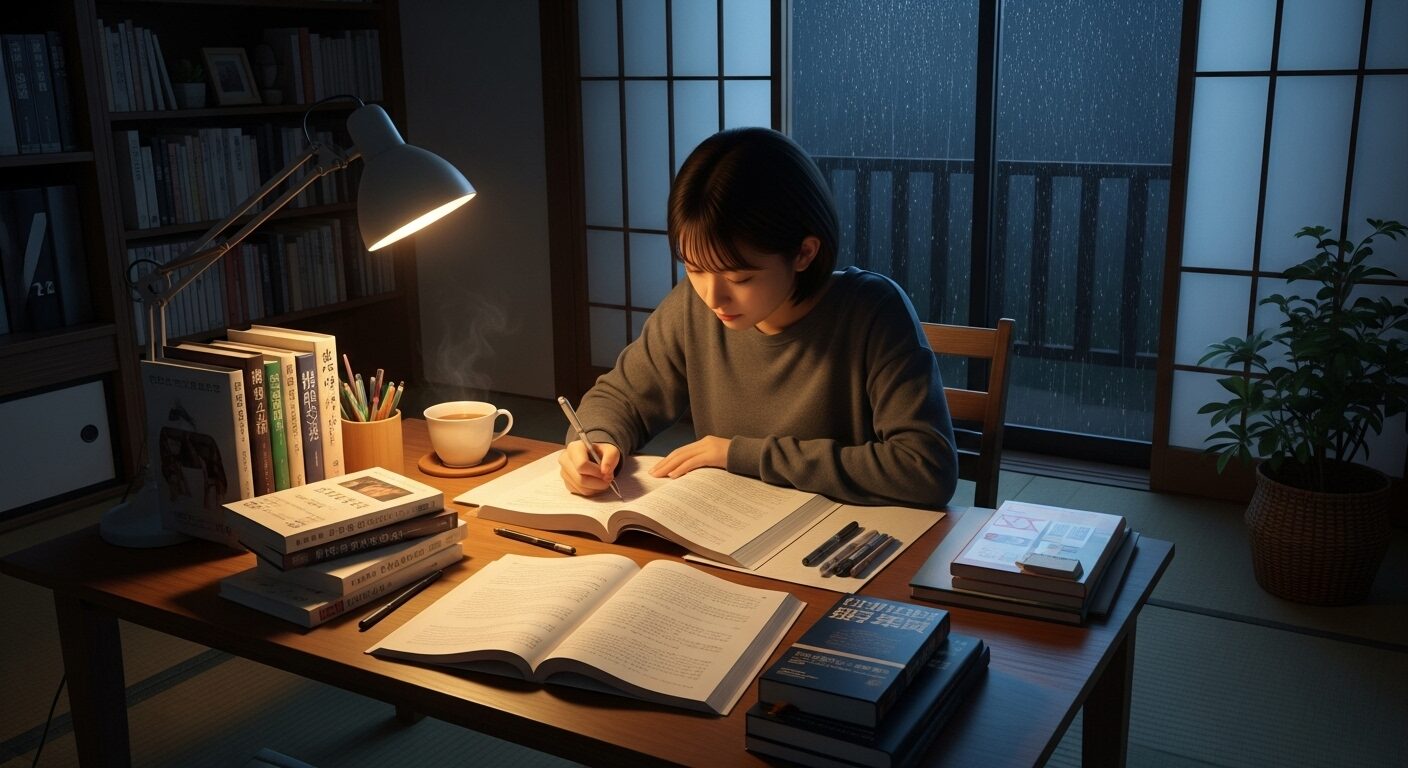漢文の置き字とは?一覧と読み方、見分け方を徹底解説
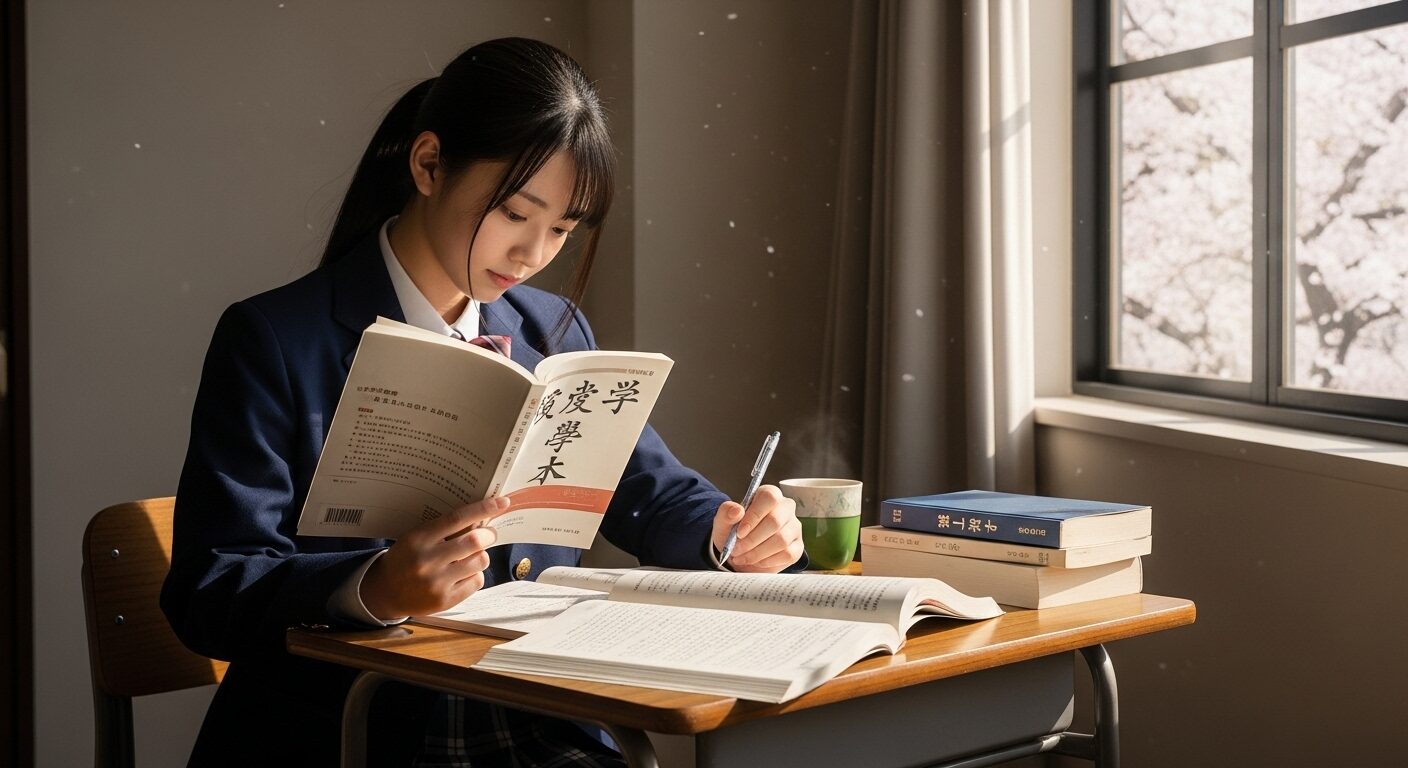
漢文の学習を進める中で、「置き字」という言葉を聞いて戸惑っていませんか?文章の中に漢字として存在しているにもかかわらず、訓読する際に読まない文字があるため、置き字の読み方や、置き字の書き下し文での扱い方に混乱してしまうのは当然のことです。
この記事では、まず主要な置き字の一覧を紹介し、それぞれの文字が持つ働きや簡単な見分け方を、具体的な例文を交えながら詳しく解説します。特に重要な接続詞の「而」や、場所・対象・比較などを示す「於・于・乎」、文末でニュアンスを加える「焉・矣」、詩などで語調を整える「兮」は、漢文読解の鍵となります。さらに、通常は読みますが、文脈によって置き字として扱われることがある「也」や「者」といった助字についても触れていきます。
この記事を最後まで読めば、なぜ置き字が読まれないのか、そして読まないながらもどのような重要な役割を果たしているのかが明確になり、漢文読解がよりスムーズになるはずです。
漢文の置き字とは?読み方と一覧
置き字の読み方の基本ルール

漢文の置き字に関する最も基本的なルールは、訓読(漢文を日本語の文法で読む)する際に、その文字を読まないというものです。これは漢文訓読という、日本独特の読解法から生まれました。
少し専門的な話になりますが、漢文(古代中国語)は、語順や「助字」と呼ばれる機能語によって文法的な関係を示す「孤立語」に分類されます。一方、日本語は「てにをは」といった助詞や動詞の活用語尾によって文法機能を示す「膠着語」です。
なぜ読まないのかというと、置き字が持っている文法的な働き(例えば、接続、場所、時間、比較、断定など)は、その置き字の前や後ろにある漢字に付ける「送り仮名」によって、すでに日本語として表現されているからです。送り仮名は、まさに日本語の助詞や活用語尾の役割を果たします。
例えば、「於」という置き字は場所を示す「~に」や「~で」という意味を持ちますが、これは「於」自体を読むのではなく、「於」の直後にある場所を示す語に「ニ」という送り仮名を付けることでその意味を反映させます。もとの中国語ではもちろん「於(yú)」と発音されていましたが、日本語の訓読という特殊な翻訳読法の中で、読みが省略されるようになったのです。
漢文の置き字は、日本の高等学校における国語教育(古典)の基礎であり、文部科学省の学習指導要領においても、漢文読解の重要な要素として位置づけられています。
ただし、注意点として、同じ漢字が常に置き字として使われるわけではありません。文脈によって、読まれる場合と読まれない(置き字になる)場合があるため、文法的な判断が不可欠です。
- 例1:「乎」が文中で場所を示す場合(例:志乎学)は置き字ですが、文末で疑問や反語を示す場合は「か」「や」と読まれます(例:不亦楽乎)。
- 例2:「而」が接続詞の場合は置き字ですが、二人称(あなた)を示す場合は「なんぢ」と読まれます(例:而忘其君乎)。
文の中での位置や役割によって、置き字になるかどうかが変わるため、パターン暗記ではなく文脈判断が重要です。
主要な置き字の一覧と働き

漢文の読解で頻繁に登場する主要な置き字は、実はそれほど多くありません。まずは代表的なものとその働きを、働きごとに分類して一覧で確認しましょう。これらは漢文の「助字」の一部であり、文法的な機能を持ちますが、訓読の際に読みが省略されるものです。
| 置き字 | 読み(参考) | 品詞的役割 | 主な働き(分類) | 日本語での処理 |
|---|---|---|---|---|
| 而 | ジ | 接続詞 | 接続(順接・逆接) | 直前の語に「~テ」「~ドモ」等の送り仮名を付ける |
| 於 | オ | 前置詞 | 場所・対象・比較・受身など | 直後の語に「~ニ」「~ヨリ」等の送り仮名を付ける |
| 于 | ウ | 前置詞 | 「於」とほぼ同じ機能 | 直後の語に「~ニ」「~ヨリ」等の送り仮名を付ける |
| 乎 | コ | 前置詞 | 「於」とほぼ同じ機能 | 直後の語に「~ニ」「~ヨリ」等の送り仮名を付ける |
| 矣 | イ | 終助詞(語気助詞) | 断定・完了・詠嘆 | 文末に「~なり」「~り」等の語気を添える |
| 焉 | エン | 終助詞(語気助詞) | 断定・完了・詠嘆 | 文末に「~なり」「~り」等の語気を添える |
| 兮 | ケイ | 間投助詞(語気助詞) | 語調を整える(詩などで使用) | 読まず、リズムを整える役割と理解する |
これらの置き字は、単なる飾りや省略可能な文字ではなく、文の構造を明確にしたり、微妙なニュアンスを加えたりするために必要不可欠な要素です。訓読の際は読みませんが、その存在と働きを意識することが、正確な読解につながります。

まずはこの7文字、特に接続詞の「而」、前置詞の「於」、終助詞の「矣」の3つを「読まない字の代表格」として認識することが、漢文読解の第一歩になりますよ。
置き字の書き下し文での処理方法
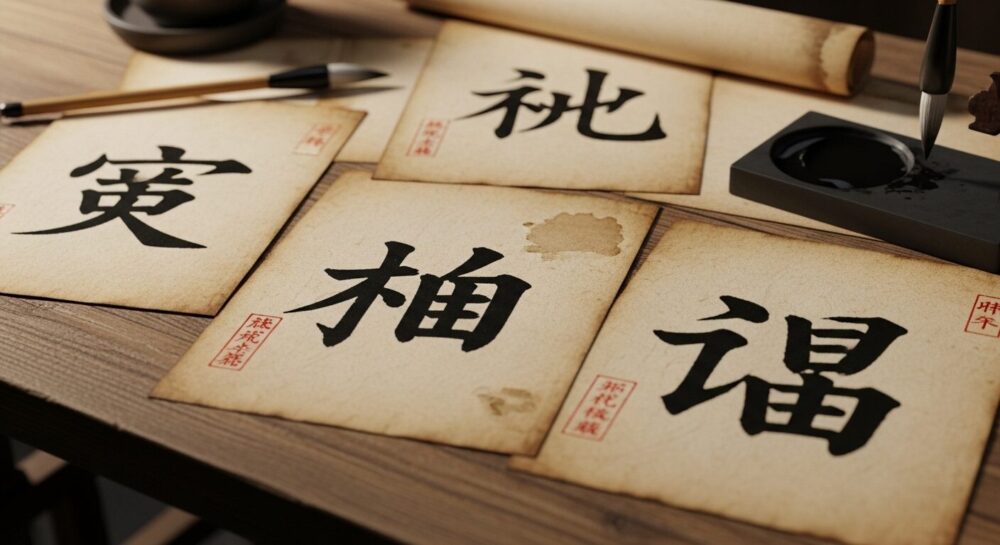
訓読の際に読まない置き字は、書き下し文(訓読したものを仮名交じり文で書き表したもの)にする際には、その文字を書きません。つまり、完全に省略されます。
これは、前述の通り、置き字の持つ文法的な意味や働きが、送り仮名や文末の活用語尾としてすでに日本語の文章に組み込まれているためです。もし置き字をそのまま書き下してしまうと、意味が重複したり、日本語として不自然な文章になったりしてしまいます。
具体例を見てみましょう。
白文: 学而時習之
訓読文: 学(まな)ビテ時(とき)ニ之(これ)ヲ習(なら)フ
書き下し文: 学びて時に之を習ふ
この例では、「而」という置き字が持っている順接(~して、そして)の意味が、直前の「学」に付けられた送り仮名「て」によって表現されています。そのため、書き下し文には「而」という漢字は登場しません。
もし仮に「而」を「しこうして(そして)」と読んでしまうと、「学びてしこうして時に之を習ふ」となり、非常に冗長で不自然な日本語になってしまいます。訓読では、このように日本語として自然な形になるよう、置き字の働きを送り仮名に吸収させるのです。
置き字の処理方法として、以下の2点を明確に覚えておきましょう。
- 訓読する際は、その存在を意識しつつも読まない。
- 書き下し文にする際は、その文字を書かない(省略する)。
置き字の簡単な見分け方
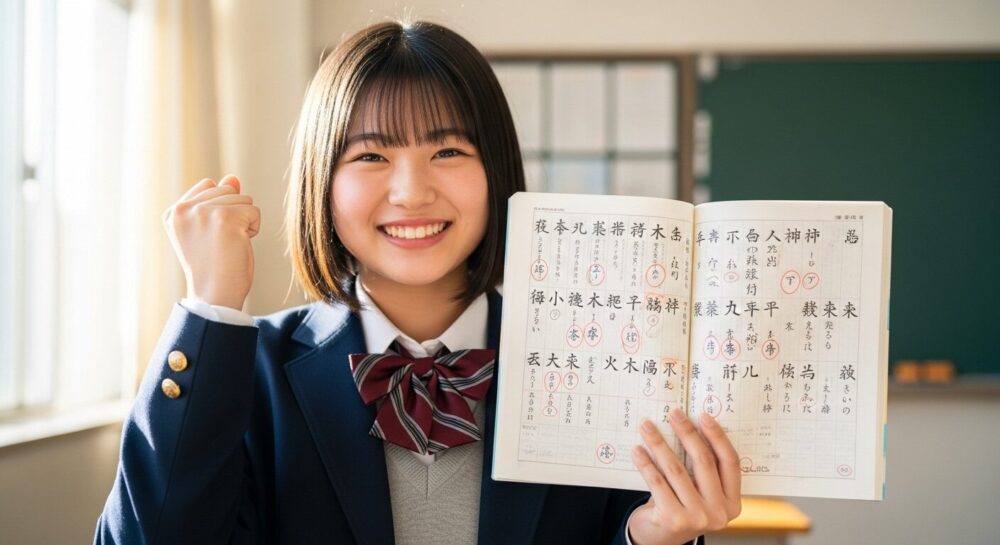
漢文を読み慣れていないと、どの字が置き字なのかを判断するのは難しいかもしれません。しかし、置き字を見分けるための非常に簡単な目安があります。
それは、返り点(レ点、一二点など)や送り仮名が、その漢字に何も付いていないことに注目する方法です。
置き字は訓読の際に読まないため、日本語の語順に合わせて読む順番を変える必要がありません。したがって、返り点の対象になることは基本的にありません。また、読み方がないため、送り仮名が付くこともありません。
例えば、「霜葉紅於二月花」(霜葉は二月の花よりも紅なり)という有名な一節があります。この文で、「於」という字には返り点も送り仮名も一切付いていません。「於」の前にある「紅」と、後ろにある「二月花」には「ヨリモ」という返り点(レ点)と送り仮名が付きますが、「於」自体は素通りされています。これが、「於」がこの文脈で置き字として使われていることの強い根拠となります。
ただし、この見分け方は非常に有効ですが、万能ではありません。注意点も理解しておきましょう。
- 文脈によっては、置き字ではない字(例:動詞)にたまたま返り点や送り仮名が付かないケースもあります(例:漢詩などで「人見鳥〇〇」→「人見る鳥〇〇」と倒置で読む場合、「見」には訓点が付かない)。
- 逆に、置き字の代表格である「而」や「乎」が、置き字ではない用法(例:「而」=なんぢ、「乎」=かな)で使われる場合は、読まれるため訓点(送り仮名や返り点)が付きます。
あくまで「置き字である可能性が非常に高いサイン」として活用し、最後は文脈と、その漢字が持つ基本的な用法(接続詞、前置詞、終助詞など)の知識を組み合わせて判断することが大切です。
例文で理解する置き字の役割
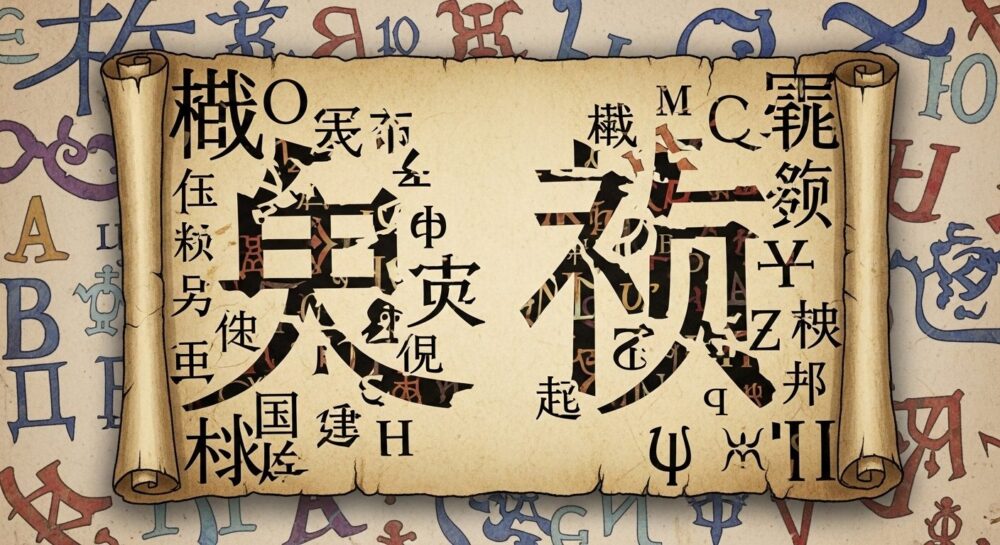
ここでは、置き字が実際の漢文(白文)の中でどのように機能しているのか、簡単な例文を通してその役割を確認してみましょう。置き字が「読まれない」からといって「意味がない」わけではないことがよく分かります。
1. 「而」(接続)
- 白文: 温故而知新
- 書き下し文: 故(ふる)きを温(たず)ねて新しきを知る。
- 役割: 「而」が順接(~して)の接続詞として働き、前の「温」に送り仮名「て」を付けさせています。もし「而」がなければ「温故知新」となり、「古いことを温め、新しいことを知る」という並列的な意味合いが強くなりますが、「而」があることで「古いことを温めた結果として新しいことを知る」という連続性・因果関係がより明確になります。
- 出典: これは『論語』為政篇の一節として非常に有名です。
2. 「於」(場所・対象)
- 白文: 釣於濮水
- 書き下し文: 濮水(ぼくすい)に釣る。
- 役割: 「於」が場所(~で)を示す前置詞として働き、直後の「濮水」に送り仮名「に」を付けさせています。「釣濮水」でも意味は通じますが、「於」を置くことで「濮水において」という動作の場所を明確に示す、より整った文になります。
3. 「矣」(断定・強調)
- 白文: 可矣
- 書き下し文: 可なり。
- 役割: 「矣」が文末で断定・強調の語気を添えています。「可」だけでも「可(か)なり」と読めますが、「矣」を添えることで「それでよいのだ」「間違いない」という強い断定や、詠嘆のニュアンスが加わります。
このように、置き字は読まれなくても、送り仮名や文末のニュアンスとして、確かに文の意味を支えていることがわかります。置き字は、漢文を日本語として自然に読むための「縁の下の力持ち」と言えるでしょう。
文脈で変わる漢文の置き字の働き
接続詞の働きを持つ「而」

「而(ジ)」は、置き字の中でも特に重要な字の一つで、文や句をつなぐ接続詞の働きをします。文脈に応じて「順接」「逆接」「並列」といった複数の機能を持つため、その見分け方が読解の鍵となります。
1. 順接(~テ・~シテ)
前の内容を受けて、後の内容に素直につなげる働きです。「そして」「~して」と訳されます。最も基本的な用法です。
- 例文: 学而時習之
- 書き下し文: 学びて時に之を習ふ。
- 見分け方: 直前に読む漢字の送り仮名が「~テ」や「~シテ」となっている場合、順接の働きをしています。
2. 逆接(~ドモ)
前の内容とは反対、あるいは予想に反する内容を後につなげる働きです。「しかし」「~だけれども」と訳されます。
- 例文: 子欲養而親不待
- 書き下し文: 子養はんと欲すれども親待たず。
- 見分け方: 直前に読む漢字の送り仮名が「~ドモ」となっている場合、逆接の働きをしています。文脈から明らかに前後が対立している場合も逆接と判断できます。
3. 並列(~シテ・~ニシテ)
前後が対等な関係で並んでいることを示します。「~であり、かつ~である」と訳されます。
- 例文: 温厚而謙虚
- 書き下し文: 温厚にして謙虚なり。
- 見分け方: 形容詞や名詞など、文法的に対等な語句が「而」の前後で結ばれている場合に多く見られます。
【重要】置き字ではない「而」
「而」が置き字にならない、つまり読まれる用法として、二人称の代名詞「なんぢ」(あなた)があります。これは文の主語や目的語として使われます。
- 例文: 而忘其君乎
- 書き下し文: なんぢ其の君を忘るるか。
- 解説: この「而」は文頭で主語として機能しているため、「あなた」という意味の「なんぢ」と読みます。接続詞として文中に置かれる置き字の用法とは、文脈や位置で明確に区別できます。
前置詞の働きをする「於・于・乎」
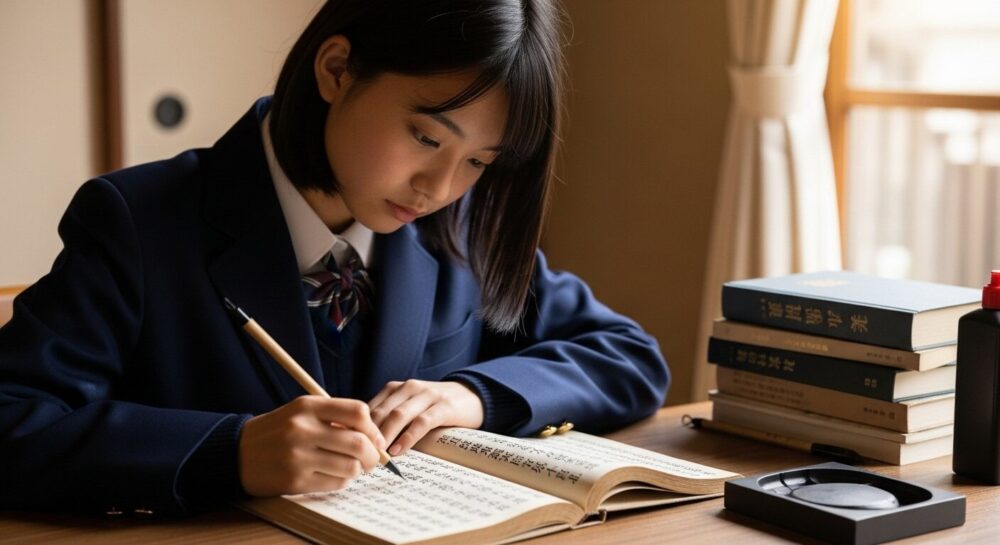
「於(オ)」「于(ウ)」「乎(コ)」の3つの漢字は、多くの場合、文中に置かれて英語の前置詞(at, in, from, thanなど)と非常によく似た働きをします。これら自体は読みませんが、直後の語に特定の送り仮名を付けさせることで、その機能を示します。「于」と「乎」は、「於」とほぼ同じ機能を持つと考えて差し支えありません。
どの働きをするかは、文脈と送り仮名によって判断します。
| 主な働き | 送り仮名(直後の語) | 例文(書き下し文) | 白文(参考) | 解説 |
|---|---|---|---|---|
| 場所・対象・状況 | 「~に」「~を」 | 吾十有五にして学に志す | 志乎学 | 動作の場所(~で)や、対象(~に)を示します。 |
| 動作の起点 | 「~より」 | 千里の行も足下より始まる | 始於足下 | 動作が始まる場所や時間(~から)を示します。 |
| 比較 | 「~より(も)」 | 苛政は虎よりも猛なり | 猛於虎 | 比較の基準(~よりも)を示します。述語が形容詞であることが多いです。 |
| 受身 | 「~に」(~る・らる) | 斉に重んぜらる | 重於斉 | 受身の動作主(~によって)を示します。「~ニ~ル(ラル)」の形で使われます。 |
【重要】置き字ではない「乎」
「乎」は、文中に置かれれば置き字(前置詞)ですが、文末に置かれると置き字ではなく、読まれます。これは非常に重要な区別です。
- 疑問・反語: 「~か」「~や」と読む。
(例:不亦楽乎 → 亦た楽しからずや。) - 詠嘆: 「~かな」と読む。
(例:大道之行乎 → 大道の行はるるかな。)
文中の「乎」は置き字、文末の「乎」は読む、と覚えましょう。
文末の「焉・矣」が示す意味
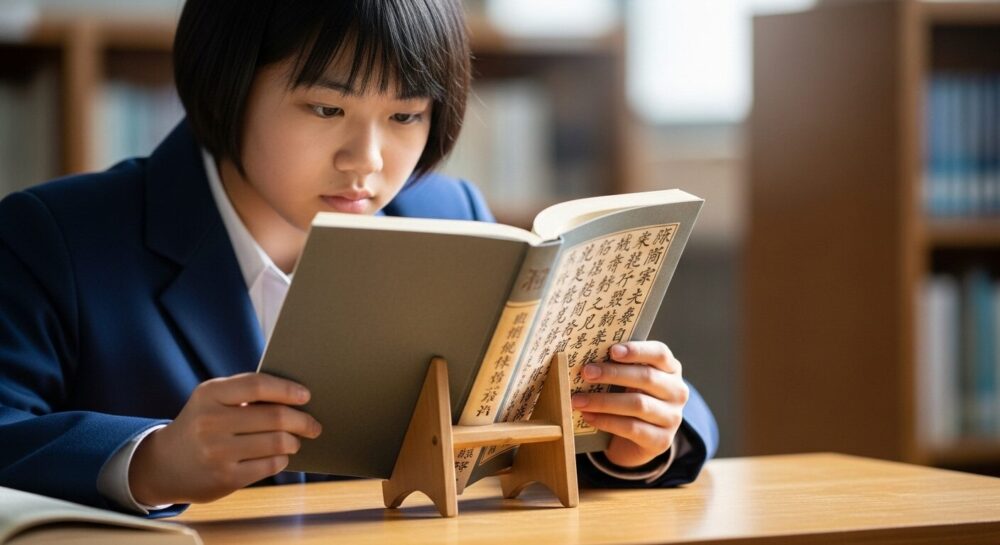
「焉(エン)」と「矣(イ)」は、主に文末に置かれ、それ自体は読まないものの、文全体の語調を強めたり、微妙なニュアンスを加えたりする働きをします。日本語の終助詞(~だよ、~だなあ、~してしまった)に近い感覚ですが、置き字として処理されます。
「矣(イ)」の働き
文末で断定(~である)、完了(~してしまった)、詠嘆・強調(~だなあ)などの意味を添えます。どの意味になるかは、文脈や直前の語の活用形で判断します。「矣」は、主観的な強い断定や詠嘆を表す傾向があります。
- 例文(断定): 朝に道を聞かば、夕べに死すとも可なり。(可矣)
- 例文(完了): 舟は已に行けり。(舟已行矣)
- 例文(強い意志): 千万人と雖も、吾往かん。(吾往矣)
「焉(エン)」の働き
「矣」と非常によく似ており、文末で断定(~なり)や完了(~せり)などの語気を強めます。「矣」に比べると、やや客観的な事実の断定や、文末の語調を軽く整えるために使われることもあります。
- 例文(完了): 聞く者皆感嘆せり。(聞者皆感嘆焉)
- 例文(断定): 蓋し一歳の死を犯す者二たびなり。(~者二焉)
【重要】置き字ではない「焉」
「焉」も置き字以外の重要な用法が多い字です。文末以外で使われる場合は特に注意が必要です。
- 疑問・反語(いづクンゾ): 「どうして~か、いや~ない」
(例:焉知死 → いづクンゾ死を知らん。) - 代名詞(これ・そこ): 「これ(に・を)」「そこ(に・で)」
(例:在焉 → これに在り。)
文末にある「焉」は置き字、文頭や文中にある「焉」は疑問詞や代名詞、と見分けるのが基本です。
語調を整える「兮」の役割

「兮(ケイ)」は、これまで説明した他の置き字とは少し性質が異なります。
この字は、主に詩や歌(韻文)、特に戦国時代の楚の国の歌謡(楚辞)や、漢代の「賦」などで多用されます。文法的な意味(接続や場所など)を持つというよりは、句の途中や句の終わりで、リズムや語調を整えるために挿入される文字です。日本語の歌でいう「ヨイショ」や「ああ」といった合いの手のような役割(間投助詞)と考えると分かりやすいでしょう。
- 例文: 力抜山兮 気蓋世
- 書き下し文: 力は山を抜き 気は世を蓋(おほ)ふ。
- 役割: これは項羽が詠んだとされる有名な「垓下の歌」の一節です。「兮」は「力抜山」という句と「気蓋世」という句の間で、語調を整え、詠嘆の気分を高めるためだけに使われています。そのため、訓読でも書き下し文でも完全に無視(省略)されます。
漢文、特に詩を読んでいるときに「兮」が出てきたら、「ああ、ここでリズムを整えているんだな」「これは楚辞系統の詩だな」と理解し、訓読や書き下しではシンプルに読まず、書かないで問題ありません。
置き字になる「也」と「者」

「也」や「者」は、通常「~なり(断定)」「~か・~や(疑問・反語)」「もの(人・こと)」と読む、漢文の超重要単語です。しかし、特定の文脈において、これらも置き字として読まないで処理されることがあります。これは少し発展的な内容ですが、知っておくと読解の幅が広がります。
置き字になる「也(ヤ)」
「也」は通常、文末に置かれて断定(~なり)や疑問・反語(~か、~や)として読まれます。しかし、文の途中に挿入されることがあります。この場合、文のリズムを整えたり、軽い強調を示したりするだけで、日本語の読点「、」のような役割を果たし、特に読まない(置き字とする)ことが多いです。
- 例文: 夫也、必知其所止。
- 書き下し文: 夫(そ)れ、必ず其の止まる所を知る。
- 解説: この文頭の「夫也」はセットで「そもそも、」という発語の役割を果たし、「也」自体は読みません。
また、文末にあっても、直前が命令形(~こと無かれ)などの場合、断定の「なり」と読まず、単に語気を強める置き字として処理することもあります。(例:無也 → 無かれ。)
置き字になる「者(シャ)」
「者」は通常「もの(人・こと)」と読みますが、文頭で「A者、B也」(AはBである)という形で使われる場合、「Aは」という主題(テーマ)を示す働きをします。この「~は」という意味が日本語の助詞として処理されるため、「者」自体は読まない(置き字とする)ことがあります。
- 例文: 兵者、凶器也。
- 書き下し文: 兵は、凶器なり。
- 解説: 「兵者」で「兵は」と読み、「者」の字は書き下し文に現れません。これは「知者」(知る者)のように「~するもの」と訳す用法とは明確に区別されます。
「也」や「者」が置き字になるケースは、少し発展的な内容です。まずは「而・於・矣」といった基本的な置き字をしっかりマスターしてから、これらの例外的な用法に取り組むと、混乱せずに学習を進められますよ。
置き字の練習問題

ここまでの内容を理解できたか、簡単な練習問題で確認してみましょう。各問題の後に解答と解説があります。しばらく考えてみてから、解答と解説を見てみてください。
【問題1】
次の(ア)~(オ)の漢字のうち、置き字として使われることがないものを一つ選んでください。
(ア)而 (イ)於 (ウ)矣 (エ)兮 (オ)不
【解答1】(オ)不
【解説】
(ア)「而」、(イ)「於」、(ウ)「矣」、(エ)「兮」は、すべてこの記事で紹介した代表的な置き字です。
(オ)「不」は「~ず」と読む否定の助動詞であり、必ず読んで書き下します。したがって置き字ではありません。
【問題2】
「視而不見」という白文について、送り仮名と書き下し文の組み合わせとして正しいものを一つ選んでください。
(ア)視レドモ而見ず → 視れども而して見ず
(イ)視レドモ而不レ見 → 視れども見ず
(ウ)視テ而不(ず)レ見 → 視て見ず
(エ)視ル而(ども)不(ず)レ見 → 視るども見ず
【解答2】(イ)
【解説】
「視(見る)」と「不見(見えない)」は逆の内容です。したがって、「而」は逆接の接続詞として働きます。この場合、「而」の直前に読む「視」に「ドモ」という送り仮名を付け、「而」自体は置き字として読みません。よって、書き下し文は「視れども見ず」となります。
【問題3】
「苛政猛於虎也」という白文について、「於」の働きとして最も適切なものを一つ選んでください。
(ア)場所(~で)
(イ)対象(~に)
(ウ)比較(~よりも)
(エ)受身(~によって)
【解答3】(ウ)比較
【解説】
この文は「苛政(かせい)」と「虎」の「猛(たけ)さ」を比べています。「於」は比較の基準を示し、直後の「虎」に「ヨリモ」という送り仮名を付けさせます。書き下し文は「苛政は虎よりも猛なり」となり、「於」は比較(~よりも)の働きをしています。
【問題4】
「舟已行矣」という白文を書き下し文にする場合、「矣」はどのように処理するのが最も適切ですか。
(ア)「矣(かな)」と書き下す。
(イ)「矣(なり)」と書き下す。
(ウ)「矣(けり)」と書き下す。
(エ)書き下さず、省略する。
【解答4】(エ)書き下さず、省略する。
【解説】
「矣」は文末の語気を強める置き字です。この文では「已(すで)ニ」という副詞があることから、動作の完了(~してしまった)を示していると判断できます。訓読する際は、直前の「行」に完了の助動詞「けり」を付けて「行けり」と読みますが、「矣」の文字自体は書き下し文には書きません(省略します)。
【問題5】
次の(ア)~(ウ)の文のうち、下線部の漢字が置き字ではないものを一つ選んでください。
(ア)不亦楽乎。
(イ)志乎学。
(ウ)力抜山兮気蓋世。
【解答5】(ア)
【解説】
(イ)「乎」は文中にあり「学に志す」の「に」の働きをする前置詞(置き字)です。
(ウ)「兮」は詩の語調を整える置き字です。
(ア)「乎」は文末にあり、「亦た楽しからずや」と読みます。これは疑問・反語(~ではないか)の終助詞であり、置き字ではありません。
まとめ:漢文 置き字の学習ポイント
漢文の置き字は、「読まない字」として単純に無視してよいものではありません。それどころか、文の構造を支え、意味を正確に伝達するために不可欠な働きをしています。最後に、漢文の置き字を学習する上での重要なポイントをまとめます。
- 置き字は訓読では読まず、書き下し文では省略する
- 置き字の働きは前後の漢字に付ける送り仮名に反映される
- 返り点や送り仮名が何も付かないのが置き字の簡単な見分け方
- 「而」は順接(~て)と逆接(~ども)の接続詞の働きが重要
- 「於・于・乎」は場所・対象・比較など前置詞の働きを持つ
- 「於・于・乎」は直後の語の送り仮名(~に、~より等)で意味を判断する
- 「焉・矣」は文末に置かれ、断定や完了、詠嘆の語気を強める
- 「兮」は主に詩で使われ、リズムを整える役割を持つ
- 「也」や「者」も文脈によっては置き字として扱われることがある
- 同じ漢字でも置き字でない用法(例:乎=か、焉=いづクンゾ、而=なんぢ)に注意する
- 置き字の用法は、文中の位置(文中か、文末か)で見分けることが多い
- まずは主要な置き字(而・於・矣・焉)から覚えるのが効率的
- 置き字を意識することで、文の構造や関係性が見えやすくなる
- 置き字のパターンを暗記するだけでなく、多くの例文を通じて文脈で判断する習慣をつける
- 読まない字が持つ「意味」を理解することが漢文読解力アップの鍵