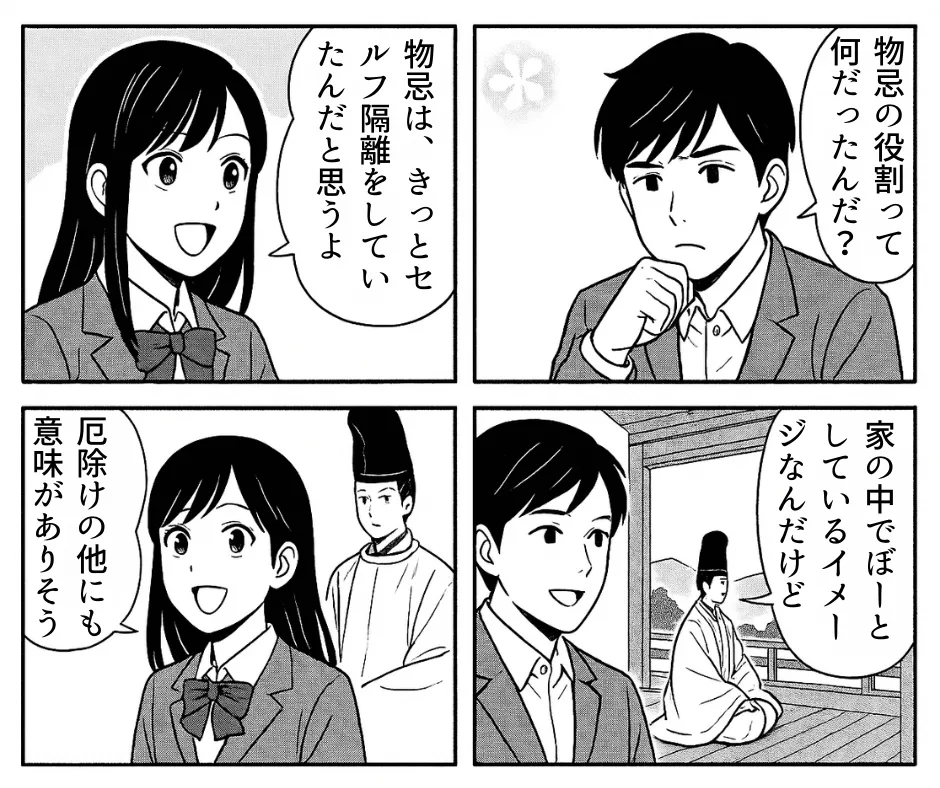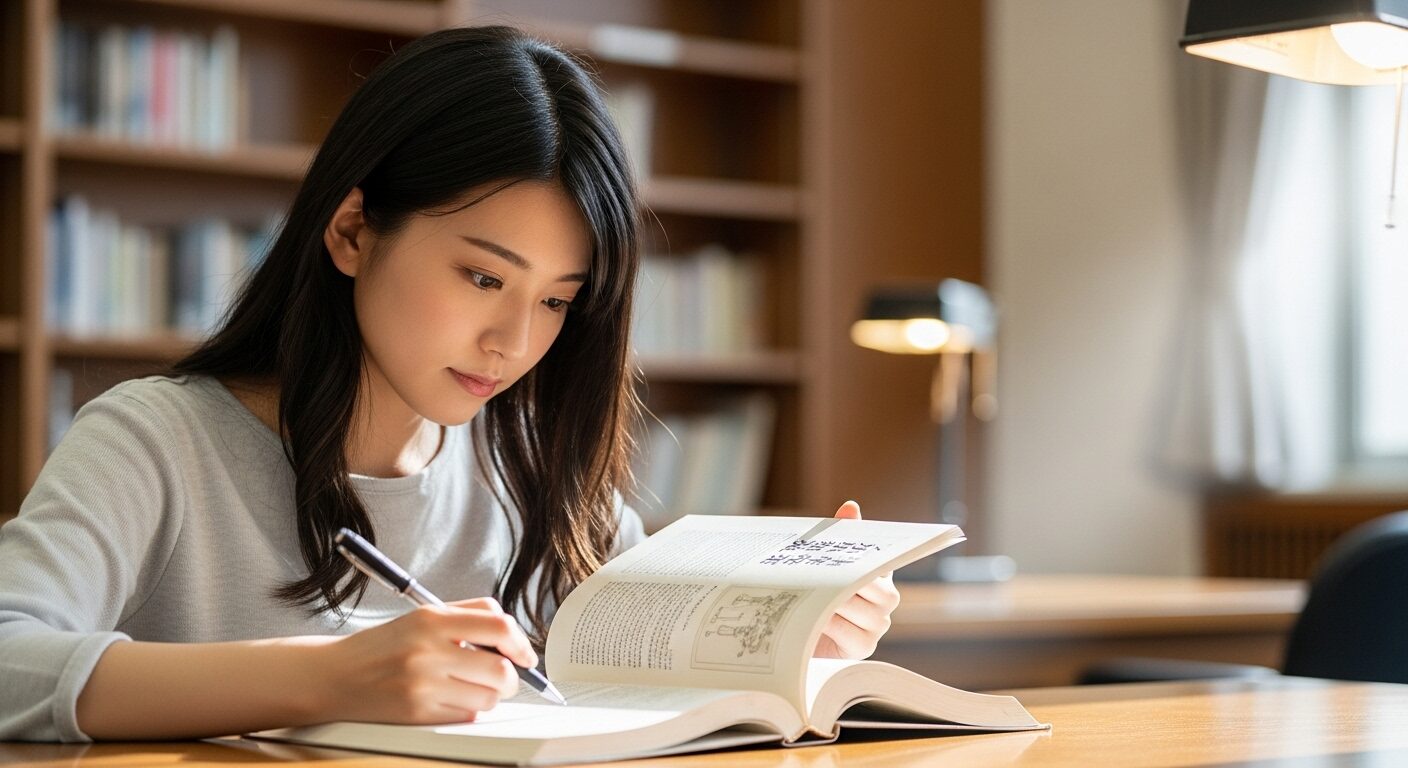古文の助動詞「じ」意味の見分け方と活用を徹底解説【練習問題付】

古文の学習を進める中で、助動詞 「じ」について「意味がよく分からない」「どうやって見分けるの?」と疑問に思っている方はいませんか?この助動詞は古文読解において重要な役割を果たしますが、いくつかのポイントを押さえれば決して難しくありません。
この記事では、そんな助動詞 「じ」について、基本的な意味から解説を始め、文中でどのように使われるかを示す接続のルール、そして非常にシンプルな活用表まで、一つひとつ丁寧に解説していきます。
特に多くの学習者が悩む「意味の見分け方」に関しては、具体的な例文と共に詳しく説明し、スッキリ解消します。他の活用語で論点となる本活用と補助活用の違いのような複雑な活用はありませんが、似ている助動詞「まじ」との違いもしっかり整理します。
さらに、知識の定着を図るための短文練習問題、そして実際の読解力を養う長文練習問題も用意しています。この記事を通して、助動詞「じ」への理解を深め、古文の世界をより深く味わうための一歩を踏み出しましょう。
- 助動詞「じ」の二つの意味(打消推量・打消意志)とその見分け方
- 助動詞「じ」の活用が特殊型(無変化)であること
- 助動詞「じ」が動詞などの未然形に接続するルール
- 助動詞「じ」と「む」や「まじ」との関係性および相違点
古文の助動詞「じ」の基本を解説
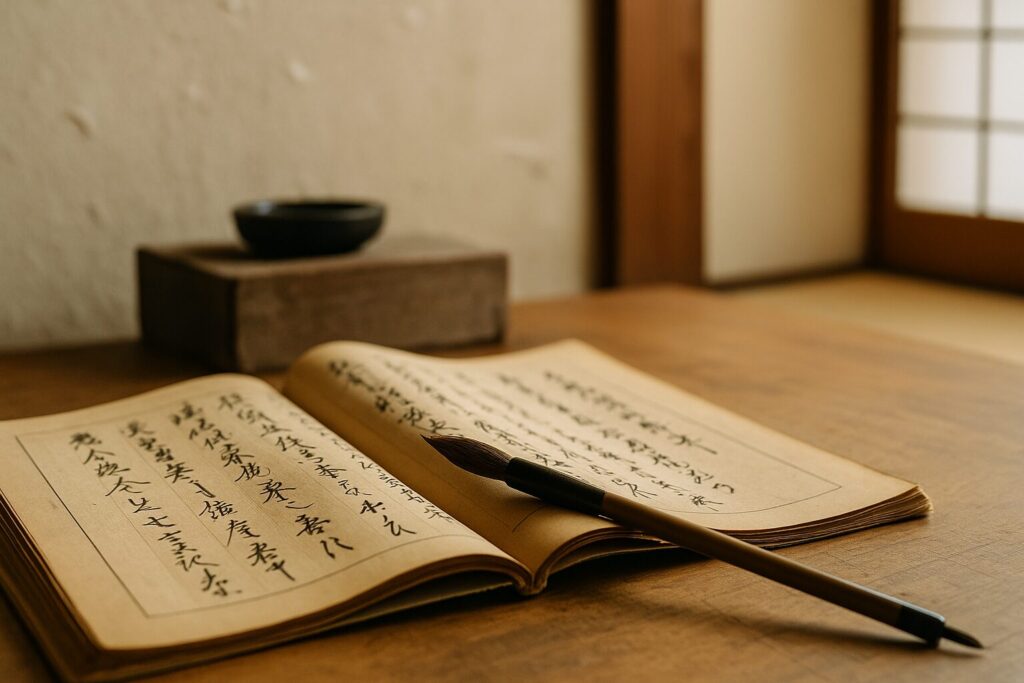
古文の学習で登場する助動詞「じ」について、基本的な知識をわかりやすく解説します。この記事を読むことで、助動詞「じ」の役割、形、そして似ている助動詞との違いが理解できるでしょう。
- まずはここから!助動詞「じ」とは?
- 助動詞「じ」がつく前の形:接続ルール
- 変化しない?助動詞「じ」の活用表
- 「む」の打ち消しと覚えるのがコツ
- 助動詞「じ」と「まじ」の違いは?
まずはここから!助動詞「じ」とは?
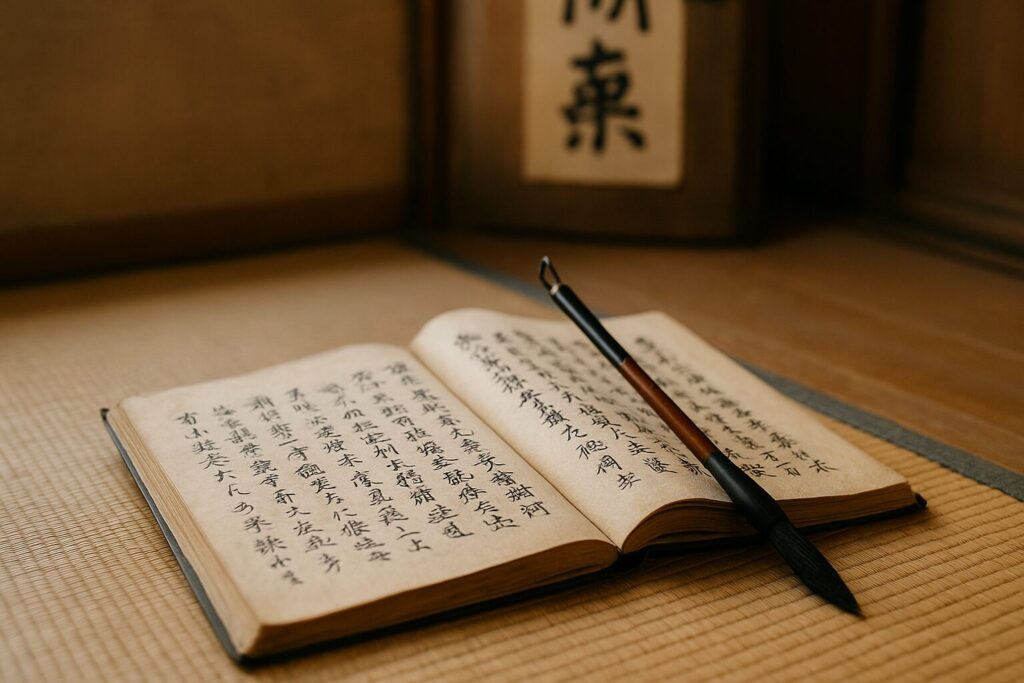
助動詞「じ」は、古文の中で主に打ち消しの推量(~ないだろう)や打ち消しの意志(~ないつもりだ・~まい)を表す言葉です。
現代語の「~まい」に近いニュアンスを持っています。
古文には多くの助動詞がありますが、「じ」は推量や意志を表す助動詞「む」と対になる関係にあります。
「む」が肯定的な推量や意志を示すのに対し、「じ」はその否定形と考えると理解しやすくなります。例えば、「行かむ」が「行こう・行くだろう」という意味になるのに対し、「行かじ」は「行くまい・行かないだろう」という意味合いを持ちます。
このように、「じ」は何かを否定的に推測したり、何かをしないという意志を示したりする際に用いられる重要な助動詞です。
助動詞「じ」がつく前の形:接続ルール

助動詞「じ」は、どのような言葉に接続するのでしょうか。これは非常にシンプルで、助動詞「じ」は活用する語の「未然形」に接続します。
未然形とは、動詞や形容詞などがまだその動作や状態が実現していない形を指します。 例えば、動詞「行く」の未然形は「行か」です。これに「じ」が付くと「行かじ」となります。
同じように、動詞「見る」の未然形は「見」なので、「見じ」となります。サ変動詞「す」であれば未然形は「せ」なので「せじ」となります。
この接続ルールは「じ」を理解する上で基本となりますので、必ず覚えておきましょう。未然形に接続するという点を押さえておけば、文章中で「じ」を見つけたときに、その直前の語が未然形であると判断する助けにもなります。
変化しない?助動詞「じ」の活用表

助動詞「じ」の活用は「特殊型」あるいは「無変化型」と呼ばれ、非常にシンプルです。多くの助動詞が文脈に応じて形を変えるのに対し、「じ」は基本的に形を変えません。
以下に活用表を示します。
| 活用の種類 | 未然形 | 連用形 | 終止形 | 連体形 | 已然形 | 命令形 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| じ (特殊型) | (なし) | (なし) | じ | じ | じ | (なし) |
表を見てわかる通り、未然形、連用形、命令形は存在しません。
文中ではほとんどの場合、終止形か連体形の「じ」の形で現れます。
已然形の「じ」も存在しますが、これは係り結びの法則で文末が已然形になる場合に限られ、主に室町時代以降の用例で見られる程度です。
活用を覚える負担が少ない点は、助動詞「じ」の学習しやすいポイントと言えるでしょう。
「む」の打ち消しと覚えるのがコツ
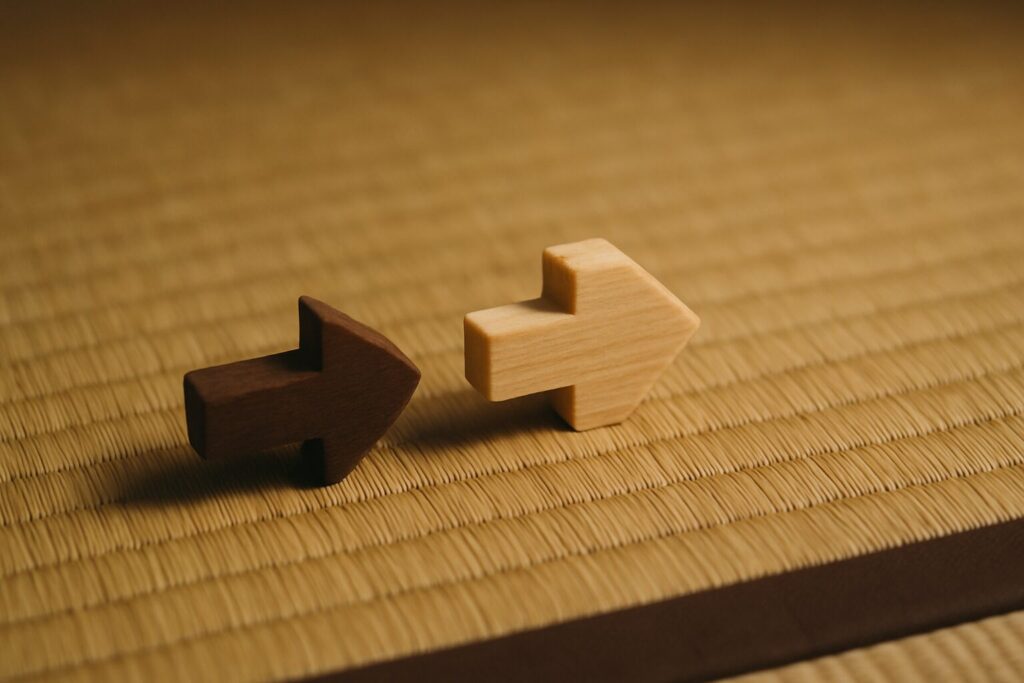
助動詞「じ」の意味を覚える上で最も効果的な方法は、助動詞「む」(または「むず」)の打ち消しと捉えることです。
助動詞「む」には、推量(~だろう)、意志(~しよう)、適当・勧誘(~がよい・~しないか)、仮定(~としたら)、婉曲(~ような)といった複数の意味があります。「じ」はこの中の「推量」と「意志」の意味を打ち消す形で使われます。
- 「む」の推量(~だろう) → 「じ」の打消推量(~ないだろう)
- 「む」の意志(~しよう) → 「じ」の打消意志(~まい、~ないつもりだ)
このように、「む」の意味と対比させて考えると、「じ」が持つ二つの主要な意味(打消推量・打消意志)をスムーズに理解できます。古文の助動詞は数が多く、意味も多岐にわたるため、関連付けて覚えることは非常に有効な学習法となります。
助動詞「じ」と「まじ」の違いは?
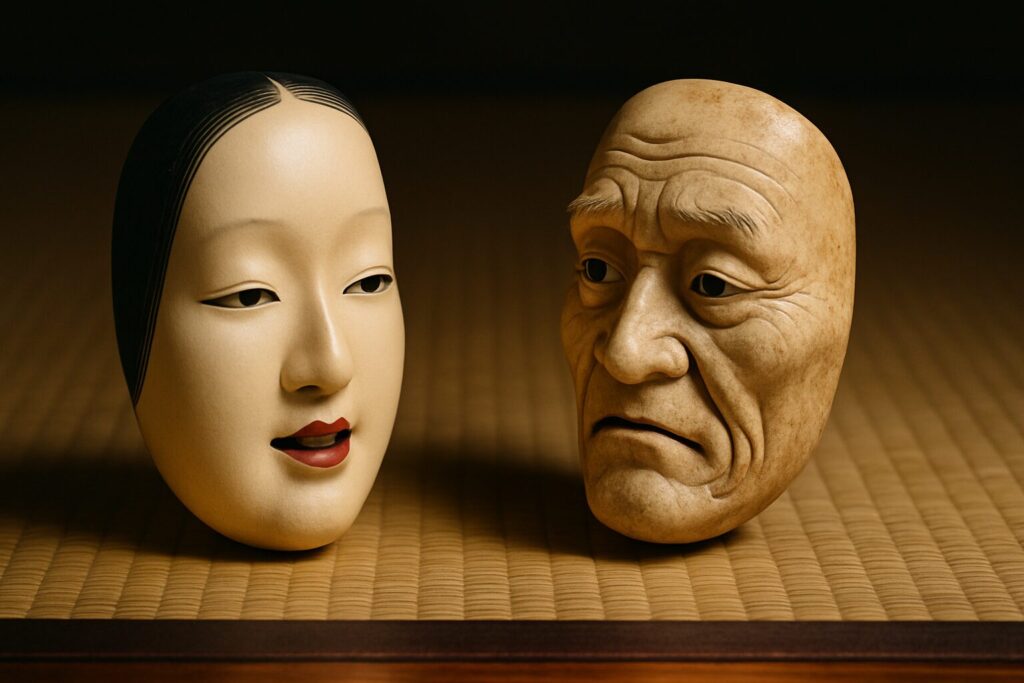
助動詞「じ」としばしば混同されやすいのが、同じく打ち消しの意味を持つ助動詞「まじ」です。これらは意味が似ている部分もありますが、明確な違いがあります。
主な違いは以下の通りです。
| 特徴 | 助動詞「じ」 | 助動詞「まじ」 |
|---|---|---|
| 意味 | ①打消推量 (~ないだろう) ②打消意志 (~まい) | ①打消推量 (~ないだろう) ②打消意志 (~まい) ③打消当然 (~はずがない) ④不適当・禁止 (~べきでない・~てはならない) ⑤不可能推量 (~できそうにない) |
| 活用 | 不変化型 (じ・じ・じ) | 形容詞シク活用型 (まじく・まじ・まじき・まじけれ) |
| 接続 | 未然形 | 終止形 (※ラ変型活用には連体形) |
| 関係性 | 「む」の打ち消し | 「べし」の打ち消し |
「じ」は「む」の打ち消しであり、意味は打消推量・打消意志の2つが基本です。
接続は未然形、活用は特殊型です。
一方、「まじ」は「べし」の打ち消しと考えられ、意味が打消推量・打消意志に加えて、打消当然、不適当・禁止、不可能推量と多岐にわたります。接続は終止形(ラ変型には連体形)、活用は形容詞シク活用型です。
このように、意味の数、活用、接続の点で異なるため、文脈で見分ける必要があります。特に接続する語の形(未然形か終止形/連体形か)は大きなヒントになるでしょう。
助動詞「じ」の意味と見分け方・練習問題

ここでは、助動詞「じ」が持つ具体的な意味と、文脈の中でどのように意味を見分けるか、そして実際の練習問題を通して理解を深めていきます。
- 助動詞「じ」2つの意味と見分け方
- 意味① 打消推量「~ないだろう」
- 意味② 打消意志「~ないつもりだ」
- 現代語「~まい」との関連性
- 例文で確認!助動詞「じ」の短文練習問題
- 読解に挑戦:助動詞「じ」の長文練習問題
助動詞「じ」2つの意味と見分け方

前述の通り、助動詞「じ」には主に「打消推量」と「打消意志」の二つの意味があります。文脈の中でどちらの意味で使われているかを見分けるには、多くの場合、文の主語に注目するのが有効です。
- 主語が一人称(私、我など)の場合:多くは「打消意志」(~ないつもりだ、~まい)の意味になります。話し手自身の行動に対する否定的な意志を表します。
- 主語が三人称(彼、彼女、それ、特定の人名など)の場合:多くは「打消推量」(~ないだろう)の意味になります。話し手以外の人物や事物に対する否定的な推測を表します。
- 主語が二人称(あなた、そなたなど)の場合:文脈によりますが、打消意志(~するな、~するつもりはないだろう)や、打消推量(~ないだろう)のどちらの可能性もあります。ただし、二人称主語の例は比較的少ないです。
これはあくまで一般的な傾向であり、絶対的なルールではありません。しかし、意味を判断する際の大きな手がかりとなるため、まずは主語の人称を確認する習慣をつけると良いでしょう。最終的には文脈全体を読んで判断することが重要です。
意味① 打消推量「~ないだろう」

打消推量は、ある事柄に対して「そうではないだろう」「~ないだろう」と否定的に推測する意味を表します。現代語訳では「~ないだろう」や「~まい」と訳されます。
この意味は、主に文の主語が三人称(話し手・聞き手以外)のときに用いられることが多いです。
【例文】
- 荒雄は帰り来じか。(万葉集)
- (訳)荒雄は帰って来ないだろうか。
- (解説)主語である「荒雄」(三人称)の帰還について、否定的に推量しています。
- 一生の恥、これに過ぐるはあらじ。(竹取物語)
- (訳)一生の恥で、これ以上のものはないだろう。
- (解説)「これに勝るもの」という事物(三人称相当)が存在しないだろうと推量しています。
- 法師ばかりうらやましからぬものはあらじ。(徒然草)
- (訳)僧侶ほどうらやましくないものは(この世に)ないだろう。
- (解説)「うらやましくないもの」という存在(三人称相当)について、法師が最たるものだろうと推量しています。
このように、自分や相手以外の人物の行動や、物事の状態について否定的に推し量る場合に打消推量の意味となります。
意味② 打消意志「~ないつもりだ」

打消意志は、話し手自身が「~しないつもりだ」「~すまい」と、何かをしないという否定的な意志を示す意味です。現代語訳では「~ないつもりだ」「~まい」となります。 この意味は、主に文の主語が一人称(私、我など)のときに用いられます。
【例文】
- さらば、御供には率て行かじ。(竹取物語)
- (訳)それならば、お供には連れて行かないつもりだ。
- (解説)主語は省略されていますが、文脈上かぐや姫(一人称)が供に対して「連れて行かない」という意志を示しています。
- われは(和歌を)詠めとも言はじ。(枕草子)
- (訳)私は(あなたに和歌を)詠めとは言うまい(言うつもりはない)。
- (解説)主語「われ」(一人称)が「言わない」という意志を明確に示しています。
- 勝たむとうつべからず。負けじとうつべきなり。(徒然草)
- (訳)(双六は)勝とうと思って打つべきではない。負けまい(負けないつもりだ)と思って打つべきである。
- (解説)主語は省略されていますが、双六を打つ人(一人称)が「負けない」という意志を持つべきだと述べています。
自分の行動に対して「~しないぞ」という決意を表す際に、打消意志の意味で「じ」が使われます。
現代語「~まい」との関連性
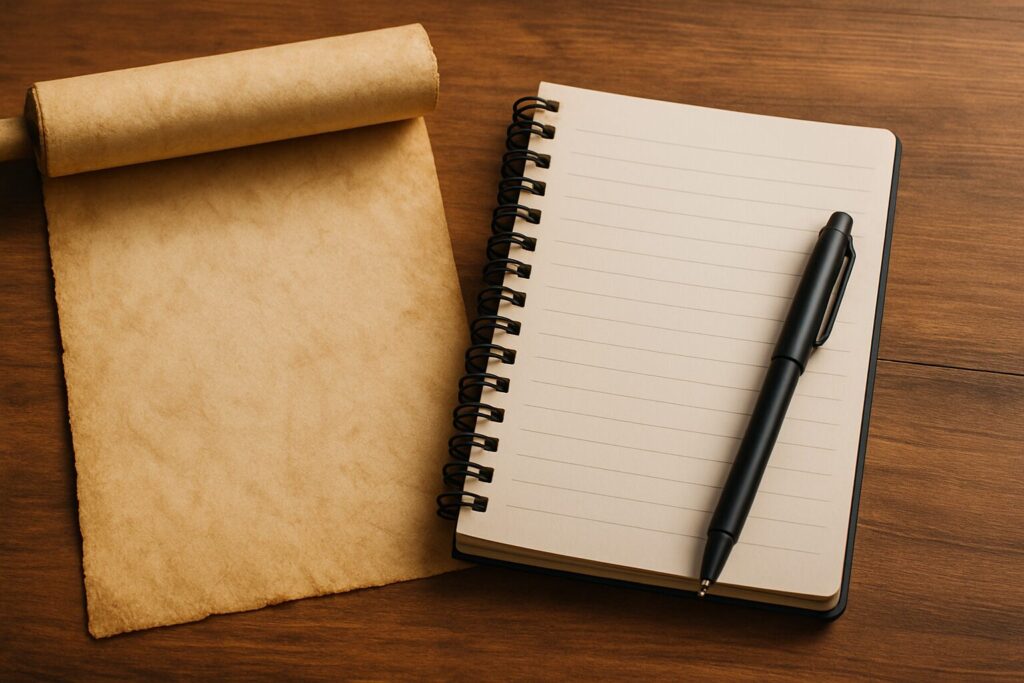
古文の助動詞「じ」の意味を考えるとき、現代語の助動詞「まい」との関連性を知っておくと理解が深まります。現代語の「まい」は、古語の「じ」や「まじ」が変化して受け継がれたものと考えられています。
現代語の「まい」にも、主に二つの意味があります。
- 打消しの推量:「彼はもう来まい」(彼はもう来ないだろう)
- 打消しの意志:「もう二度と行くまい」(もう二度と行かないつもりだ)
これは、古語の「じ」が持っていた「打消推量」と「打消意志」の意味とほぼ対応しています。 例えば、「一生の恥、これに過ぐるはあらじ」を現代語的に言えば「これ以上の恥はあるまい」となり、「われは詠めとも言はじ」は「私は詠めとは言うまい」となります。
このように、現代語の「まい」の感覚を参考にすることで、古文の「じ」のニュアンスを掴みやすくなる場合があります。ただし、古語と現代語では言葉の用法が完全に一致するわけではないので、あくまで参考程度と考えるのが良いでしょう。
例文で確認!助動詞「じ」の短文練習問題
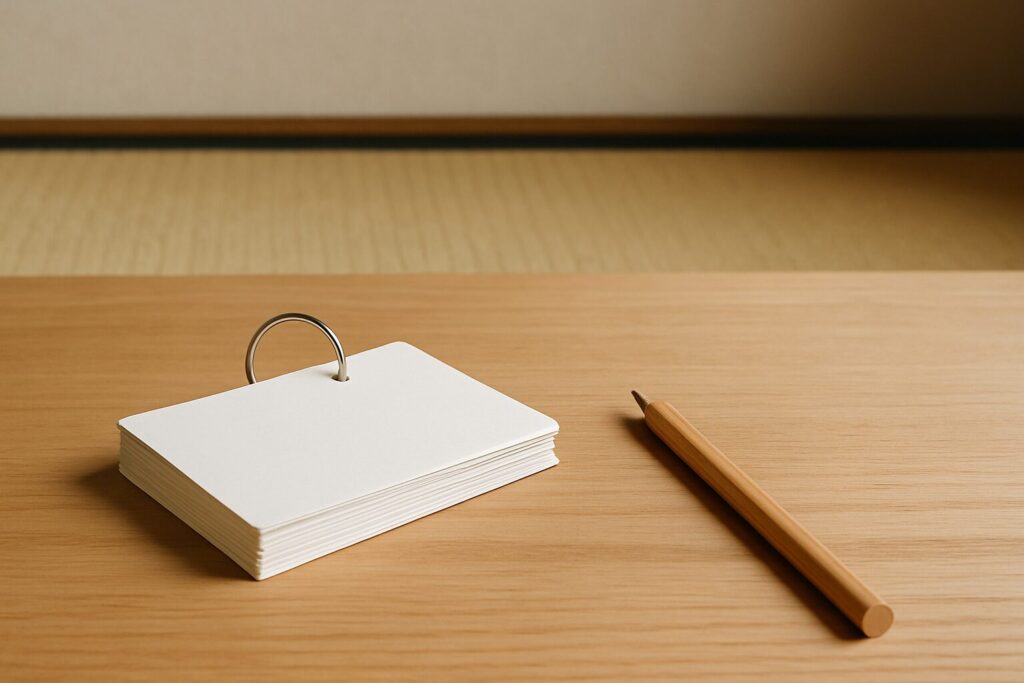
ここまでの内容を踏まえて、助動詞「じ」の理解度を確認する簡単な練習問題に挑戦してみましょう。
問題1 次の文の太字部分「じ」の文法的意味(打消推量/打消意志)と活用形を答えなさい。
(すごろく双六は)勝たんと打つべからず。負けじと打つべきなり。(徒然草・一一〇)
解答1
- 文法的意味:打消意志
- 活用形:終止形
解説1 文脈から、双六を打つ人(一人称)が「負けないつもりだ」という意志を持つべきだと述べています。主語が一人称と考えられるため、打消意志と判断できます。「じ」は活用しないため、基本的な形である終止形と判断します。(※文脈によっては「と」に続くため連用形とする考え方もありますが、特殊型のため終止形とするのが一般的です。)
問題2 次の文の太字部分「じ」の文法的意味(打消推量/打消意志)と活用形を答えなさい。 おしなべて峰も平らになりななむ山のはなくは月も入らじを(伊勢物語・八二)
解答2
- 文法的意味:打消推量
- 活用形:連体形
解説2 主語は「月」(三人称)です。山の稜線がなければ月も(そこに)入らないだろう、と推量しています。主語が三人称であることから打消推量と判断できます。文末に助詞「を」が続き、体言(形式名詞)が省略されていると考えられるため、連体形となります。
問題3 次の文の空欄に「じ」または「まじ」のどちらかを適切な形にして入れなさい。
法師ばかりうらやましからぬものはあら( )。(徒然草・一)
解答3 じ
解説3 「うらやましくないもの」という事物(三人称相当)について、「存在しないだろう」と推量しています。打消推量の意味で、動詞「あり」の未然形「あら」に接続するため、「じ」が入ります。文末なので終止形です。
問題4 次の文の太字部分「じ」の文法的意味(打消推量/打消意志)を答えなさい。
一生の恥、これに過ぐるはあらじ。(竹取物語)
解答4 文法的意味:打消推量
解説4 主語は「これに過ぐる(もの)」(三人称相当)です。「これ以上にまさる(恥)はないだろう」と推量しています。主語が三人称相当であることから打消推量と判断できます。文末なので終止形です。
問題5 次の文の太字部分「じ」の文法的意味(打消推量/打消意志)を答えなさい。
「京にはあらじ。東の方に住むべき国求めに。」とて行きけり。(伊勢物語・九)
解答5 文法的意味:打消意志
解説5 主語は省略されていますが、「東の方に住むべき国求めに行く」人物(一人称)です。その人物が「京には住むまい、住まないつもりだ」という意志を表しています。主語が一人称と考えられるため、打消意志と判断できます。引用の「と」の前にあるため終止形です。
問題6 次の文の太字部分「じ」の文法的意味(打消推量/打消意志)を答えなさい。
さらば、ただ心にまかせよ。われはよめとも言はじ。(枕草子・九九段)
解答6 文法的意味:打消意志
解説6 主語が「われ」(私・一人称)と明示されています。「私は(和歌を)詠めとは言うまい、言うつもりはない」という話し手自身の意志を表しています。主語が一人称であるため、打消意志です。文末なので終止形です。
問題7 次の文の太字部分「じ」の文法的意味(打消推量/打消意志)を答えなさい。
さらば、御供には率て行かじ。(竹取物語)
解答7 文法的意味:打消意志
解説7 主語は省略されていますが、文脈上かぐや姫(一人称)が「(帝の使者の)お供にはついて行かないつもりだ」という意志を示しています。主語が一人称と考えられるため、打消意志と判断できます。文末なので終止形です。
問題8 次の文の太字部分「じ」の文法的意味(打消推量/打消意志)と活用形を答えなさい。
わが道ならましかば、かくよそに見侍らじものを。(徒然草・一六七段)
解答8
- 文法的意味:打消意志
- 活用形:連体形
解説8 主語は省略されていますが、「わが道」(私の専門分野)という言葉から筆者自身(一人称)と考えられます。「もし自分の専門分野であったなら、このようにただ見ているだけということはすまい、しないつもりなのに」という意志(反実仮想)を表しています。主語が一人称と考えられるため打消意志です。文末に助詞「ものを」が続いているため連体形です。
読解に挑戦:助動詞「じ」の長文練習問題

最後に、実際の古文の中で助動詞「じ」がどのように使われているか、少し長めの文章で確認してみましょう。
問題文 徒然草・十段より。後徳大寺左大臣と西行法師に関する逸話の一節です。
後徳大寺大臣の、寝殿に鳶ゐさせじとて縄を張られたりけるを、西行が見て、「鳶のゐたらむは、何かは苦しかるべき。この殿の心さばかりにこそ」とて、その後は参らざりけると聞き侍るに、(後略)
問題 太字「じ」の文法的意味(打消推量/打消意志)を答えなさい。
解答 打消意志
解説 ここでは、後徳大寺大臣が「(自分の)寝殿に鳶をとまらせまい、とまらせないつもりだ」と考えて縄を張った、という状況が描かれています。主語である大臣(三人称)自身の意図・意志を表しているため、「打消意志」と判断するのが適切です。「~とて」(~と思って)という引用の助詞が伴っていることも、意志を表す文脈であることを補強しています。このように、「じ」は基本的に一人称主語で打消意志を表すことが多いですが、文脈によっては三人称主語の人物の意志を表すためにも用いられます。
助動詞「じ」の重要ポイント

記事のポイントを以下にまとめました。参考になったらうれしいです。
- 助動詞「じ」は打消推量・打消意志を表す
- 打消推量の訳は「~ないだろう」である
- 打消意志の訳は「~ないつもりだ」「~まい」である
- 助動詞「む」の推量・意志を打ち消す働きを持つ
- 「む」の否定形と捉えると理解しやすい
- 接続は活用する語の未然形である
- 活用は不変化型(じ・じ・じ)で形はほぼ変わらない
- 活用形には未然形・連用形・命令形がない
- 已然形は係り結びの場合に稀に見られる
- 意味の見分けは主に文の主語の人称で行う
- 主語が一人称の場合は打消意志が多い
- 主語が三人称の場合は打消推量が多い
- 現代語「まい」の由来の一つとされる
- 同じ打消の助動詞「まじ」とは異なる点が多い
- 「まじ」とは接続・活用・意味の数で区別が必要