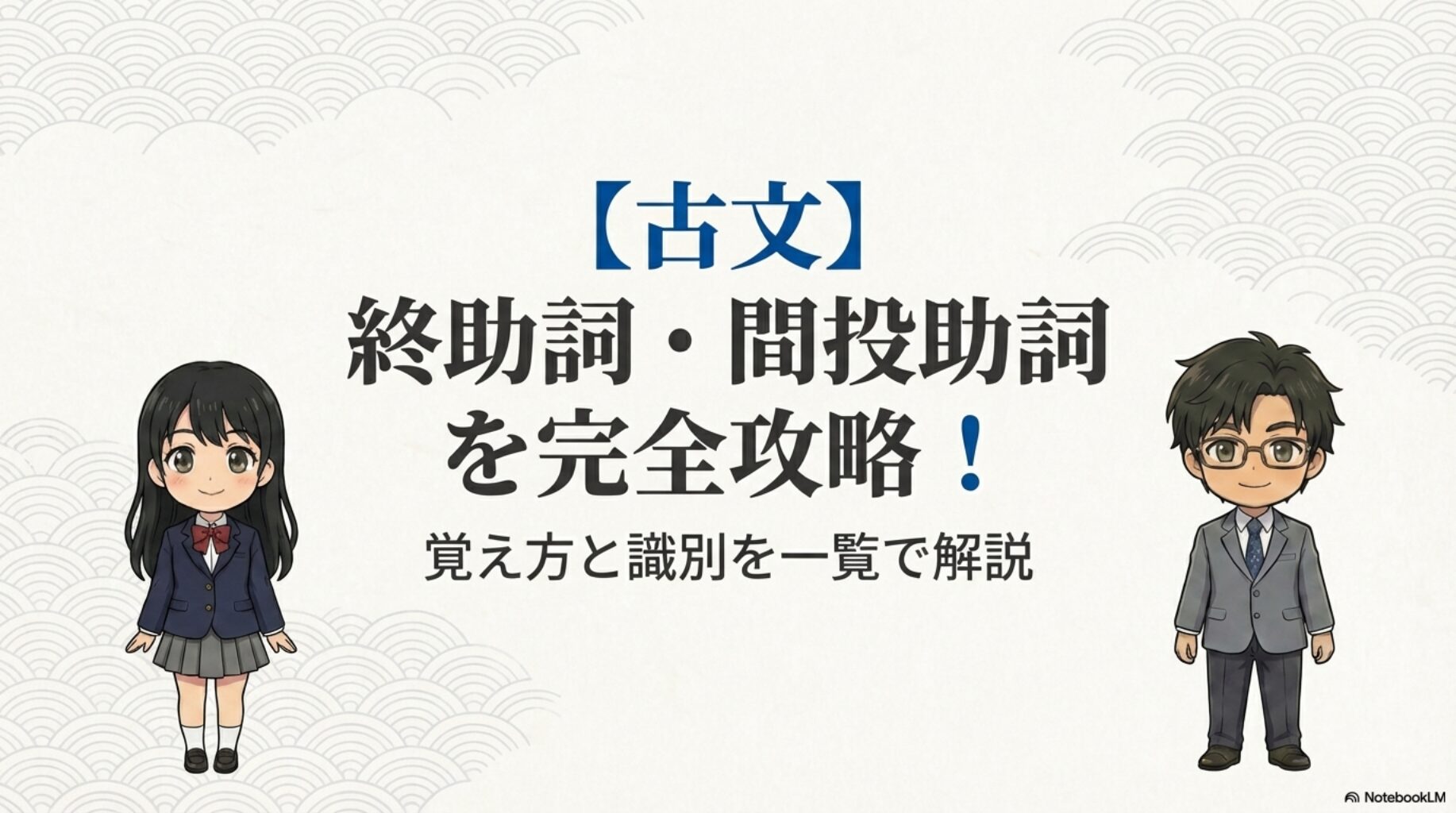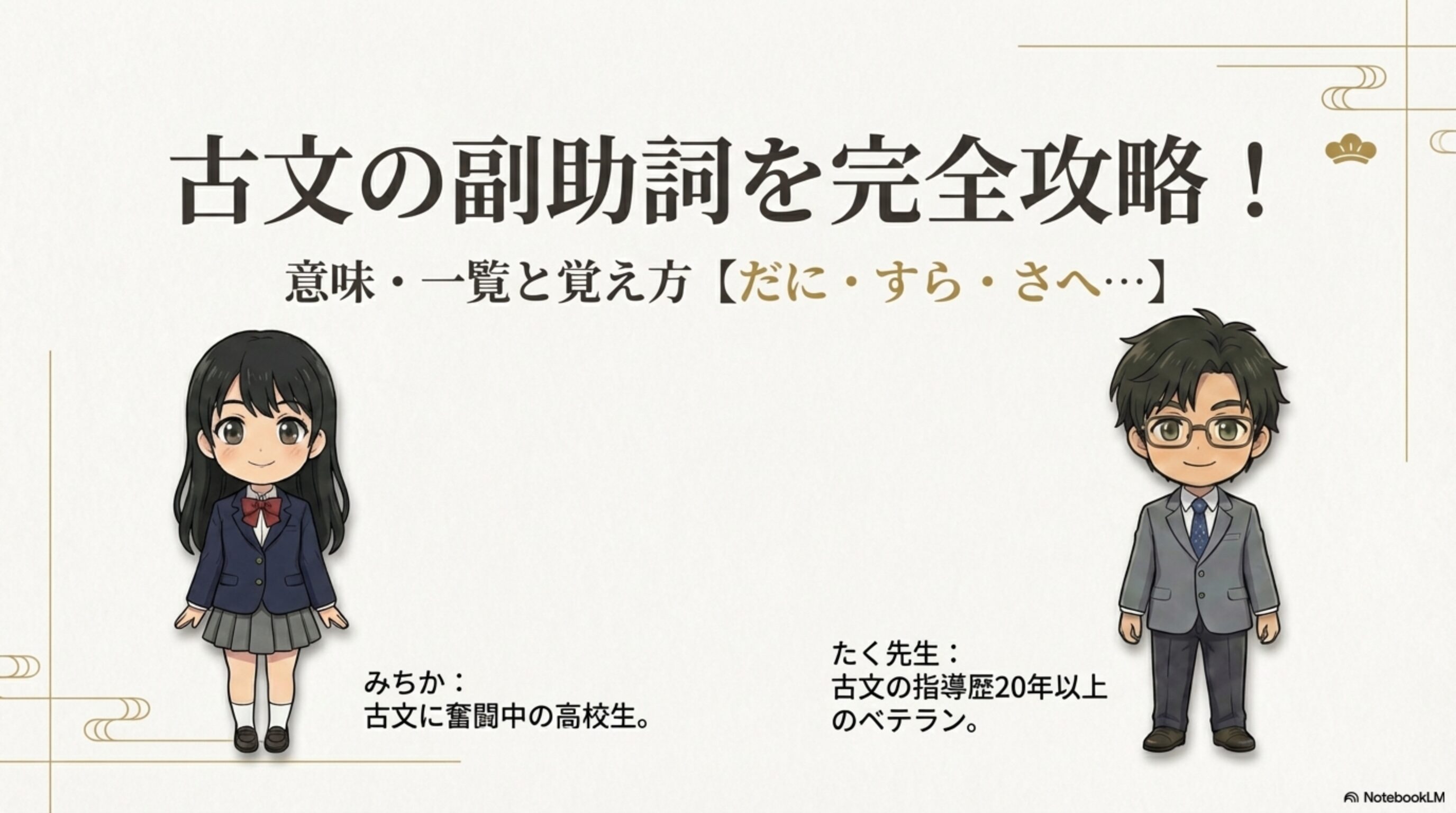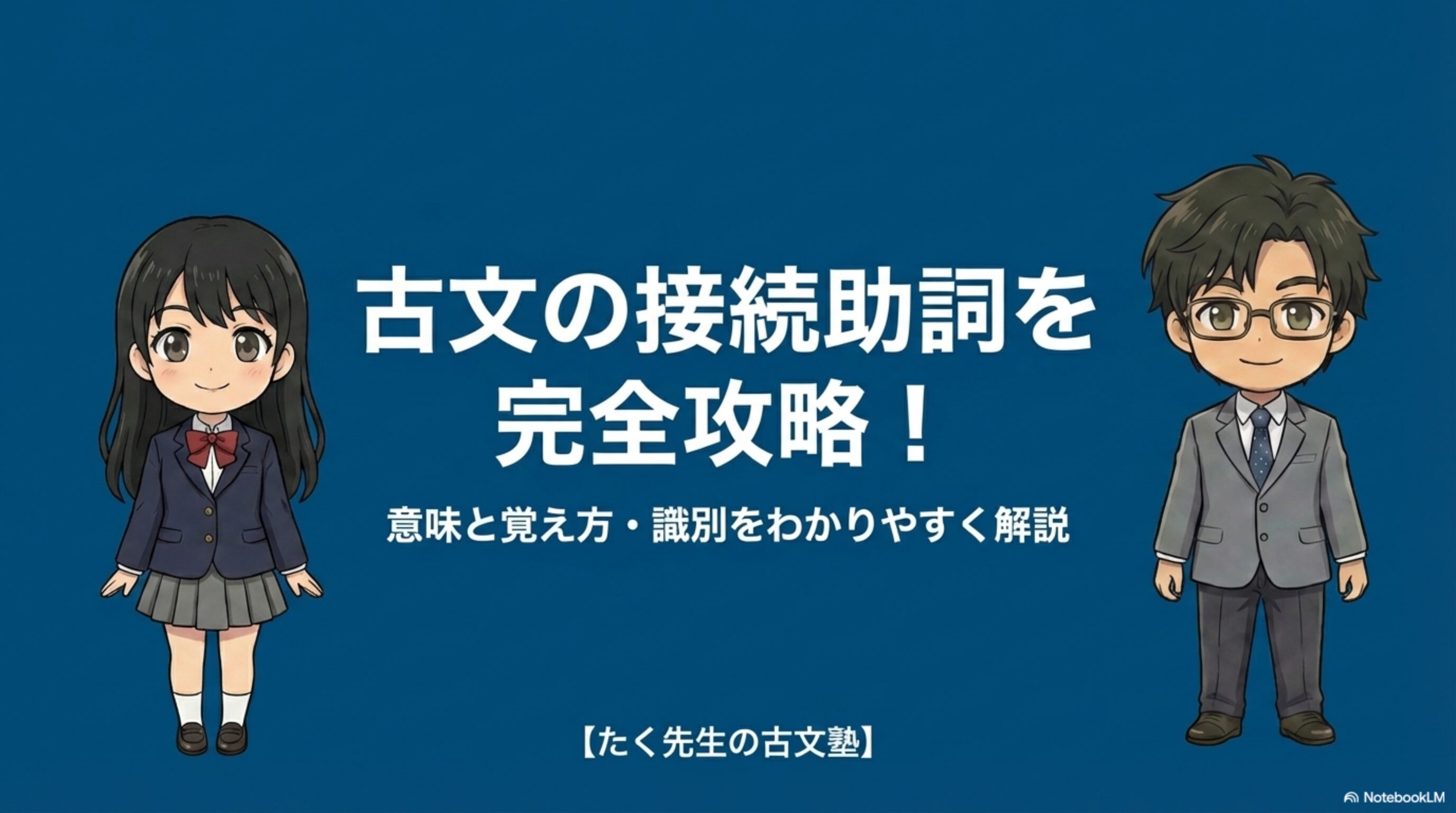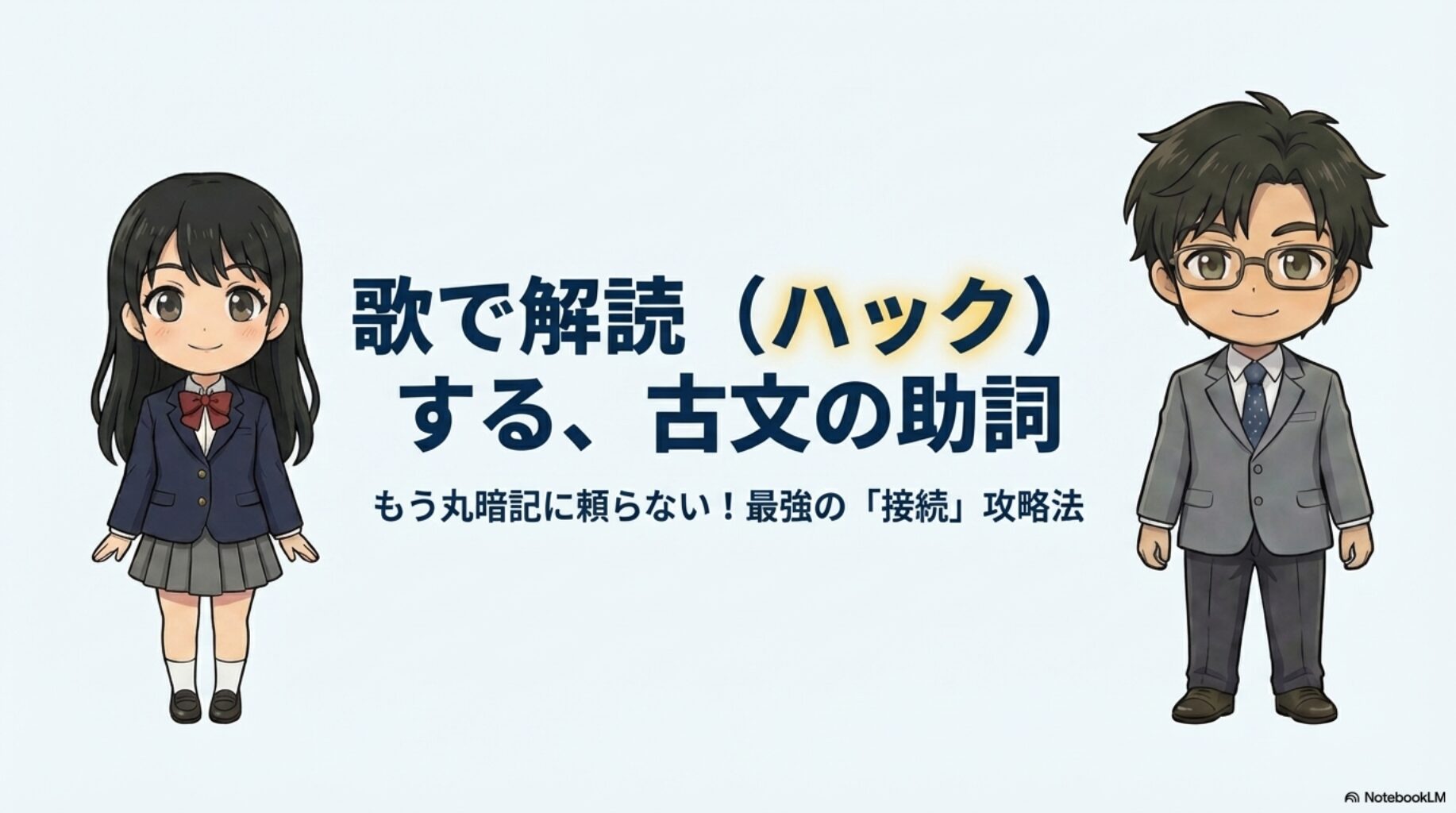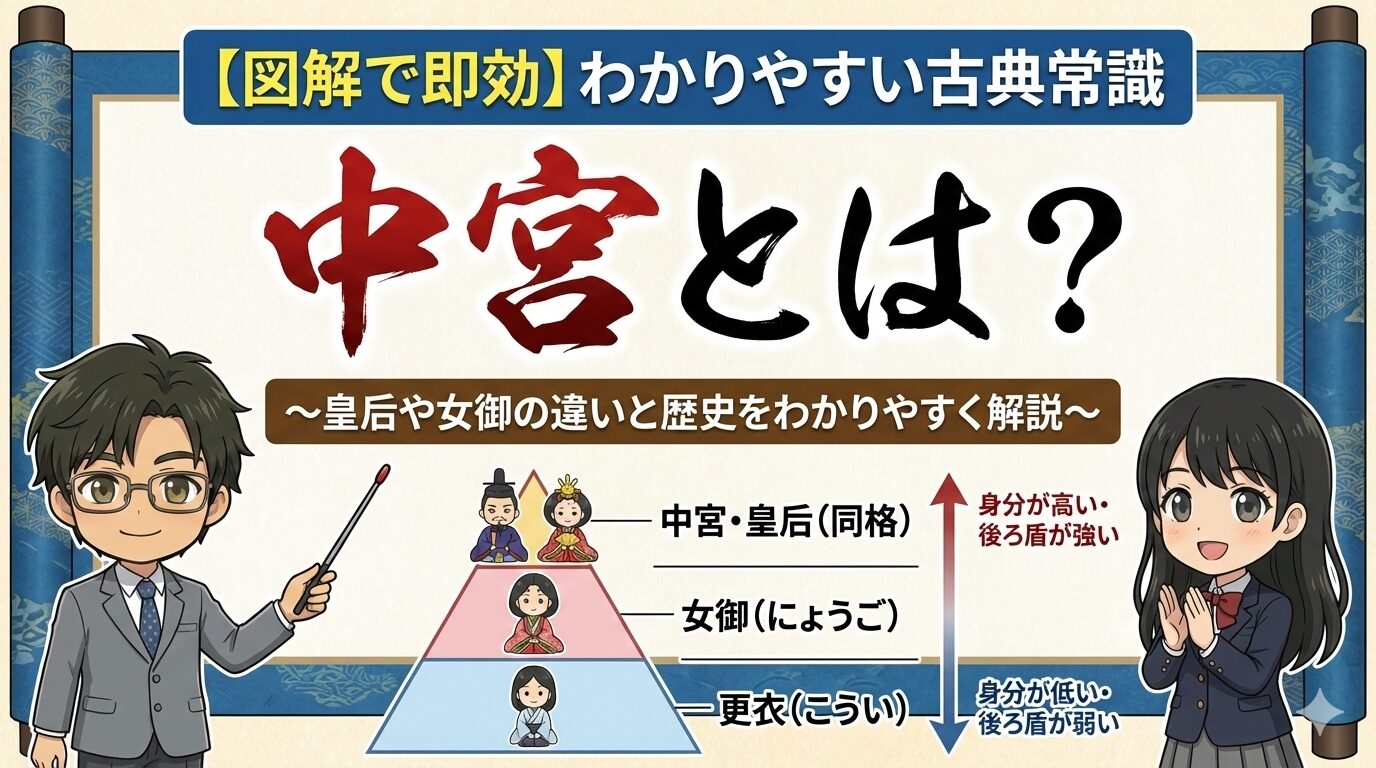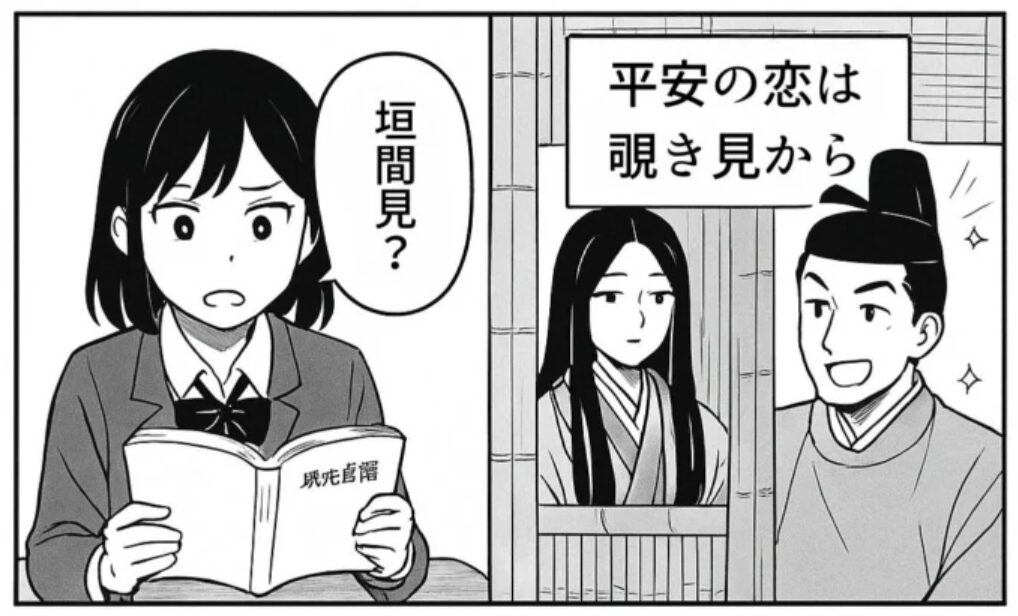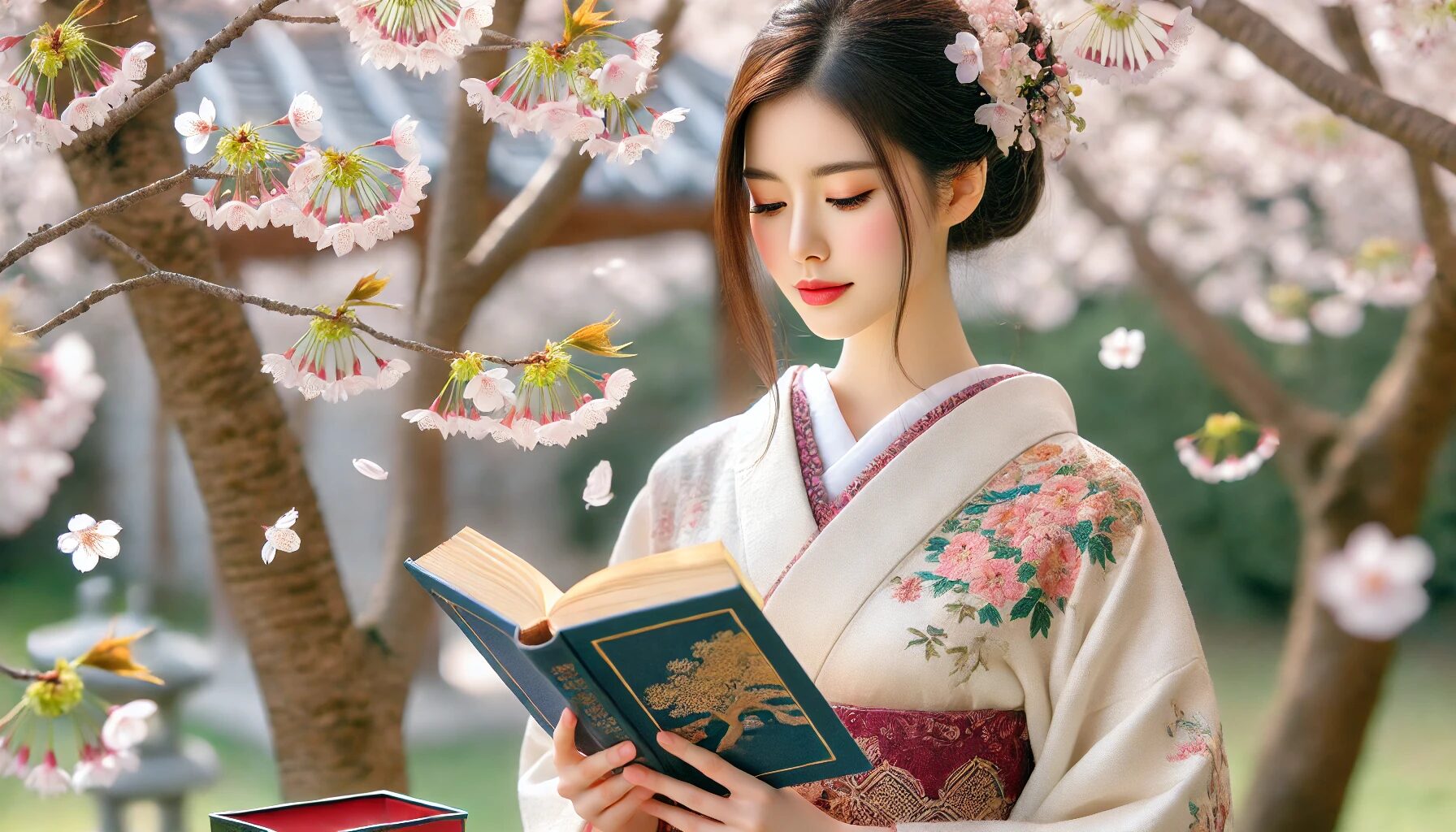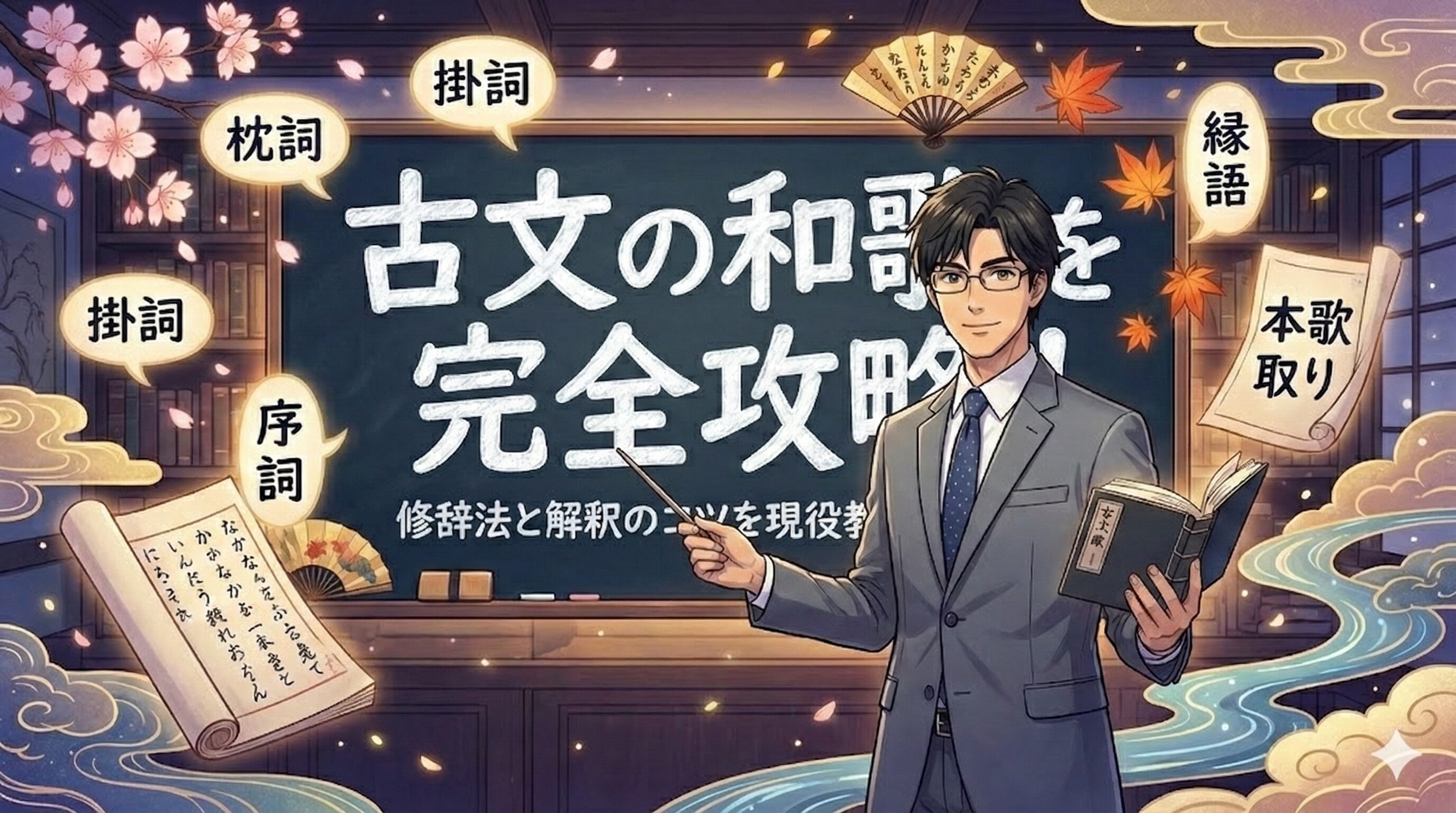方違えとは?古文が楽しくなる平安時代の風習を解説
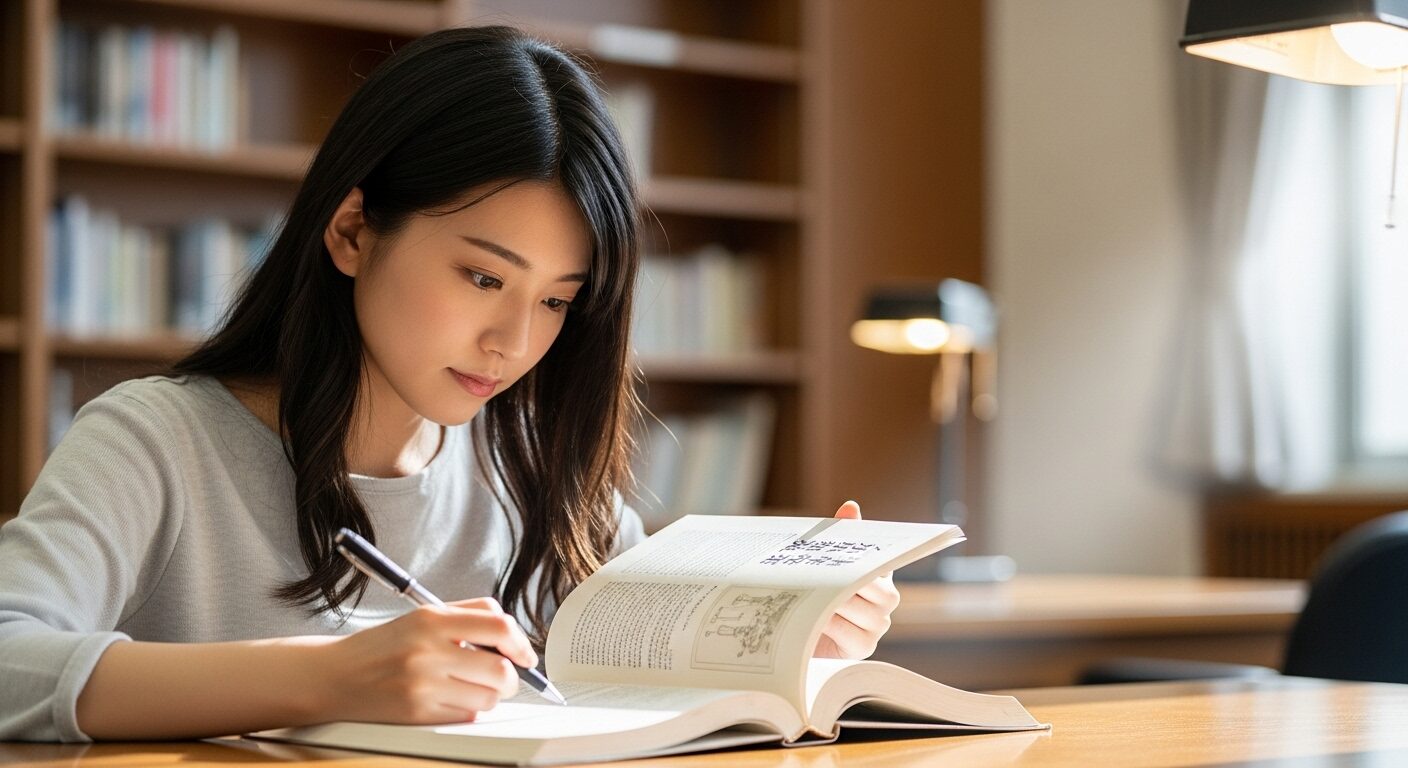
こんにちは。ミチプラス、運営者の「たく先生」です。
古文の授業で「方違え(かたたがえ)」という言葉が出てきて、「なんだかよくわからないな…」と感じたことはありませんか?
源氏物語や枕草子を読んでいると当たり前のように出てくるこの風習、一体何のために、どんなやり方をしていたのか気になりますよね。平安時代の陰陽道と深く関わっているらしいけど、なんだか難しそう…と感じるかもしれません。
実はこの方違え、現代の私たちの生活にも、引越しや旅行の際の「方位除け」や「八方除け」といった形で、その考え方がちょっぴり残っているんです。この記事では、そんな方違えの基本的な意味から、古典文学での描かれ方、そして現代にも通じる豆知識まで、わかりやすく解説していきます。この記事を読めば、平安貴族の行動の裏側がわかり、古文の世界がもっと面白く感じられるようになるはずですよ。
古文が面白くなる平安時代の「方違え」とは

まずは「方違え」の基本から見ていきましょう。言葉の意味や当時の人々がどんなことをしていたのかを知るだけで、古典の世界がぐっと身近になりますよ。平安貴族の行動の裏には、彼らなりのルールや世界観があったんですね。
方違えの基本的な意味を知ろう
方違え(かたたがえ)とは、平安時代に広く行われていた、災いを避けるための非常に合理的(?)な風習のことです。「方忌み(かたいみ)」とも呼ばれていました。
例えば、あなたが出かけようとしたとき、目的地の方角が陰陽道の占いで「凶方位(きょうほうい)」、つまり縁起が悪い方角だとされたとします。そんなとき、平安貴族たちは「じゃあ、行くのをやめよう」とはなりませんでした。
直接その方角へ向かうのをやめて、前日の夜にいったん別の方角にある知人の家などで一泊し、翌朝そこを新たな出発点として目的地へ向かう、これが「方違え」です。
こうすることで、目的地への方角そのものを変えてしまう、というわけですね。物理的に移動のベクトルをずらすことで、凶方位を吉方位(きちほうい)に変えるという、なんともユニークで前向きな発想だなと私は思います。
平安時代の具体的なやり方とは?

では、平安貴族たちは具体的にどのように方違えを実践していたのでしょうか。そのやり方は、単なる移動以上に、当時の社会的なつながりを反映したものでした。
方違えをするときは、前日の夜のうちに、友人や親戚、知人の邸宅など、目的地とは違う吉方位にある場所へ移動して一泊するのが一般的でした。
そして、ここが非常に面白いポイントなのですが、方違えで宿泊客を迎えた家の主人(あるじ)は、その客に食事やお酒を振る舞い、手厚くもてなすのが当然のマナーとされていたんです。
つまり、方違えは単に災いを避けるための個人的な儀式というだけでなく、貴族同士の社交の場としても重要な機能を持っていたんですね。現代で言えば、「終電を逃したから泊めて!」というのとは少し違い、もっと儀礼的で、お互いの関係性を確認し合うようなフォーマルなイベントだったのかもしれません。
この風習が貴族社会に定着していたことは、10世紀初頭の和歌集である『古今和歌集』にも「方たがへに人の家にまかれりける時に」という記述があることからもわかります。(出典:国立国会図書館デジタルコレクション『古今和歌集』)
陰陽道がもたらした独特の風習

そもそも、なぜ平安貴族たちはこれほどまでに方角の吉凶を気にしたのでしょうか。その思想的な背景には、当時の社会に絶大な影響力を持っていた「陰陽道(おんみょうどう)」があります。
陰陽道は、古代中国で生まれた陰陽五行説をベースに、天文学や暦、占いなどが日本で独自に発展した思想体系です。平安時代の貴族たちは、この陰陽道の教えを、政治や儀式はもちろん、日々の生活の隅々にまで取り入れていました。
日本独自の発展
方角に関する禁忌の思想そのものは中国から伝わったものですが、「凶方位を避けるために、わざわざ別の場所に一泊して方角を変える」という「方違え」の具体的な実践方法は、実は日本で独自に発展した風習なんです。外からの文化をそのまま受け入れるのではなく、自分たちの生活様式に合わせて柔軟に作り変えていく、日本人らしい工夫がここにも見られますね。
記録としては、9世紀の歴史書『三代実録』に、天皇が方違えに似た行動をとったという記述があり、これが最古の記録とされています。天皇自らが行うほど、重要な慣習だったことがうかがえます。
なぜ?凶方位を避ける理由
凶方位を避けた直接的な理由は、その方角に「方位神(ほういじん)」と呼ばれる、ちょっと気難しい神様たちがいると考えられていたからです。
これらの神様は、定められた周期で各方位を移動(遊行)するとされ、神様がいる方角は「方塞がり(かたふさがり)」と呼ばれました。この方角にまっすぐ進むことは、神様を「犯す」行為とされ、祟りや災難を招くと信じられていたのです。
特に注意された主な方位神
平安貴族が特に気にしていた方位神には、以下のような神様がいました。それぞれ移動のペースや滞在期間が違うのが特徴です。
| 神名 | 特徴 |
|---|---|
| 天一神(てんいちじん/なかがみ) | 5~6日周期で方角を移動する、最も日常的に意識された神様。平安時代の方違えのほとんどは、この天一神を避けるためだったと言われています。 |
| 金神(こんじん) | 1年間同じ方角に留まる、特に恐れられた凶神。この方角での建築や移転は絶対に避けられました。 |
| 大将軍(だいしょうぐん) | 3年間同じ方角に留まる強力な神様。ただし、時々別の場所へ短期出張(遊行)することもありました。 |
ちなみに、天一神が天上に帰っている16日間は「天一天上(てんいつてんじょう)」と呼ばれ、この期間は神様の祟りがないため、どの方角へも自由に移動できるラッキー期間とされていました。
現代の引越しや旅行での豆知識

「さすがに今はそんなこと気にしないよ」と思うかもしれませんが、実はこの「方違え」の考え方は、形を変えながら現代にもしっかりと息づいています。
特に、引越しや長期の旅行、家の新築といった人生の大きな節目では、方位の吉凶を気にする文化が根強く残っています。現代的な解釈では、凶方位への移動は、健康運や金運、人間関係に悪い「気」や「エネルギー」をもたらす、と考えられることが多いようです。
もし目的地が凶方位だった場合、現代人はどうするのでしょうか?平安貴族のように友人の家に泊まるのは難しいですが、現代ならではの「方違え」が実践されることがあります。
現代版「方違え」の3つの方法
- 仮住まいをする(本格派):新居が凶方位の場合、まず吉方位にある物件に一時的に住み、そこを新たな拠点としてから最終的な新居へ引っ越す方法です。
- ホテルなどで一泊する(実践派):引越しの前日に、現在の家から見て吉方位にあるホテルなどに一泊し、翌日そこから新居へ向かう、より手軽な方法です。
- 移動ルートを工夫する(お手軽派):引越し当日、トラックや車で移動する際に、意図的に一度吉方位へ向かってから目的地へ進路を変える方法。気休めかもしれませんが、何もしないよりは良いとされています。
昔の人の知恵が、現代の私たちの不安を和らげるために応用されていると思うと、なんだか興味深いですよね。
古典文学から学ぶ「方違え」の読み解き方

方違えの基本がわかったところで、次は古典文学の有名な作品にどう描かれているかを見ていきましょう。この知識があると、物語の登場人物たちの「なぜ、ここでこんな行動を?」という疑問が解け、物語の解像度がぐっと上がりますよ。
源氏物語に描かれた恋のきっかけ
古典文学の最高傑作、紫式部の『源氏物語』において、方違えは物語を劇的に動かす重要な装置として使われています。
有名な「帚木(ははきぎ)」の巻。主人公の光源氏が、友人たちと女性談議に花を咲かせた「雨夜の品定め」を終えた夜のことです。正妻である葵の上のいる左大臣邸へ帰ろうとしますが、内裏から見てその方角が、方位神のいる「方塞がり」であることが判明します。
そこで光源氏は、急遽、部下である中流貴族・紀伊守(きいのかみ)の邸宅に方違えをすることになります。
そして、本来訪れるはずのなかったその屋敷で、彼は人妻の「空蝉(うつせみ)」と運命的な出会いを果たし、その夜、半ば強引に関係を持ってしまうのです。
もし、この「方違え」という社会的に正当化された口実がなければ、この恋愛沙汰は起こり得ませんでした。方違えは、厳格な宮廷社会の日常から逸脱するための、誰にも非難されない完璧な理由を提供したのです。光源氏は後に、空蝉と再会するために意図的に方違えを口実として利用さえします。
このように、方違えは単なる背景設定ではなく、物語に偶然の出会いやロマンスを生み出すための、非常に巧みなプロット装置として機能しているんですね。
枕草子に見る当時のリアルな日常
一方、清少納言の『枕草子』では、方違えのより社会的な、そしてリアルな一面が切り取られています。
「すさまじきもの(興ざめなもの、がっかりするもの)」をリストアップする有名な段で、彼女はこう書いています。
「方違へに行きたるに、あるじせぬ所」
これは、「方違えで泊まりに行ったのに、その家の主人が(期待していた)もてなしをしてくれないこと」という意味です。特に、季節の変わり目である「節分」の日は、通常よりも盛大なおもてなしが期待されていたため、その日にもてなしがないのは格別に興ざめだ、とまで記しています。
この短い一文から、方違えがいかに公的な儀礼であり、そこには「客をもてなす義務」と「もてなしを受ける期待」という暗黙の社会的ルールが存在したかが、生き生きと伝わってきます。ルール違反は「すさまじきもの」として書き残されるほど、社会的な失態と見なされたのですね。
現代の方位除けと有名な神社

現代では、方違えのために友人の家に泊まることはほとんどありません。その代わりに、凶方位への引越しや旅行が避けられない場合には、神社で「方位除け(ほういよけ)」のご祈祷を受けるのが最も一般的な対策となっています。
これは、神様の力をお借りして、方位に関する災いを取り除いてもらおうという考え方です。全国には、こうした方災除けで特に有名な神社がいくつかあります。
方災除け・八方除けで知られる主な神社
- 方違神社(ほうちがいじんじゃ):大阪府堺市
その名の通り、方災除け信仰の中心地。神社の境内地がかつての三国の境界にあったことから「方位のない清地」とされ、ここをお参りすることで方位の災いをリセットできると信じられてきました。 - 寒川神社(さむかわじんじゃ):神奈川県
「全国唯一の八方除けの守護神」として絶大な信仰を集めています。あらゆる方角から来る災厄をすべて取り払ってくれるとされ、全国から多くの参拝者が訪れます。 - 城南宮(じょうなんぐう):京都府
「方除(ほうよけ)の大社」として知られ、平安遷都の際に都の南を守るために創建された歴史ある神社です。
もし方位が気になることがあれば、こうした神社に相談してみるのも一つの方法かもしれません。ただし、ご祈祷の詳細や受付時間については、必ず各神社の公式サイトで最新の情報を確認するようにしてくださいね。
寝床違えというもう一つの対策
もう一つ、現代的な対策として知られているのが「寝床違え(ねどこたがえ)」という方法です。
これは非常にユニークな対策で、凶方位へ引越してしまった「後」に実践するものです。その考え方は、家の中心から見て、自分にとっての吉方位にあたる部屋に寝室を移したり、ベッドの位置を変えたりすることで、引越しによる凶作用を和らげよう、というものです。
面白いのは、方違えが陰陽道や九星気学の考え方に基づいているのに対し、この寝床違えは主に「風水」の思想に基づいている点です。一般的に「家の外(移動)は九星気学、家の中(配置)は風水」というように、異なるシステムを柔軟に使い分けているのが興味深いなと思います。
八方除けとの違いはなんだろう?
神社でご祈祷を受ける際、「方位除け」と非常によく似た言葉で「八方除け(はっぽうよけ)」というものも耳にすることがあります。この二つ、一体どう違うのでしょうか?
それぞれの役割を簡単にまとめると、以下のようになります。
- 方位除け:特定の「一つの凶方位」に関する災いをピンポイントで取り除くご祈祷。「北東が凶方位だから、そこからの災いを祓ってください」というような、具体的なお願いになります。
- 八方除け:東西南北とその間の八方位、つまり「あらゆる方角」から来る災いをすべて取り除く、より包括的でパワフルなご祈祷です。
「八方塞がり」という、どの方向に行ってもうまくいかないとされる年の厄除けなどには、この八方除けが特に良いとされていますね。
古文読解に活かす方違えの知識
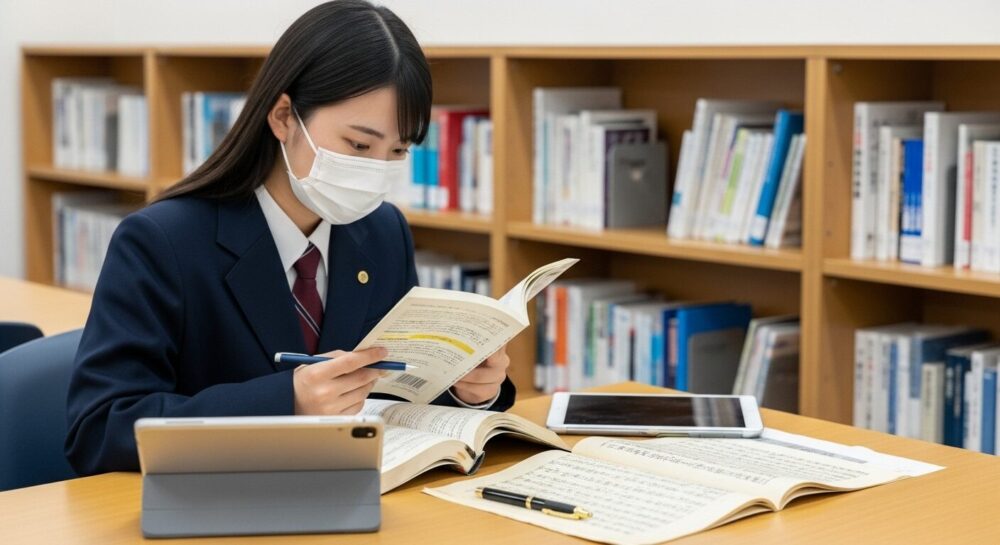
さて、ここまで平安時代の風習である「方違え」について、その意味から現代へのつながりまで、色々と見てきました。
この知識があると、古文の世界がぐっと立体的で、人間味あふれるものに見えてきませんか?
例えば、物語の登場人物がなぜ急に友人の家に泊まることになったのか、なぜそこで予期せぬ出会いや事件が生まれるのか。その背景に「方違え」という、彼らにとっては当たり前のルールがあることを知っているだけで、一見すると突飛に見える行動の一つ一つに「なるほど、そういうことだったのか!」と深く納得できるようになります。
方違えは、単なる昔の迷信として片付けるのではなく、平安貴族たちの世界観や行動原理、そして人間関係を理解するための大切な鍵です。この知識を頭の片隅に置いておくだけで、これからの古文の授業や、古典文学の読書が、きっと何倍も面白く、味わい深いものになるはずですよ。
古文の勉強、お疲れ様でした!
「よし、やるぞ!」と思っても、「でも、文法をゼロから体系的にやり直すのって、独学だと不安だなぁ…」と感じていませんか?
もし、あなたが「元・古文が苦手」だった先生から、センスに頼らない「論理的な解き方」を学びたいなら…
今、多くの受験生から「神授業」と呼ばれている「スタディサプリ 古文」を、私が徹底的に分析した記事がきっと役立つはずです。
なぜ岡本先生の授業がそこまで支持されるのか、ゼロから始める具体的な受講順番まで詳しく解説しています。
古文を「苦手」から「得意」に変える、その具体的な方法に興味がある方は、ぜひ覗いてみてくださいね。
→ 関連記事:スタディサプリ古文が神授業と言われる理由|ゼロから始める最適ルートも解説
この記事を読んで、古文の理解がまた一つ深まりましたね。
でも、古文は「単語」「文法」「読解」「常識」など、全ての知識が有機的につながって初めて高得点が取れる科目です。
「次はどこを勉強すればいいの?」
「苦手なあの分野、どうやって対策しよう?」
そんな迷子にならないよう、ミチプラス内の古文記事を「勉強する順番」に整理した「完全攻略マップ」を作成しました。
辞書代わりにブックマークして、最短ルートで志望校合格を目指しましょう!